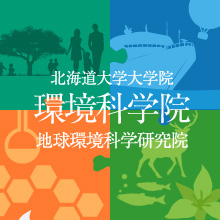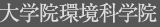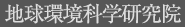プレスリリース
2021-07-05
本学院生物圏科学専攻の山口良文教授(低温科学研究所),東京大学大学院薬学系研究科博士後期課程(当時)の姉川大輔氏,三浦正幸教授らの研究グループは,冬眠する小型哺乳類シリアンハムスターが冬眠の際の低体温に耐えるためにビタミンEを肝臓に高い濃度で保持することを明らかにしました。
シリアンハムスター,シマリス,ジリス,ヤマネなどの小型冬眠哺乳類は,数ヶ月に渡る冬季のあいだ,体温が10ºC以下に低下した深冬眠と呼ばれる低温状態で何日間も過ごします。またこの深冬眠から目覚める際には,体内で熱を多量に作り出すことで体温を37ºC付近まで急激に復温させます。こうした長時間の低温や急激な復温は,私たちヒトを含む冬眠しない哺乳類には致命的なストレスとなります。なぜ冬眠する哺乳類が低温や急激な復温に耐えることができるのか,その仕組みの殆どは未だに不明ですが,これらの動物は細胞レベルでも低温耐性を示すことが幾つかの事例から知られています。そこで研究グループはまず,シリアンハムスターの肝臓の細胞(肝細胞)も,低温培養下で長期生存可能な低温耐性を有することを確認しました。さらに,ビタミンEの少ない餌で飼育されたシリアンハムスターの肝細胞は低温誘導性の細胞死を生じ,この現象はビタミンE投与で回復すること,つまりシリアンハムスターの低温耐性は餌中に含まれるビタミンE量に依存することを発見しました。また低温耐性の異なるシリアンハムスターとマウスの間で,餌由来のビタミンEの保持能力に差があることを見出しました。本研究成果は,ヒトにおける臓器移植や再生医療の際の臓器低温保存や,低体温に伴う障害の予防法の開発にもつながると期待されます。
本研究成果は,2021年6月25日(金)公開のCommunications Biology誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
冬眠哺乳類の低温耐性にビタミン E が関わることを発見~臓器移植・臓器保存への貢献に期待~(PDF)
2021-06-23
本学院環境起学専攻の藤井賢彦准教授(地球環境科学研究院)らは,国立環境研究所地球システム領域の高尾信太郎研究員,海洋研究開発機構の脇田昌英研究員・山本彬友特任研究員,水産研究・教育機構の小埜恒夫主幹研究員と共に,世界的に進行している地球温暖化・海洋酸性化・貧酸素化が将来,北海道沿岸域の水産対象種に対して深刻な影響を及ぼす可能性を指摘しました。そして,深刻な影響を回避するためにはパリ協定で求められている人為起源CO2排出の大幅削減が不可欠であることがわかりました。また,特に環境ストレスに対して脆弱な幼生期にはCO2濃度を人工的に調整した環境で飼育することや,陸域から沿岸域への物質流入を調整すること等,地域における施策も海洋酸性化・貧酸素化影響を軽減する上で有効であると提言しています。
本研究で実施した手法は地球温暖化・海洋酸性化・貧酸素化が水産対象種に及ぼす複合影響の緩和に向けた地域での合意形成・施策のために定量的な科学的指針を提供すると期待されます。
なお,本研究成果は,2021年6月11日(金)公開のFrontiers in Marine Science誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
北海道沿岸域の温暖化・酸性化・貧酸素化影響が明らかに~水産対象種に対する深刻な影響回避には具体的な対策が必要~(PDF)
2021-06-22
本学院地球圏科学専攻博士後期課程の山崎開平さんと青木茂准教授(低温科学研究所),平野大輔助教(低温科学研究所。現所属:国立極地研究所),中山佳洋助教(低温科学研究所),および海洋研究開発機構の勝又勝郎主任研究員らの研究グループは,地球上で最大の海流である「南極周極流」が,南極大陸に向かって拡大することで,南極海の深層が暖まっていることを発見しました。
この研究では,東南極沖を対象とし,海洋現場観測データの時空間解析と数値シミュレーションを組み合わせて解析することで,南極周極流の「南限」が,過去30年間に50km以上南下したことを突き止めました。さらに,海の力学的な分厚さを調べることによって,海洋前線の南下と南北深層循環の強化が,南限の移動を引き起こしていることがわかりました。今回発見された南極周極流の極向き拡大は,海洋の持つ熱が南極氷床へ近づきつつあることを示しています。地球温暖化などによって南極海に吹き付ける偏西風が強くなったことが,その原因である可能性があります。南極海の深層水は南極沿岸付近では最も暖かい水で,南極の氷を融かす主な熱源であると考えられます。暖かい深層水が氷床に向かって流れ込めば,より多くの融け水が海に放出されることで,海面上昇と気候システムに影響することが懸念されます。
本研究は水産庁「開洋丸」による観測航海で取得されたデータを使用しており,科学研究費補助金(課題番号 17H01615, 17H06317, 19K23447, 21H04918, 21K13989)の助成を受けて実施されました。
なお,本研究成果は,2021年6月11日(金)のScience Advances誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
南極大陸に向かって海流が接近中~南極海の深層が暖まるメカニズムを発見~(PDF)
2021-06-09
本学院地球圏科学専攻の山本正伸教授,ブラウン大学地球惑星環境科学科のスティーブ・クレメンス教授らの研究グループは,過去150万年間の南アジアのモンスーン降雨の変動を復元し,モンスーン降雨が日射量の周期的変動だけでなく,大陸氷床量と大気中二酸化炭素濃度の周期的変動に応答していることを明らかにしました。
地球温暖化の進行に伴い,人口稠密なアジア南部の人々の生活や農業に大きな影響を与える南アジアのモンスーンがどのように変化するのか注目されています。
研究グループは,インド東部のベンガル湾で採取した海底堆積物コアに含まれている有孔虫殻の酸素同位体比,植物ワックスの組成や同位体比,化学組成を分析し,ベンガル湾の過去150万年間の塩分,河川からの泥の流出量,雨水の同位体比の変動を復元しました。その結果,モンスーンによるインド東部の降水量は日射量の周期的変動だけでなく,大陸氷床量と大気中二酸化炭素濃度の周期的変動に応答していることを明らかにしました。
これは,二酸化炭素の増加による温暖化に伴い,降雨が増加するという気候モデルによる予測を支持します。
なお,本研究成果は,2021年6月4日(金)公開のScience Advances誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
南アジアのモンスーン降雨の過去と未来を解明(PDF)
2021-06-09
本学院地球圏科学専攻博士後期課程の史穆清さんと白岩孝行准教授及び三寺史夫教授(低温科学研究所)の研究グループは,ロシア科学アカデミー極東支部火山・地震研究所のヤロスラブ・ムラビヨフ博士と共同で,ロシア連邦水文気象環境監視局が管理する河川流量データを用いてカムチャツカ半島から周辺海域に流出する河川の全流量を推定し,河川流量とオホーツク海の高密度陸棚水形成海域の表層塩分に関係があることを見出しました。
海洋に対する河川水の割合はわずか0.003%に過ぎず,河口域や沿岸を除くと,海洋に対する河川の影響はこれまで限定的と考えられていました。本研究は,限られた地域の河川流量が半球規模の海洋循環に影響を与える可能性を示した貴重な成果です。オホーツク海のオーバーターニング(鉛直循環)は,北太平洋の海洋循環を通じて気候に影響だけでなく,栄養塩の循環をも駆動し,オホーツク海や親潮海域の生物生産にも大きく関わっています。そのため,本研究は,オホーツク海のオーバーターニングの機構解明や予測に新たな視点を与えたものと評価されます。
本研究成果は,2021年5月24日(月)公開のJournal of Hydrology: Regional Studies誌にオンライン公開されました。
なお,本研究は,科学研究費補助金・基盤研究A(課題番号:17H01156)の助成を受けて実施されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
新たな陸-海結合システムを発見~オホーツク海のオーバーターニングに与える河川水の影響~(PDF)
2021-05-21
本学院生物圏科学専攻の揚妻直樹准教授(北方生物圏フィールド科学センター)らの研究グループは,屋久島西部の世界自然遺産地域内に生息するニホンジカの固有亜種・ヤクシカの個体群が,2014年以降,減少傾向にあることを明らかにしました。全国的にシカの急増が伝えられている中で,人間による捕獲や駆除がないにも関わらず,シカが継続的に減少することがわかったのは初めてです。
屋久島には,もともとオオカミなどの中・大型肉食動物が分布しておらず,ヤクシカは天敵が不在のまま進化してきました。また,西部の世界遺産地域は,過去およそ50年間シカの捕獲が行われていないため,自然なシカの生態を知ることができる日本に残された希少な場所となっています。
この地域のシカの数は調査を開始した2001年から2014年まで年率9%で増加していました。ところが,それ以降は,年率マイナス15%で減少し始めました。この地域のシカが地域外へ移出する割合は多めに見積もっても年3.5%であったことから,シカの数が増加から減少に転じた原因は,移出ではなく自然要因による死亡率の増加だと考えられました。これらの結果は自然生態系がシカ個体群を調節している可能性を示すものです。ただし,シカ個体群の変動を理解するには数十年単位の継続データが必要であり,現在の減少傾向もいつまで続くのかはわかりません。今後も捕獲することなく,注意深く見守り調査することで,この希少なシカ個体群の理解へと繋げていくことが重要です。
現在,屋久島の世界自然遺産地域では,生態系保護を目的として,駆除によるシカの個体数調整が行われています。しかし,本研究は,自然生態系の調節機能を活かした,人為によらないシカ管理の可能性とその必要性を示唆するものといえます。
なお,本研究成果は,「保全生態学研究」に掲載予定で,2021年4月20日(火)にオンラインで早期公開されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
屋久島世界遺産地域でヤクシカが減少している!~従来の定説を覆す,生態系による制御の可能性を示唆~(PDF)
2021-05-18
本学院地球圏科学専攻の安成哲平助教(北極域研究センター),東京大学先端科学技術研究センターの中村尚教授,三重大学の立花義裕教授及び米国 NASA,韓国UNISTによる国際研究チームは,近年夏季に多発するシベリア・亜寒帯北米(アラスカ・カナダ)の森林火災と西欧の熱波を同時に発生させうる高気圧性循環(気候)パターンを初めて特定し,森林火災由来の大気エアロゾルの増加が夏季北極域とその周辺の高濃度PM2.5の原因であることを初めて明らかにしました。
NASA衛星による火災データやNASAの全球データセットMERRA-2の解析から,近年温暖化の進行が知られている北極域において2003–2017年(15年間)のPM2.5濃度が高い20ヶ月のうち13ヶ月は夏季(7–8月)で,近年多発する森林火災由来の有機炭素エアロゾルから大きな影響を受けていることが明らかとなりました。また,この時の典型的な大気循環場として,西欧に熱波,シベリア・亜寒帯北米(アラスカ・カナダ)に森林火災を同時誘発させうる気候パターンを初めて特定しました。さらに,同期間でユーラシア大陸上の気候変動パターンを表す指標の一つ(Scandinavian pattern index)に基づいて独立解析を行い,この大気循環場との類似性を偶然にも発見し,解析期間を1980年まで延ばしたところ,この気候パターンは2002年以前には見られず,近年にのみ突出して見られることが明らかになりました。夏季に西欧からシベリア,亜寒帯北米にある3つの高気圧が北極周辺を環状に取り囲む特徴から,本研究でこの気候パターンをcircum-Arctic wave (CAW) pattern と命名しました。
本研究で発見された近年のCAWパターン発生・発達メカニズムや温暖化との関係などが今後解明されれば,夏季の西欧熱波やシベリア・アラスカ・カナダの森林火災の同時発生を高精度に予測できる可能性が大いに期待されます。これは同時に,森林火災由来の大気汚染(PM2.5)予測にも直結し,北極及び周辺域の大気汚染対策への貢献も期待されます。
本研究成果は,2021年5月17日(月)公開のEnvironmental Research Letters誌に掲載されました。
なお,本研究は,北極域研究推進プロジェクト(ArCS),北極域研究加速プロジェクト(ArCS II)ほか,複数の研究費による支援を受けて進められました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
北極域の森林火災と西欧熱波を同時誘発させうる気候パターンを初めて特定~北極域とその周辺で起こる夏季森林火災と熱波同時発生予測手法の発展とその高精度化への期待~(PDF)
2021-05-07
本学院環境起学専攻の平田貴文特任准教授(北極域研究センター),同センターのアイリーン・アラビア博士研究員,ならびにアラスカ大学フェアバンクス校の国際共同研究グループは,1990年から2018年までの長期にわたって得られた159種の魚類や無脊椎動物の観測データを用いて,漁業が盛んで気候変動の脅威が継続している東ベーリング海の陸棚海域が,生物多様性の高い海域であることを発見しました。
過去約30年の間に北洋では大きな気候変動が起きています。特に,温暖化と海氷の激減は,生物群集組成を変え,生物多様性の再構成が余儀なくされています。研究グループが東ベーリング海陸棚海域を調査したところ,その北部と南部に,それぞれ生物多様性の高い海域が局所的に存在していました。それらの海域は,研究海域に占める面積が10%程度しかないにもかかわらず,調査種のうちの91%(159種中,144種)の生息地となっていました。さらに,それらの海域では商業魚種(スケトウダラやマダラ)やカニ類(ズワイガニなど)も多く,漁業資源の保護の点からもその海域の重要性が示されました。
また,研究グループは,これらの多様性の高い海域における観測データを用いた解析により,過去約30年間で冬季の海氷や水温変化が比較的小さい気候緩衝海域と一致していることを見出しました。
これらのことから,東ベーリング海で長期にわたって生物生産を維持できる緩衝された気候が,高い生物多様性と安定な群集構造の存在を許容していると考えられます。
本研究成果は,気候変動下で回復力のある海洋生態系及び持続的漁業を維持するために,海洋生物群集の気候変動退避海域(海洋生物が気候変動から逃げ込む海域)の同定および維持の重要性と必要性を提唱しています。
なお,本研究成果は,2021年4月25日(日)オンライン公開のGlobal Change Biology 誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
海洋観測カメラによる有色溶存有機物の観測に成功~超小型人工衛星を利用した北極域観測技術の構築に期待~(PDF)
2021-05-07
本学院環境起学専攻の先崎理之助教と本学大学院農学院の北沢宗大氏,釧路市立博物館の貞國利夫氏,NPO法人おおせっからんどの高橋雅雄氏の研究グループは,国内希少野生動植物種に指定されているシマクイナの繁殖を北海道勇払原野と青森県仏沼で初めて確認しました。
シマクイナは極東に分布する世界最小のクイナ科鳥類です。その生態は謎に包まれていますが,生息数が少なく減少していると思われることから,国内希少野生動植物種に指定されています。しかし,近年,北日本の複数の湿地では夏季に数羽から数十羽のシマクイナが相次いで確認されており,繁殖が疑われていました。
そこで研究グループは,2012年以降に本種が毎年確認されている北海道勇払原野の湿地でシマクイナの繁殖状況を調べました。2018年5~9月に,湿地内の本種の縄張り付近に自動センサーカメラを仕掛け,湿地内の固定ルートを歩いて繁殖の決め手となる本種の子連れの発見を試みました。
その結果,自動センサーカメラではシマクイナの子連れを撮影することは出来なかったものの,目視調査では本種の一組の子連れ(成鳥1羽と巣立ち雛6羽)の観察・撮影に世界で初めて成功し,約110年ぶりに本種の巣を発見しました。さらに,2004年に青森県仏沼で保護・撮影され,種不明とされていたクイナ科鳥類の巣立ち雛が,研究グループの検証によりシマクイナであることが判明しました。これらは日本におけるシマクイナの初めての繁殖記録であり,本種の生態の理解と保全に貢献する重要な成果です。
本研究成果は,2021年4月28日(水)公開のWilson Journal of Ornithology誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
国内希少野生動植物種・シマクイナの国内繁殖を初確認~巣の発見は約110年ぶり,巣立ち雛の撮影は世界初~(PDF)
2021-05-07
本学院地球圏科学専攻の飯塚芳徳准教授,的場澄人助教(低温科学研究所)は,東京工業大学,国立極地研究所,名古屋大学,気象研究所等の研究者らと共に,北極グリーンランドアイスコアの分析から硫酸エアロゾルの生成過程を復元し,1980年以降の二酸化硫黄(SO2)排出削減にもかかわらず,硫酸エアロゾルの減少が鈍化している要因を解明しました。
大気中でSO2から生成される硫酸エアロゾルは,気候変動や健康影響との関連から重要な物質とされています。SO2排出量は排出規制の導入により,1980年以降の30年間で約7割削減されたものの,硫酸エアロゾルの減少は5割程度にとどまっています。この減少鈍化のメカニズムが特定されていないことが,効果的な削減策の策定や正確な気候変動予測の足かせとなってきました。
本研究では,北極グリーンランドアイスコア試料を使った硫酸の三酸素同位体組成(Δ17O値)(17Oの異常濃縮)の分析により過去60年間の大気中の硫酸エアロゾルの生成過程を復元しました。その結果,この期間に大気中の酸性度が減少したため,排出されたSO2から硫酸への酸化反応が促進される「フィードバック機構」が作用していたことがわかりました。酸性度の減少は,SO2削減による酸性物質の減少に加え,施肥などによるアンモニアなどのアルカリ性物質の排出増加によると考えられます。規制対象ではなかったアルカリ性物質の排出が,硫酸エアロゾルの減少鈍化の原因であったという本研究の結果は,今後の効果的な大気汚染の緩和策の策定や,正しい将来の気候変動予測に役立つことが期待されます。
本研究成果は,5月5日(米国東部時間)にアメリカ科学振興会(AAAS)のオンライン誌 「サイエンスアドバンシズ(Science Advances)」に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
SO2排出削減にもかかわらず硫酸エアロゾル減少が鈍化する要因を特定-硫酸の三酸素同位体組成に基づいたフィードバック機構の解明-(PDF)
2021-05-06
隕石に含まれるアミノ酸や糖,核酸塩基などの低分子有機物は,その特異的な炭素同位体組成(13Cの濃縮)から,太陽系外縁部や太陽集積前の極低温環境でできた分子から作られたと考えられてきました。
本学院地球圏科学専攻の力石嘉人教授(低温科学研究所)は,東北大学大学院理学研究科の古川善博准教授,岩佐義成さん(当時博士課程前期2年)らと共に,隕石に含まれる主要な有機物である不溶性有機物とアミノ酸や糖などの低分子有機物との間に存在する大きな炭素同位体組成の差が,隕石有機物の生成反応の一つとして提案されてきたホルモース型反応によって再現できることを明らかにしました。
本研究の成果によって,小惑星に含まれるアミノ酸や糖などの低分子有機物は,これまで考えられていたよりもはるかに広範囲に分布した一般的な材料から生成されていたことが示されました。
本研究成果は,2021年4月29日に米国科学振興協会(AAAS)が発行する『Science Advances』で公開されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
模擬実験で隕石アミノ酸の同位体組成を再現-小惑星有機物の主要生成反応のひとつが明らかに-(PDF)
2021-04-16
一般に「森の香り」として知られる生物起源の揮発性有機化合物(BVOC)は,さまざまな環境ストレスに対する植物などの抵抗力に大きな役割を果たしており,大量に放出される場合は周辺の大気環境にも重要な影響を与えると考えられています。しかし,地理的規模での物理的環境や生物的環境が,放出物質の多様化とどのように関係しているのかについては,ほとんど知られていません。
本学院生物圏科学専攻の甲山哲生研究員(当時)と修士課程(当時)の吉岡颯さんは,東京大学大学院農学生命科学研究科の日浦勉教授(前職は本学院教授)らと共に,遺伝的に異なる全国12集団の天然スギから放出されるBVOCを同一環境下で定量し,テルペン類の組成と量が集団によって大きく異なることを明らかにしました。さらに同グループは,BVOC放出は集団が分布する地域の気候だけでなく,病原菌組成とも密接な関係にあることを見出しました。
優占樹種の機能的な特徴は生態系に波及的に影響を及ぼすため,今後は全国に大規模に植栽されているスギのさまざまな地域系統品種の機能に注目するとともに,BVOCを介した樹木と病原菌の相互作用も考慮した育種や管理が,気候変動対策としても求められるでしょう。
なお,本研究成果はScientific Reports誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
スギの“香り”が語ること〜生物起源揮発性有機化合物放出の地理変異を解明〜(PDF)
2021-04-12
本学院環境起学専攻の根岸淳二郎准教授は,奈良女子大学の片野泉准教授,熊本大学の皆川朋子准教授,兵庫県立大学の土居秀幸准教授,徳島大学の河口洋一准教授,(国研)土木研究所・名古屋工業大学萱場祐一教授から成る研究チームと共に,ダム湖内の堆砂対策として全国のダム河川で実施されている「ダム下流域への置き土」(以後、「土砂還元」)が,河床環境の改善のみならず,生物群集や生物多様性をも改善することを初めて定量的に検証しました。本研究の成果から,ダム河川における「土砂還元」事業が生物の個性豊かな川づくりを可能にすると期待できます。また本研究は,劣化した河川生態系を改善するには適切な土砂量が重要であることを指摘することで,今後の「土砂還元」事業の手法についても提案しました。
本研究成果は,令和3年(2021年)4月8日18時(日本時間)に,英国科学誌「Scientific Reports」に
オンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
ダム湖の堆砂対策としての「置き土」が劣化した河川環境と生物多様性を同時に回復させることを初めて検証(PDF)
2021-04-12
日本列島人(ヤポネシア人)の起源と形成を文理融合で研究する,文部科学省新学術領域研究「ヤポネシアゲノム」の特集号が,日本人類学会の機関誌であるAnthropological Scienceに刊行され、そこに 6編の論文が掲載されました。
これらの研究は,青山学院大学,国立遺伝学研究所,国立科学博物館,国立国際医療研究センター研究所,佐賀市教育委員会,東京大学,新潟医療福祉大学,北海道大学,山梨大学の研究グループ(所属機関名五十音順)の成果です。本学院からは,生物圏科学専攻の鈴木仁教授が執筆されています。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
日本人類学会の機関誌Anthropological Scienceの「ヤポネシアゲノム特集号」に掲載された6論文のご紹介(PDF)
2021-03-31
本研究院の博士研究員(在籍時)のPizza KA Chow 博士と内田健太博士,小泉逸郎准教授らの研究グループは,都市のどのような環境がリスの新規課題解決能力に影響するのかを明らかにしました。最近の研究から,都市に進出した鳥類や哺乳類が,本来の生息地に住む同種他個体と比べて柔軟に新規課題を解くことがわかってきました。一方で,どのような都市環境がこうした認知能力に影響するのかは不明なままでした。
研究グループはパズルボックスを北海道帯広市の複数の公園に生息するエゾリスに解かせるというユニークな手法を用いて,新規課題解決能力に及ぼす環境要因を検討しました。その結果,ヒトが多い都市公園ほどパズルを解く成功率が低下すること,公園の周りにビルなどの構造物が多いほど成功率が低下すること,エゾリスが多い公園ほど成功率が低下することが明らかとなりました。一方で,成功した個体は,パズルを解いている時に周りにヒトが多いほど,より短い時間でパズルを解きました。これらの結果は,ヒトが多いと一部の個体はパズルを解くのを諦める一方,一部の個体はより素早くパズルを解くことによってヒトとの接触を減らしていると推察できるかもしれません。
本成果は都市に生息する動物が本来と異なる環境下でどのように振る舞っているのかを理解する大きな手がかりとなります。また,一見ヒトとうまく共存しているように見える動物でもヒトを避けて暮らしていることが示唆され,都市環境における野生動物とヒトとの共存を考える上でも重要な知見です。
なお,本研究成果は,2021年3月31日(水)公開のProceedings of the Royal Society B誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
都市のリス,どんな環境でパズルを解ける?~異なるストレス環境下でどう振る舞うか~(PDF)
2021-03-30
本学院地球圏科学専攻修士課程2年の岸紗智子さんと大島慶一郎教授・西岡純准教授(共に低温科学研究所)らの研究グループは,自動昇降する酸素センサー付きプロファイリングフロートにより,オホーツク海の広範囲を13年間にわたって連続観測を行い,海水中に溶けている酸素量の変動から,初めて正味の生物生産量(純群集生産量)を見積もることに成功しました。その見積もりによると,純群集生産量は春,直前に海氷が存在していた海域で圧倒的に大きい値になることが示され,春の植物プランクトンの顕著な大増殖(春季ブルーム)は海氷融解によってもたらされていることを初めて定量的指標をもって明らかにしました。この原因として,密度(塩分)の低い海氷融解水によって作られる強い成層(密度差)の他に,海氷が融解することで放出される物質(鉄分であることが有力)が重要であることも示唆されました。今回見積もられた海氷融解域での純群集生産量の値は,世界で最も顕著な春季ブルームが起こる南大洋氷縁域にも匹敵するもので,オホーツク海の高い生物生産を定量的な指標で示した結果でもあります。
本研究は科学研究費補助金・基盤研究S(課題番号 17H01157; 20H05707)の助成を受けて実施されました。なお,本研究成果は,2021年3月26日(金)公開のGeophysical Research Letters 誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
オホーツク海の高い生物生産は海氷の融解によることを解明~フロート観測による初の融解期の正味生物生産量の推定~(PDF)
2021-03-25
本学院地球圏科学専攻のEvgeny A. Podolskiy助教(北極域研究センター),杉山慎教授(低温科学研究所)らの研究グループは,グリーンランドの氷河と海洋の境界で見られるプルーム中での直接観測に成功し,これまで主に数値シミュレーションから予想されていたプルームの動態を,観測によって初めて明らかにしました。
水温,塩分,深度センサーを氷河前のプルームに直接投入して,海水特性の変化を高頻度でモニタリングした結果,氷河の融解や氷河湖の決壊に伴う淡水の流出,潮汐変動,フィヨルド内外の海水交換などにより,従来考えられていたよりもダイナミックに海水特性が変化することが明らかになりました。プルームはフィヨルドのポンプとして海水をかき混ぜ,氷河末端の水中融解とカービングの促進,栄養豊富な海水の循環など,氷河変動と海洋環境に大きな役割を果たします。本研究により,フィヨルドの海水循環モデルの高度化や氷河・海洋境界現象の理解が進み,グリーンランドにおける氷河変動と海洋生態系の理解への貢献が期待されます。
本研究成果は,2021年3月25日(木)公開のCommunications Earth & Environment誌にオンライン掲載されました。
なお,本研究は,科学研究費助成事業,ArCS北極域研究推進プロジェクト,ArCS II北極域研究加速プロジェクトの助成を受けて実施されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
グリーンランドで氷河ポンプの直接観測に成功~氷河前に湧き上がる融解水の実態を解明~(PDF)
2021-03-16
本学院生物圏科学専攻博士後期課程(在籍時)の福井翔さん,同博士前期課程(在籍時)の澤田史香さん,小泉逸郎准教授と北海道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場の春日井潔研究主幹らの研究グループは,日本では北海道だけに生息する絶滅危惧種であるオショロコマ(サケ科イワナ属魚類)と北米原産の外来カワマスが野外で交雑していることをDNA解析から明らかにしました。また,両者の雑種(雑種第1世代)は妊性があり,雑種第2世代目以降も存在していることも確認されました。さらに,ある交雑個体は同じ河川に生息する別種であるイワナ(アメマス)のミトコンドリアDNAを保有していました。今回の調査ではカワマスとアメマスの交雑個体は確認されませんでしたが,過去には複数の河川で報告されています。
これらの事実から,人為的に移入されたカワマスが北海道の在来イワナ属2種の純粋な遺伝子を撹乱する(遺伝子汚染)可能性が示唆されました。オショロコマとカワマスは外見が似ており,特に雑種2世代目以降では判別が難しく,知らない間に遺伝子汚染が広がることも考えられます。カワマスは美しい魚で味も良く,一部の地域では釣魚としても人気が高いですが,在来生態系に与える影響も考慮して適正に管理する必要があります。本研究成果は希少在来種の保全政策を立てる際に有用であるのはもちろん,水産資源やレクリエーションとしての需要がある外来種の管理を考える上でも重要になります。
なお,本研究成果は,タカラ・ハーモニストファンド助成を受け,2021年2月25日(木)公開のZoological Science誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
オショロコマと外来カワマスの交雑を確認~希少在来魚の保全政策に貢献~(PDF)
2021-03-15
日本をはじめ、アジア各国の典型的な景観の一部として親しまれる水田には、水田や周辺地域の気温上昇を緩和させる効果があることが知られています。一般に、盛んに蒸散している植物は気化冷却)により植物体温が低くなることから、特に晴天の日中に周辺の気温上昇を抑えますが、大気中のCO2濃度が上昇すると、植物体の気孔の開き具合(気孔開度)が小さくなるため、蒸散が減ることで、植物による気温上昇を抑制する効果が低下します。このため「水田の気象緩和効果」は将来的に低下するのではないかと懸念されています。そこで、農研機構と本学院地球圏科学専攻の渡辺力教授(低温科学研究所)らの研究グループは,水稲の気孔応答による温度の変化と上空の大気層との相互作用を考慮した、大気–水田生態系結合モデルを開発し、関東付近の市街地を含む水田が広がる地域を対象にシミュレーションをおこないました。その結果、現在の夏季の典型的な晴天日における水田の日中の最高気温は、対象とした地域の市街地と比べて2℃ほど低くなることが示されました。しかし、大気CO2濃度が倍増した条件では、水稲の蒸散が減って気温上昇抑制効果が減り、水田の気温は0.2~0.7℃(平均で0.44℃)ほど現在よりも上昇することがわかりました。市街地では水田の気温上昇の影響を受けて平均で 0.07℃上昇しますが、市街地のうち水田地帯に隣接するような場所では最大で0.3℃ほど気温が上昇すると推定されました。
これらの結果より、将来、大気中のCO2濃度が上昇すると、「水田の気象緩和効果」が低下し、水田およびその周辺地域の日中の最高気温が上昇することが分かりました。また温暖化による気温上昇と相まって、水田では夏季の高温によるお米の品質低下や不稔などの障害リスクが増加する可能性が懸念されます。
本成果は、国際科学誌 Boundary-Layer Meteorology に掲載されました(オンライン版2021年3月5日)。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
水田は周辺地域の気温の上昇を緩和しているが、その効果は大気CO2の増加により低下する(PDF)
2021-03-01
本学院地球圏科学専攻博士後期課程の近藤研さんと同専攻の杉山慎教授(低温科学研究所)らの研究グループは,現地観測データと数値モデルによって,グリーンランドで氷河から流出する河川が引き起こした洪水のメカニズムを明らかにしました。
北極域では気温上昇に伴って氷河の融解が増加しています。氷河の融解は海水準の上昇や海洋環境の変化だけでなく,洪水災害などによって現地で暮らす人々にも影響を与えます。本研究を実施したグリーンランド極北の集落カナック村でも,2015年と2016年に村を流れる氷河流出河川が増水して,道路決壊や橋の流失などの被害が生じました。
そこで研究グループでは,氷河と河川の現地観測で得たデータに,日本における雪氷研究で培われた数値モデルを適用し,カナック村で洪水が発生した際の気象条件から河川流量を再現しました。その結果,2回の洪水は氷河の激しい融解と数年に一度の豪雨が原因と判明しました。また,2100年までに予測される4℃の気温上昇によって,河川への流出水量が現在の3倍に達することが明らかになりました。
以上の結果は,今後さらなる気温上昇や雨量増加が予測される北極域において,洪水のリスクがより深刻化する可能性を示しています。本研究成果によって,近年の気候変動が北極域の人間社会に及ぼす影響の理解が進み,極域に暮らす人々の安全な将来設計に貢献することが期待されます。
本研究成果は,2021年2月17日(水)公開のJournal of Glaciology誌にオンライン掲載されました。なお,本研究は,ArCS北極域研究推進プロジェクト,ArCS II 北極域研究加速プロジェクトの助成を受けて実施されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
北極域の氷河が引き起こす洪水災害のしくみを解明~極北の集落カナック村に現れた気候変動の爪痕~(PDF)
2021-02-05
本学院生物圏科学専攻修士課程の長谷川貴章さんと仲岡雅裕教授(北方生物圏フィールド科学センター)は,魚類が海水中から取り込むマイクロプラスチックの量について,水中から直接摂取するよりも,餌生物を介して摂取する方がはるかに多いことを明らかにしました。
プラスチックごみによる海洋汚染が世界中で進む中,特にマイクロプラスチックが海洋生物へ与える影響が懸念されています。魚類はマイクロプラスチックを海水中から直接取り込むだけでなく,餌を食べることで間接的に取り込みますが,2つの経路の相対的な重要性はこれまで不明でした。そこで本研究では,肉食性魚類シモフリカジカとその餌生物であるイサザアミ類を用いて,魚類のマイクロプラスチック摂取における餌生物を介した経路の重要性について検証しました。
その結果,シモフリカジカはマイクロプラスチックを含んだイサザアミ類の摂食により,水中から直接摂取するよりも3~11倍の量のマイクロプラスチックを取り込んでいることが判明しました。また,マイクロプラスチックがアミに取り込まれる過程で細粒化されるため,餌生物を介してカジカ体内に取り込まれるマイクロプラスチックは直接取り込むものより粒径が小さくなっていました。
マイクロプラスチックは細粒化されると体内組織に移行して悪影響を与えることが指摘されています。また,プラスチックは有害化学物質を含んでおり,これも食物連鎖を通じて濃縮することにより高次消費者へ影響を与える可能性があります。それらの影響に関する研究の進展が期待されます。
なお本研究成果は,2021年1月9日(土)公開のEnvironmental Pollution誌に掲載されました。詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
魚類は餌生物を通じてマイクロプラスチックを大量に取り込む~マイクロプラスチック汚染の食物連鎖を通じた波及効果を解明~(PDF)
2021-01-20
本学院生物圏科学専攻の早川卓志助教,東京工業大学生命理工学院の二階堂雅人准教授,株式会社 digzymeの鈴木彦有博士,アデレード大学のFrank Grutzner 教授,コペンハーゲン大学のYang Zhou 研究員,Guojie Zhang教授らの国際共同研究グループは,『単孔類』と呼ばれる「卵を産む哺乳類」であるカモノハシとハリモグラの高精度な全ゲノム塩基配列の決定に成功し,単孔類がどのように進化しているかを明らかにしました。
カモノハシはオーストラリア東部の河川や湖沼に,ハリモグラはオーストラリア全土とパプア島の陸地に生息しています。単孔類はカモノハシとハリモグラの2グループしかおらず,どのように哺乳類が卵を産む爬虫類的な祖先から進化したのかを教えてくれる貴重な存在です。
早川助教ら日本グループは,カモノハシとハリモグラの化学感覚(味覚,嗅覚など)の進化に注目しました。その結果,両種は哺乳類全体でも特別な進化をしており,明確な違いがありました。具体的には,①ハリモグラは苦味受容体遺伝子がとても少ないこと,②一方でハリモグラは嗅覚受容体遺伝子を沢山持つこと,③カモノハシはフェロモン受容体遺伝子を沢山持つことがわかりました。
本研究成果はハリモグラが餌となるアリやシロアリが発する匂いを頼りに餌を探していることや,水中生活者のカモノハシがフェロモンを用いて効率よく仲間とのコミュニケーションや繁殖をしている可能性を示しており,哺乳類のゲノムと生態を結びつける重要な知見です。
なお,本研究成果は,2021年1月6日(水)公開のNature誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
カモノハシとハリモグラの全ゲノム解読に成功!~世界でたった 2 グループしかいない「卵を産む哺乳類」のゲノムの進化を解明~(PDF)
2021-01-15
本学院生物圏科学専攻博士後期課程2年の中野有紗氏,星野洋一郎教授(北方生物圏フィールド科学センター),千葉大学環境健康フィールド科学センターの三位正洋名誉教授の研究グループは,植物の胚乳を培養することで,二倍体の植物から三倍体と六倍体を同時に作出する技術を考案しました。
植物の倍数性レベルが上がると花や果実,葉のサイズが大きくなるなどの利点があります。倍数体を作出してその利点を品種改良に利用する方法は,倍数性育種として知られています。これまで,三倍体や六倍体を作出するためには,コルヒチンによる倍加と交配を行う必要があり,多くの時間と手間が必要でした。本研究では,胚乳が三倍性を示すことに着目し,ヒガンバナ科のマユハケオモト(ハエマンサス:Haemanthus albiflos)を材料に,胚乳培養とコルヒチン処理を組み合わせることで,交配を経ずに三倍体と六倍体を同時に作出する手法を考案しました。
未熟な種子を滅菌して,胚乳と胚を分離して摘出し,組織培養を行いました。胚乳はカルス形成を経て,植物成長調節物質を添加しない培地に移すことで植物体が再生されることがわかりました。この再生した植物は,染色体観察とフローサイトメトリーによるDNA量の測定によって三倍体であることを確認しました。次に,胚乳由来カルスにコルヒチンを処理することで六倍体を誘導しました。興味深いことに,胚乳由来カルスは胚形成能をもち,不定胚経由で植物体になっていました。
植物の胚乳は,種子の中の大部分を占め,胚に養分を供給する役割を担っています。イネやトウモロコシでは,可食部分が胚乳です。多くの植物では,重複受精により二倍体植物の胚乳は三倍性となります。しかし,胚乳は胚に養分を供給する役割を終えると退化してしまい,植物にはなりません。
近年,胚乳を組織培養することによって,二倍体の植物の胚乳から三倍体ができることがわかってきましたが,本研究では,マユハケオモトの胚乳が高い植物体再生能を保持することを明らかにするとともに,コルヒチン処理と組み合わせることで三倍体と六倍体を同時に作出する培養系を確立し,胚乳培養の応用可能性を示しています。
なお,本研究成果は,2020年11月27日(金)公開のPlant Cell, Tissue and Organ Culture誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
植物の胚乳から三倍体と六倍体を同時に作る技術を開発~倍数性育種の新たな手法を考案~(PDF)
2021-01-15
梅雨は東アジアの初夏に特徴的な現象で,時に令和2年7月豪雨や西日本豪雨(平成30年7月豪雨)のように甚大な災害を引き起こします。梅雨前線は低温のオホーツク海高気圧と暖かい太平洋高気圧の間にできる前線と説明されることが多いですが,オホーツク海の役割を明確に示した研究はありませんでした。地球環境科学研究院の中村哲博士研究員,山崎孝治名誉教授らは三重大学の立花義裕教授らと共に,低温のオホーツク海が太平洋高気圧を強め,ひいては梅雨の降水量を増やすことを数値シミュレーションにより明らかにしました。さらに,オホーツク海高気圧が無くとも梅雨現象は起こることを示し,梅雨にとってオホーツク海は副次的な役割であると示しました。
なお,本研究成果は,2020年12月15日公開のJournal of Climate誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
低温のオホーツク海は,梅雨と夏の太平洋高気圧を強めている~西日本豪雨にも影響か?~(PDF)
2020-12-28
本学院生物圏科学専攻博士前期課程(在学時)の藤田凌平氏,同専攻の星野洋一郎教授(北方生物圏フィールド科学センター),本学大学院医学研究院の早坂孝宏特任助教(現:高等教育推進機構・学術研究員)と神繁樹博士研究員,大学院保健科学研究院の惠淑萍教授による共同研究グループは,ハスカップとミヤマウグイスカグラの種間雑種を育成し,イメージング質量分析法により果実中のアントシアニンの分布パターンを明らかにしました。
ハスカップは,北海道に自生する木本性の植物で,その果実はベリー類として利用されています。星野教授らは,これまでハスカップの遺伝資源の調査と形質改良の研究を進めてきました。本研究では,ハスカップのバリエーションを広げるために,ハスカップの近縁種である赤い果実をつけ食味がよいミヤマウグイスカグラとの種間交雑を行い,種間雑種を育成しました。
種間雑種によって出来た果実は,両親の中間型を示しました。主要な果実成分であるアントシアニンの果実内の分布の様相を両親と比較しながら詳細に解析するために,イメージング質量分析法を適用しました。いずれの果実においても,アントシアニンは果実の皮に局在していることがわかりました。また,興味深いことに,形態的には中間型を示した種間雑種の果実において,いくつかのアントシアニン類は両親よりもその濃度が高いことがわかりました。形態的には両親の中間型を示す種間雑種において,両親よりも高い濃度の成分を含むことは興味深い事象として捉えられます。イメージング質量分析法は,果実のどこに何の成分が分布しているか(定性)と,その成分がどのくらいあるか(定量)を同時に解析できることから,農産物の評価に有効な手法であるといえます。
本成果は,農学,医学,保健科学等の専門分野と分析技術を生かした北海道大学内の共同研究によるものであり,また,今後ハスカップの種間交雑を利用した新たなベリー類の開発が期待されます。なお,本研究成果は2020年10月30日(金)発刊のPlant Science誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
ハスカップの種間雑種を育成し,果実のアトンシアニン類のイメージングに成功~北海道大学の農学・医学・保健科学の専門知識・分析技術を生かした共同研究成果~(PDF)
2020-11-30
本学院環境起学専攻の先崎理之助教と本学大学院農学院博士後期課程の北沢宗大氏は,信州大学大学院総合理工学研究科の松宮裕秋氏,同農学部の原 星一氏(ともに卒業済),東京大学大学院農学生命科学研究科博士後期課程の水村春香氏と共同で,絶滅危惧鳥類・アカモズの日本国内における繁殖個体数と,過去100年間の繁殖分布域の縮小程度を明らかにしました。
アカモズ亜種アカモズ(Lanius cristatus superciliosus)はかつて,北海道大学構内や長野市善光寺,東京都23区内をはじめとして,北海道から本州にかけての多くの地域に普通に生息していました。しかし,1990年代以降に劇的な個体数・分布域の減少が報告され始め,現在は環境省のレッドリストで絶滅危惧IB類に選定されています。こうした状況にもかかわらず,現在は国内の「どこに」「どのくらい」のアカモズが生息しているのか,これまで「どの程度」減少してきたのかは定量的に調べられてきませんでした。
そこで本研究では,日本全国を対象として,2010~2019年にアカモズの新規繁殖地の捜索と,既存の繁殖地における個体数調査を実施しました。その結果,本亜種の国内の繁殖個体数はわずか332個体程度であることが判明しました。更に,調査で明らかになった現在の分布域を,過去の文献やデータベースから推定された過去の分布域と比較したところ,過去100年間で本亜種の分布域が90.9%縮小したことが明らかになりました。これらの数値は,国際自然保護連合(IUCN)が定義するレッドリストカテゴリーのうち,絶滅の危機に瀕している種(EN)の基準を満たし,深刻な絶滅の危機に瀕している種(CR)の基準にも迫っています。そのため,本亜種は絶滅の危険性が非常に高く,一刻も早い保全活動の実施が望まれます。
本研究成果は,2020年11月17日(木)公開のBird Conservation International誌でオンライン出版されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
絶滅危惧鳥類アカモズの危機的状況を明らかに~日本国内の繁殖個体数と繁殖分布域の縮小の程度を初めて算出~(PDF)
2020-11-30
本学院の川西亮太特任助教と本学総合博物館の大橋慎平技術補佐員(当時)は,17年前の2003年に東シナ海で採集された同館分館水産科学館所蔵の深海サメ(トガリツノザメ)の口の中に,大型のウオノエ科甲殻類(全長約6cm)が寄生したまま保存されているのを発見しました。
3Dスキャンなどによる詳細な形態観察の結果,これまでブラジル南部の大西洋から一度だけ報告されていたElthusa splendidaであると結論付け,今回の標本を基に標準和名「オオウオノエ」を提唱しました。世界に300種以上が生息するウオノエ科ですが,魚の口の中という極めて限られた空間に寄生する種としては世界最大級です。ブラジル南部は東シナ海と地球の裏側の関係にあり,このウオノエが大西洋から太平洋にかけての深海に広く生息している可能性を示しています。魚類に寄生して暮らすウオノエ科甲殻類は深海起源である可能性が指摘されていますが,深海域は調査を行いにくいため,どのようなウオノエの仲間がどの地域に生息しているのかもよくわかっていません。今後も,深海魚をはじめとした様々な博物館標本を調査することで,謎に包まれたウオノエ科の分布や生態の解明が進むと期待されます。
なお本研究成果は,2020年11月17日(火)公開のSpecies Diversity誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
博物館所蔵の深海サメから世界最大級のウオノエ科甲殻類を発見~世界で 2 例目,太平洋初~(PDF)
2020-11-17
本学院環境起学専攻の先崎理之助教とカリフォルニアポリテクニック州立大学のClinton Francis准教授らの国際研究グループは,アメリカ全土における 142 種の鳥類の繁殖活動に人為騒音と人工光が大きく影響していることを明らかにしました。
近年,多くの研究が鳥類を含む動物の行動への騒音と人工光の影響を明らかにしてきました。しかし,騒音と人工光が動物の繁殖活動にまで影響するのか,もし影響するならその影響は広域的なのか,他の環境要因と比較してどの程度の影響なのか,どんな特徴を持つ動物が影響を受けやすいのかといったことはわかっていませんでした。
そこで,2000-2014年にアメリカ全土で市民科学者によって収集された 142 種・58506 件の鳥類の繁殖活動データと高解像度の人工光・騒音の空間分布図を用いて,騒音と人工光が鳥類の繁殖活動に与える影響を定量化しました。その結果,静かな環境と比較して大きな騒音に晒された環境では,森林性鳥類の一腹卵数(巣内に産み落とされた卵の数)と繁殖成功率(雛が巣立つ確率)がそれぞれ約12%及び約19%低下しており,抱卵放棄率も約15%増加していました。さらに,暗い環境と比べて強い人工光に晒された環境では,開放地性鳥類及び森林性鳥類の双方が3~4週間早く卵を産んでおり,森林性鳥類では一腹卵数が約16%増加していました。これらの結果から,生物群集の繁殖活動への騒音と人工光の広域的な影響が初めて明らかになりました。本研究は,生物多様性に対する騒音と人工光の影響緩和策の必要性を示す重要な成果です。
なお,本研究成果は,2020年11月11日(水)公開のNature誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
鳥類の繁殖活動への騒音と人工光の広域影響を解明~生物多様性保全戦略における騒音・人工光の影響緩和策の必要性を示唆~(PDF)
2020-11-13
本学院生物圏科学専攻の大原雅教授並びに若菜勇客員教授(釧路国際ウェットランドセンター)らの研究グループは,阿寒湖におけるマリモ(Aegagropila linnaei)の繁殖実態を初めて明らかにしました。
美しい球状の集合体を形成することで知られるマリモは,環境省RDBで絶滅危惧I類に指定されるなど,世界的に個体数の減少が進んでおり,保全の基礎となる成長や繁殖に関する研究の進捗が求められています。マリモが遊走子(胞子)を形成することは古くから知られていましたが,観察例が極めて少なく,マリモ集団は主に栄養成長によって維持されていると考えられてきました。
本研究では,国の特別天然記念物に指定されている阿寒湖のマリモを対象に,2017年と2018年の春から秋にかけて,湖内の生育状態の異なる5カ所の集団について遊走子の形成実態を調査しました。その結果,4本鞭毛を有する遊走子の形成が,藻体が集まって球状になる集合型のマリモ集団1カ所と藻体が岩石等に付着する着生型の集団の2カ所で確認されました。遊走子の形成時期は,両年とも8月中旬から9月上旬にかけてで,再現性があるものの,遊走子を形成した藻体の割合は最大で1.3%と極めて低いことが明らかになりました。これまで,マリモの遊走子形成は稀にしか起こらない偶発的な現象と考えられてきましたが,今回の結果は低い割合ではあっても一定の時期に繁殖していることを示します。また,遊走子が発芽・成長することも確認されており,遊走子が新しい個体の供給源になる一方で,低い形成率が長期に及ぶ栄養成長の継続を通じてマリモの特徴である集合形態の維持・発達にも寄与しているものと見られます。
なお本研究成果は,2020年9月17日(木)公開のAquatic Botany誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
特別天然記念物「阿寒湖のマリモ」の繁殖生態を解明~絶滅が危惧されるマリモの保全に大きく前進~(PDF)
2020-10-28
本学院環境起学専攻の野呂真一郎教授(地球環境科学研究院)と環境物質科学専攻の中村貴義教授(電子科学研究所),本学創成研究機構化学反応創成研究拠点(WPI-ICReDD)の土方優特任准教授,株式会社リガクの佐藤寛泰研究員らの研究グループは,イオン液体中の二酸化炭素の様子を柔らかい結晶を使って可視化することに成功しました。
大気中の二酸化炭素濃度上昇は地球温暖化の原因の一つとして知られており,二酸化炭素を大気中に放出する前に高効率に分離回収する試みが世界中で行われています。回収法の一つであるイオン液体による吸収法はこれまで精力的に研究されてきましたが,規則正しい構造をもたない液体であるがゆえに,イオン液体中に吸収された二酸化炭素の構造を見る・知ることはこれまで困難でした。本研究では,液体の柔らかさと結晶の規則性を兼ね備えた柔らかい結晶中にイオン液体成分を組み込むことで,イオン液体中に吸収された二酸化炭素の状態を可視化することに成功しました。本研究成果は,二酸化炭素分離の高効率化へ向けた材料設計に重要な指針を与えることが期待されます。
なお,本研究成果は,2020年10月27日(火)公開のCommunications Chemistry誌に掲載されました。また,本研究は,文部科学省科学研究費補助金「挑戦的研究(萌芽)」(18K19864),北海道大学「物質科学フロンティアを開拓するAmbitiousリーダー育成プログラム」による支援を受けて行われました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
柔らかい結晶を使って液体中の二酸化炭素の様子を可視化~二酸化炭素分離の高効率化に期待~(PDF)
2020-10-23
本学院地球圏科学専攻の宮﨑雄三助教,西岡純准教授(低温科学研究所),鈴木光次教授,山下洋平准教授(地球環境科学研究院)らの研究グループは,亜寒帯西部北太平洋での船舶による大気と海水の同時観測から,海洋植物プランクトンの細胞老化が進むほど,海しぶきによって大気へ移行する有機物の量が増えることを明らかにし,大気微粒子(エアロゾル)がもつ雲粒の生成能力を抑制する可能性を初めて示しました。
大気エアロゾルは太陽光を散乱・吸収するほか,雲の量や降水過程に影響を与えるなど,気候変動に重要な役割を果たします。エアロゾルに最大80~90%含まれる有機物は雲生成の促進・抑制を決定づけると考えられています。地球の表面積の約7割を占める海洋の表面では,微生物の活動に伴う有機物が海しぶきにより大気へ放出されますが,海洋大気中の有機物量を支配する要因は明らかではありません。研究グループは海洋植物プランクトンの細胞「老化」に着目した指標を新たに用い,細胞老化が進むほど,海水中及び海しぶきとして大気へ放出される有機物の量が増えることを明らかにしました。さらにこの細胞老化に伴う大気エアロゾルの有機物量の増加は,雲の生成を「抑制」する可能性があることを見出しました。本成果は,温暖化等による海洋表層の植物プランクトンの活動度の変化が,大気への有機物の放出を通して雲の生成に影響することで起こる,将来的な気候影響を評価・予測する上で重要な知見となることが期待されます。
なお,本研究成果は,2020年10月12日(月)公開のScientific Reports誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
海洋微生物の「老い」が雲の生成を抑える~雲の生成を制御する大気中の有機物量の指標として,海洋微生物の老化度を新たに提唱~(PDF)
2020-10-05
本学院地球圏科学専攻の杉山慎教授,西岡純准教授(低温科学研究所)および深町康教授(北極域研究センター)は,本学北方生物圏フィールド科学センターの野村大樹准教授,東京大学大気海洋研究所の漢那直也研究員(日本学術振興会特別研究員・元北海道大学北極域研究センター)と共同で,グリーンランドのカービング氷河から流出する,鉄分に富んだ融け水が,窒素,リンなどの栄養塩に富む海水と混ざって海面へ湧き上がり,夏の間のフィヨルドの生物生産に大きく貢献することを明らかにしました。
氷の融け水は,水深200mにある氷河の底からフィヨルドに流出し,その場の海水を巻き込んで湧昇します。ポンプを使ったように海面へ汲み上げられた融け水と海水は,周囲の海水に比べ鉄分と栄養塩を豊富に含んでおり,フィヨルドの広域に広がり植物プランクトンの増殖を促します。
カービング氷河が流入するグリーンランドのフィヨルドには,氷河の恵みを受けた豊かな生態系が広がっています。今後,北極域の温暖化が進行してカービング氷河が消失すれば,氷河の融け水による汲み上げポンプの機能が失われて生態系に大きな影響が予想されます。本研究は,グリーンランドで加速している氷河の融解が,フィヨルドの生態系に与える影響の理解への貢献が期待されます。
本研究成果は,2020年9月28日(月)公開のGlobal Biogeochemical Cycles 誌にオンライン掲載されました。なお,本研究は,ArCS北極域研究推進プロジェクト,ArCS II 北極域研究加速プロジェクト,日本科学協会の助成を受けて実施されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
氷河ポンプがフィヨルドの豊かな海洋生態系を支える~海の栄養分が補給・撹拌・移送されるしくみを解明~(PDF)
2020-09-20
本学院地球圏科学専攻の西岡純准教授(低温科学研究所),東京大学および海洋研究開発機構の合同研究チームは,シベリアとアラスカの間に位置する“アナディル海峡”で海洋調査を行い,北極海に流れこむ冷たい『湧き水』の存在を明らかにした。この観測は,ロシア極東海洋気象学研究所の「マルタノフスキー号」と海洋研究開発機構の海洋地球研究船「みらい」を用いて2017年と2018年の夏に行われた。それ以前の観測では,ロシア排他的経済水域(EEZ)内の観測が制限されているためにアメリカEEZ内であるアラスカ沿岸の調査結果が中心に報告されてきた。これによると,夏に北極海に流入する海水は極めて高温で,その温暖な海水が北極海の海氷分布を主体的に決定すると言われてきた。しかしながら,アナディル海峡の西側(ベーリング海北西部シベリア沿岸)海域を「マルタノフスキー号」で詳しく調査し「みらい」の広域調査(アラスカ沿岸)とあわせることで,冷たい水が下層から湧き出すポイントが存在し,その水が海峡を北上することで北極海の低水温と海氷の維持につながっていることが明らかになった。この発見によって今後,以前より高い精度での北極海の海氷予測の実現が期待される。また今後はアナディル海峡の冷水の起源を特定し,詳しい調査を行うことで北極海の海氷とベーリング海北西海域の気候変動との因果関係を明らかにしていく。
本研究成果は,Journal of Geophysical Research–Oceans誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
北極海の冷水の起源はシベリアにあった!シベリア沿岸に冷水湧昇帯を発見し,その物理メカニズムを解明(PDF)
2020-09-19
本学院地球圏科学専攻の青木茂准教授,平野大輔助教(低温科学研究所)ならびに博士後期課程の山崎開平さんは,海洋研究開発機構や東京海洋大学,水産研究・教育機構の研究者らとともに,オーストラリア南方の南極海の海底付近において,これまで加速度的に低くなってきているとされてきた塩分が,2010年代に反転して急激に高くなりつつあることを見出しました。これまで減ってきていた重い水の量も増えています。こうした海の変化の実態は,水産庁の開洋丸による広域海洋調査や東京海洋大学の海鷹丸による観測航海といった近年の日本による観測を,世界の過去の観測も含めて比較することで判明しました。この変化は,南極深海の海洋循環が強まりつつある可能性も提示しています。変化の原因は,この海域の上流側に位置する南極の棚氷の融解が,ここ何十年か加速してきていたものの,2010年代の前半に弱まったことにある可能性があり,南極氷床と深海との連動性を示すものです。今後の動向を見極めるためには,南極海モニタリング観測網の整備により,変化の傾向を引き続き注視していく必要があります。
本研究成果は,2020年9月15日(火)公開のScientific Reports誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
南極の海の底,もう甘くするのは止めました!?~数十年続いた淡水化傾向が逆転。南極海観測網の継続に期待~(PDF)
2020-08-26
本学院環境起学専攻の藤井賢彦准教授(地球環境科学研究院)と長野県環境保全研究所,九州大学,国立環境研究所,福井工業大学,総合地球環境学研究所及び東北大学(研究当時)の研究グループは,気候危機などの脅威にさらされている沖縄のサンゴ礁の保全に対する支払意志額を全国規模で推計すると共に,提供する情報の量や種類の効果を世界で初めて検証しました。本研究は,文部科学省気候変動リスク情報創生プログラム領域テーマ「課題対応型の精密な影響評価」JPMXD0712103606(研究代表機関:京都大学),環境再生保全機構の環境研究総合推進費 JPMEERF16S11520(研究代表機関:総合地球環境学研究所)及び JPMEERF20192007(研究代表機関:長野県環境保全研究所)の支援を受けて行われました。
なお,本研究成果は,Ecosystem Services誌に掲載されています。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
環境保全への協力意識に情報提供が与える影響を評価―寄付してもよいと思う金額は,文章と図表で情報提供すると12~19%増加,動画で情報提供すると逆に5~7%減少―(PDF)
2020-08-25
本学院地球圏科学専攻の平野大輔助教(低温科学研究所)と国立極地研究所の田村岳史准教授,海洋研究開発機構の草原和弥研究員らの研究グループは,現場観測と数値モデルの手法を融合し,暖かい海水の流入によって生じる白瀬氷河の顕著な融解プロセスを解明しました。近年,西南極では氷床の融解が加速していることが観測され,地球の海水準上昇への影響が危惧されています。一方,東南極ではその実態は未だよく分かっていません。南極・昭和基地のあるリュツォ・ホルム湾の奥には,南極で最大級の流動速度を持つ白瀬氷河が存在しますが,氷河融解の鍵となる海洋の観測は,厚い海氷に阻まれてほとんど行われていませんでした。しかし,第58次南極地域観測隊(2016-17年)では,過去約60年にわたる日本の南極観測で初めて,湾口から白瀬氷河の前面海域にいたるエリアでの大規模な海洋観測に成功しました。本研究では,この海洋観測データの解析を軸に,数値モデルや測地・雪氷学分野との融合研究を行い「白瀬氷河の下(底面)に,沖合起源の暖かい海水が流入することで顕著な融解が生じていること,また,その融解強度は卓越風の季節変動によってコントロールされる」という一連のプロセスを提唱しました。これは,西南極と比べて圧倒的に知見が乏しい東南極における氷床質量変動の理解向上に貢献すると期待されます。
本研究は,平野助教が中心となり,南極地域観測の第Ⅸ期重点研究観測プロジェクト「氷床・海氷縁辺域の総合観測から迫る大気−氷床−海洋の相互作用」(2016〜2021年度)のもとで,国立極地研究所,海洋研究開発機構,英国南極観測局との共同研究として実施されました。なお,本研究成果は,2020年8月24日(月)公開の Nature Communications誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
暖かい海水が白瀬氷河を底面から融かすプロセスを解明~海洋観測と数値モデル,測地・雪氷学分野との融合研究~(PDF)
2020-08-21
本学院生物圏科学専攻の小林真准教授(北方生物圏フィールド科学センター)と工藤岳准教授(地球環境科学研究院)の研究グループは,大雪山などに広く生育する高山植物の一種であるミヤマキンバイが,雪解けが遅く生育期間が短い場所で地下部を発達させること,特に粗根と呼ばれる太い根の割合を増すことで多雪環境に適応していることを明らかにしました。約2ヶ月の短い生育期間中に素早く成長して開花と結実を終えるため,前年までに獲得した炭水化物を太い根に大量に貯蔵していると考えられます。
本研究の成果は, 雪田と風衝地で構成される大雪山の高山帯の美しい花畑が,将来どのように変化していくのかを予想する上で重要な知見となることが期待されます。
なお,本研究成果は,2020年8月10日(月)公開のArctic, Antarctic and Alpine Research誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
大雪山の雪渓の下に太い根を持つ植物が生えていることを発見~多雪環境における短い生育期間を生き抜くための適応~(PDF)
2020-06-01
本学院地球圏科学専攻博士後期課程の塚田大河さんと堀之内武教授(地球環境科学研究院)は,「ひまわり8号」をはじめとする新世代の静止気象衛星で実現した高頻度の観測を利用して,台風の中の雲の動きから風を観測する新しい手法を開発しました。これを,超大型で,日本の研究グループによる航空機観測が実施された2017年の台風21号の観測データに適用し,目の中の雲の動きから回転の速さの分布を導くことに成功しました。目の中の雲は,大気境界層と呼ばれる,地表面から高度2km程度までの領域の上端付近に主に存在します。台風に伴う回転運動は,境界層の上端付近で最も強くなるので,ここでの風速の水平分布が得られることは,台風の強度8や構造の把握に役立ちます。また,この高度の風速は地表付近での風速との対応も良いため,被害予想にも役立つことが期待されます。
本研究によって,目の中にメソ渦と呼ばれる小さな渦が繰り返し発生し,回転の速さが数時間で増加したことが明らかになりました。これは,メソ渦による混合によって台風の構造が変化したことによると考えられます。このような過程が,観測から確認されたのは世界で初めてです。
研究グループは,気象庁気象研究所,横浜国立大学などと共同で,新世代静止気象衛星の観測を台風の診断と研究に活用する世界的にもユニークなプロジェクトを実施しており,台風の構造を診断しその変動要因を明らかにすることに加えて,社会に発信される台風情報の改善につなげて,防・減災に貢献することを目指しています。その実現には,検証手段となる航空機観測を充実させることが重要であるため,最近日本学術会議が発表した,航空機観測に関する大型研究マスタープランの実現が待たれます。
なお,本研究成果は,2020年5月28日(木)公開のGeophysical Research Letter誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
気象衛星による“台風の目”の中の風の観測に初めて成功~台風の強度推定の向上への貢献に期待~(PDF)
2020-05-28
本学院地球圏科学専攻の西岡純准教授(低温科学研究所)と山下洋平准教授(地球環境科学研究院)は,東京大学大気海洋研究所および長崎大学の研究者らとともに,これまで明確には理解されていなかった,グローバルスケールの海洋循環(海洋コンベアベルト)の終着点に位置する北太平洋の栄養物質循環像を明らかにしました。
これまで北太平洋では,どのようなメカニズムを経て海洋表層に窒素やリンなどの栄養塩が供給され,生物活動が維持されているのかは良くわかっていませんでした。本研究では,これまでに予想されていた,深層に蓄積されている栄養塩が直接表層の高緯度海域を肥沃にしているという考えを覆し,ベーリング海で形成される中層水の栄養塩プールの形成と海峡部で起こる混合が,深層と表層の栄養塩を繋ぐ重要な役割を果たしていることを明らかにしました。この中層水由来の栄養塩とオホーツク海から流出する鉄分が混合することで,西部北太平洋の生物生産が高い状態で維持されていることが解明されました。本研究で見えてきた北太平洋の栄養物質循環像は,地球規模の海洋物質循環を解明する上で鍵となるエリアの理解を大きく進めます。今後,海洋における炭素循環,栄養物質循環,生態系の気候変動に起因する変化を理解する上で欠かせない知見となります。
本研究は,新学術領域研究「海洋混合学の創設」及び「新海洋像」,その他の科学研究費補助金,低温科学研究所共同利用開拓型研究の助成を受けて実施されました。
なお,本研究成果は2020年5月27日(水)公開の米国科学アカデミー紀要Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of Americaにオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
海洋コンベアベルトの終着点における栄養物質循環の解明~縁辺海が海を混ぜ,栄養分を湧き上がらせる~(PDF)
2020-04-24
本学院地球圏科学専攻の堀之内武准教授(地球環境科学研究院)とJAXA宇宙科学研究所などの研究者からなる国際研究グループは,金星探査機「あかつき」によって取得された観測データに基づき,長年謎だった金星大気の高速回転(スーパーローテーション)がどのように維持されているのかを明らかにしました。
金星の分厚い大気は,自転の 60 倍ほどにも達する速さで回転していることが知られています。これをスーパーローテーションと呼んでいます。スーパーローテーションは,何らかの加速機構がなければ維持できないことが知られていますが,それがどのような機構であるかは,わかっていませんでした。今回,「あかつき」で得られた画像と温度データの詳細な分析より,この加速機構を担うのが,「熱潮汐波」であることが明らかになりました。地球の潮の満ち干に関わる海の潮汐波は,月の引力によって生み出されますが,大気中には昼間熱せられて夜冷却されることによる潮汐波が地球にも金星にも存在し,熱潮汐波と呼ばれています。金星では,この熱潮汐波が,低緯度で大気の加速を担うことが重要であることが明らかになったのです。これまで,大気中に存在する潮汐波以外の波や乱れ(乱流)も加速を担う候補として考えられてきましたが,むしろその逆に働いていることも明らかになりました。なお,それらは赤道を離れた中緯度において重要な役割を果たしていると考えられます。
本研究成果は,2020年4月23日(日本時間4月24日)公開の科学雑誌Science(サイエンス)電子版に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
「あかつき」により金星大気のスーパーローテーションの維持のメカニズムを解明(PDF)
2020-04-20
本学院生物圏科学専攻の大舘智志助教(低温科学研究所)と国後島のクリリスキー自然保護区事務所のアレクサンドル・キスレイコ所長らの研究グループは,1986年から2019年までの33年間を対象に国後島と歯舞群島を中心とする北方領土におけるエゾシカの生息情報を解析しました。
従来,エゾシカの分布地は北海道本島とされ,国後島や歯舞群島からは江戸時代から終戦まで明確なエゾシカの生息記録がありませんでした。終戦後1970年〜80年代前半までは,ごく稀に単独の個体が一時的に発見されることはありましたが,恒常的な生息は確認されていませんでした。
国後島にあるクリリスキー自然保護区事務所では1986年半ば以降,北方領土におけるエゾシカの情報を収集・蓄積してきました。それらを取りまとめた結果,エゾシカの遺骸は3年に1回ほどの頻度で,国後島と歯舞群島の水晶島(1 回のみ)で発見されていることがわかりました。そして2017年からは毎年,国後島において,直接観察や糞,足跡が確認されています。2019年には2頭が同時に目撃されました。このことから国後島において少なくとも数頭のエゾシカが定着していると思われますが,今のところ島内での繁殖は確認されていません。また,エゾシカは冬期に流氷の上を歩くか,夏期に海峡を泳いで渡ったと考えられていますが,詳しい分散経路はわかっていません。
北方領土には貴重な植物が生育しています。一方,対岸の知床半島ではエゾシカが急増したことにより植生が破壊されています。仮にエゾシカが国後島で今後も定着して増殖した場合,知床半島のように植生の破壊が懸念されます。世界的にも貴重な自然環境を有している北方領土の自然を保全するためには,政治的思惑を超えたエゾシカのモニタリングと実態調査が望まれます。
なお,本研究成果は,2020年4月17日(金)公開のMammal Studyにオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
北方領土におけるエゾシカの生息状況が明らかに~ここ数年で国後島に定着か?~(PDF)
2020-04-20
多くの動物において,配偶者選択や同性間の縄張りあらそいなど,種の繁殖のために必須な行動には,体臭を介した嗅覚コミュニケーションが重要な役割を果たしています。今回,本学院生物圏科学専攻の早川卓志助教は,東京大学,京都大学霊長類研究所,進化生物学研究所,日本モンキーセンターなどの研究者らとともに,特徴的な嗅覚コミュニケーションを行うワオキツネザルに注目し,ヒトを含む霊長類で初めて,異性を惹き付けるフェロモン様効果のある匂い物質の同定に成功しました。
ワオキツネザルのオスは,手首の内側にある臭腺(前腕腺)を自身の長い尻尾にこすりつけてその尻尾を大きくゆらし,メスへのアピールや他オス個体への威嚇を行います。行動観察により,メス個体が,繁殖期のオスの前腕腺分泌液の匂いをより長く,より注意深く嗅ぐ一方で,非繁殖期の分泌液にはあまり興味を示さないことを明らかにしました。次に,分泌液の成分分析を行い,繁殖期の分泌液中には,体内の男性ホルモン(テストステロン)の増加に伴い,フローラル・フルーティー様の香りを持つ三種類の長鎖アルデヒド群が増加していることを見出しました。さらに,これらの成分のみを染み込ませた綿球に対しては,繁殖期のメスのみが興味を示し,非繁殖期のメスは興味を示さないことが分かりました。すなわち,今回同定されたオスの繁殖期を特徴づける匂い成分が,メスを誘引するフェロモン様の匂いシグナルとして機能していることがわかりました。
本成果は,未だ謎の多い霊長類の嗅覚コミュニケーションの実態を物質レベルで裏付ける最初の知見であると同時に,野生での絶滅が危惧されるワオキツネザルの繁殖管理や保全に役立つと考えられます。
本研究成果は,学術誌「Current Biology」に2020年4⽉16日付でオンライン公開されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
ワオキツネザルのメスを惹き付けるオスの匂い―霊長類のフェロモン様物質の同定に初めて成功―(PDF)
2020-04-17
南極海(南大洋)は,人類がこれまで放出してきた二酸化炭素(CO2)の約1割を吸収してきたと見積もられており,地球規模の炭素循環を理解する上で重要な海域です。本学院地球圏科学専攻の鈴木光次教授,吉川久幸名誉教授(地球環境科学研究院)らは,国立環境研究所,東京海洋大学,国立極地研究所の研究者らとともに,浮遊性微細藻類(植物プランクトン)の優占グループの変化が南極海のインド洋区における夏期の CO2 吸収量に影響を及ぼすことを,船舶観測と衛星画像解析により初めて明らかにしました。具体的には,特定の群集(珪藻類)が優占する年ほど,植物プランクトンの正味の炭素固定量は大きくなり,海洋への CO2 吸収量も増加することが分かりました。本研究で得られた知見は,温暖化等の気候変動によって生じる可能性がある植物プランクトンの群集変化が,海洋の炭素循環を通じて気候変動に及ぼす影響を評価・予測する上でも重要な情報です。
本研究成果は,海洋学分野の学術誌「Deep-Sea Research Part I」に2020年3⽉19日付でオンライン先行公開されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
南極海の二酸化炭素吸収:微細藻類の量だけでなく種類が鍵となる-優占群集の違いが夏期の炭素収支を左右していた-(PDF)
2020-04-10
本学院地球圏科学専攻の西岡純准教授(低温科学研究所)らの研究グループは,オホーツクの流氷に含まれる鉄分の量と存在状態,その起源を明らかにし,流氷から放出される鉄分が生物に使われやすいことを証明しました。流氷は,様々な起源からなる粒子状の鉄分を非常に多く含んでいますが,粒子状の鉄分が海水中に放出された際に,植物プランクトンが鉄分を使えるのかどうかはわかっていませんでした。本研究では,流氷が融けた状態を模擬した培養実験を行い,植物プランクトンが使うことのできる流氷中の鉄分の存在状態を調べました。その結果,植物プランクトンは流氷から放出された粒子状の鉄分を使って増殖することが確認されました。本研究成果は,「オホーツクの流氷は栄養物質を運び,豊かな生態系を支えている」という従来の認識を科学的見地から裏付けるもので,流氷がオホーツク海の生物生産に果たす役割の理解が進むと期待されます。
本研究は,GRENE 北極気候変動研究事業,科学研究費補助金,キヤノン財団,タスマニア大学ツネイチフジイ奨学金,低温科学研究所共同利用の助成を受け,タスマニア大学海洋南極学研究所の研究者らと共同で実施しました。
なお,本研究成果は,2020年3月31日(火)公開のMarine Chemistry誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
オホーツク海の豊かな生態系を育む流氷の役割を解明~生物に必要な鉄分を流氷が運ぶ~(PDF)
2020-03-19
本学院地球圏科学専攻の安成哲平助教(北極域研究センター)は,本学工学研究院,産業技術総合研究所らの研究者とともに,北海道札幌市と利尻島での元素状炭素 (煤) 粒子の地表面への沈着量の20年間の変遷を分析により初めて明らかにし,沈着量の年ごとの変化は非常に大きかったことを発見しました。今回,地方自治体の研究機関による酸性雨の研究で使用され長期間保存されていた薄膜フィルターに注目し,そこに捕集された煤の抽出・分析法を考案しました。煤粒子の地表面への沈着量の20年間の変遷を みると,2000~2001年の黄砂の大量飛来時には,煤粒子の沈着量が大幅に増大しており,煤を含む大気汚染物質が国内の高緯度地域に黄砂と同時に大量に輸送されていた可能性が示唆されました。雪氷面に煤が沈着すると太陽光の反射率を低下させて熱収支を変化させ,気候に影響を与えるが,今回,煤粒子沈着量の年々変動が非常に大きかったことから,短期間の沈着量データのみの利用では気候モデルによる沈着量検証の際に問題が生じる可能性が提示された。
なお,本研究成果は,2020年3月18日(英国夏時間)に論文誌Scientific Reportsに掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
20年間にわたる煤(すす)粒子の地表面沈着量の変遷を測定-積雪汚染による気候影響の評価・予測計算を検証する新たな長期データを提供-(PDF)
2020-03-18
本学院環境起学専攻のホルへ ガルシア モリノス助教(北極域研究センター)らの研究グループは,気候変動によって水産魚種の分布域が変わることで,海域から流出する魚種の代わりに流入する魚種がいない熱帯域諸国において,多くの水産資源が失われる恐れがあることを見出しました。
海水温度が上昇するにつれ,魚類は適温環境を求めて温度が相対的に低い環境へ移動します。研究グループは,2015年から2100年までの温室効果気体排出シナリオを用いて,779の漁業対象魚種の生息分布域の変化を予測するコンピューターモデルを開発しました。このモデルによると,比較的緩やかな温室効果気体排出シナリオの場合,熱帯域諸国では2100年までに現在の魚種数の15%を失う恐れがあり,より過酷な排出シナリオの場合は40%以上も失う恐れがあります。また,北西アフリカの国々は魚種数の減少が最も大きく,東南アジア,カリブ海諸国,中央アメリカ諸国でもかなりの魚種数の減少に直面することが示されました。
科学者達は,現存する地域内・多国間・二国間政策などが,気候変動によって各国の管轄水域(排他的経済水域;EEZ)から流出する魚種の管理に必要な規定を盛り込んでいるかについて疑問を持っています。公表されている127の国際漁業協定を解析した結果,いずれも気候変動,魚類生息地の変化あるいは資源量に関して,直接的な記述をしているものはありませんでした。また,いくつかの協定では短期的な資源変動を管理する仕組みは含まれていましたが,現存する協定の中で魚類資源を失う国による乱獲を防ぐ長期的政策が含まれているものはありませんでした
本研究成果は,慎重な政策決定が必要な場面において新たな知見を与えると期待されます。
なお,本研究成果は,2020年2月24日(月)公開のNature Sustainability誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
気候変動が熱帯域諸国の魚類資源を奪う~今後の気候変動適応策へ新たな知見を与えることに期待~(PDF)
2020-03-17
本学院地球圏科学専攻の山下洋平准教授(地球環境科学研究院)と西岡純准教授(低温科学研究所)は,東京大学大気海洋研究所の研究者らと共に,「どのようにしてオホーツク海由来の鉄分が北太平洋の広範囲に運ばれているのか」,そのメカニズムを捉える事に成功しました。
鉄分は生物にとって必須の栄養素ですが,海水に溶けにくい性質を持ちます。世界の多くの海域では,鉄分の多さが生態系の基盤である植物プランクトンの豊富さを左右しているため,鉄分の海洋循環メカニズムを明らかにすることは海洋生態系を理解する上で重要なテーマです。北太平洋では,鉄分の多くがオホーツク海の大陸棚堆積物から供給され,海洋内を長距離運ばれていることがこれまでの研究から明らかとなっていましたが,どのようにして溶けにくい鉄分が海洋の広範囲に運ばれているか,そのメカニズム自体は不明でした。そこで研究グループは,鉄分を溶かす(鉄分と錯体を形成する)働きをもつ有機物である「腐植物質」に着目し,オホーツク海から亜熱帯海域までの広範な海域における鉄分と腐植物質の南北断面分布を世界で初めて明らかにしました。特筆すべきは,海洋に存在する腐植物質を,海洋内部で細菌により生み出されるもの(自生性)と海洋の外から供給されるもの(外来性)に区別する手法を考案し,外来性である堆積物起源の腐植物質のみの分布を定量化する事に世界で初めて成功した点です。これにより,オホーツク海の堆積物起源の腐植物質は鉄分と錯体を形成することで,北太平洋の中層水循環システムによって,少なくとも 4,000km 運ばれ,亜熱帯海域にまで達している事が判明しました。
本研究成果は,気候変動によって環境が大きく変わりつつある海洋において,必須栄養素である鉄分の輸送を介して,生物生産性や二酸化炭素吸収量がどのように変動していくかを理解する上でも貴重な知見となります。
なお本研究は,新学術領域研究「海洋混合学の創設」及び「新海洋像」,その他の科学研究費補助金,低温科学研究所共同利用の助成を受けて実施され,2020年3月11日(水)公開のScientific Reports誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
北太平洋の生態系を潤す,鉄分の海洋循環メカニズムを解明~有機物にくっついてオホーツク海から亜熱帯へ,4,000km の旅~(PDF)
2020-03-16
本学院地球圏科学専攻の飯塚芳徳准教授(低温科学研究所)は,国立極地研究所,東京大学大気海洋研究所,海洋研究開発機構ならびに英国ケンブリッジ大学等の海外大学の研究者らと共に,南極内陸のドームふじとドームCアイスコアに含まれる微粒子のサイズや形状,化学組成を一粒ずつ電子顕微鏡によって解析することで,最終氷期の最寒期(約2万年前)にドームふじに降下したダスト(陸域を起源とする微粒子)がドームCよりも約3倍も多かったことを初めて明らかにしました。また,同時期にドームCに飛来したダストの方が小さく扁平であることから,より遠くから運ばれてきたこともわかりました。これらの結果は大気大循環モデルによるシミュレーションとも整合的であり,その原因は,氷期のダストの主な起源である南米南部のパタゴニアからの輸送距離の違いであると考えられます。
この成果は「Journal of Geophysical Research -Atmospheres」誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
氷期最寒期のダスト飛来量を複数の南極アイスコアから復元~ダスト起源のパタゴニアからの輸送距離の違いを反映〜(PDF)
2020-02-27
本学院環境起学専攻の野呂真一郎教授(地球環境科学研究院),環境物質科学専攻の中村貴義教授(電子科学研究所)らの国際研究グループは,水分子が共存しても炭化水素ガスを分離できることを明らかにしました。
プロピレンやエチレンなど分子内に二重結合をもつ炭化水素ガス(アルケン)は,我々の身の回りで使われているプラスチックや化学繊維など様々な化成品の原料として重要です。このアルケンガスを精製するためには,一緒に含まれているプロパンやエタンなどの性質のよく似た別の炭化水素ガス(アルカン)から分離する必要があります。現状は多くのエネルギーが必要でコストがかかる蒸留法により精製されており,多孔性材料を用いた分離法が近年省エネ型分離法として注目されてきました。一方で,通常の大気のように水蒸気が存在すると多孔性材料の分離性能が悪くなると言われてきましたが,それを確認した例はこれまでありませんでした。
本研究では,プロピレンを選択的に分離できる多孔性材料に水を含ませた状態で実験を行い,水が存在していてもプロピレン分離性能がほぼ維持されることを世界で初めて実証しました。また,水分子自体が新たなプロピレン認識部位として働いていることを理論計算によって示しました。本研究成果は,コストがかかる水の分離プロセスを必要としない新たな省エネ型炭化水素ガス分離法としての応用展開が期待されます。
なお,本研究成果は,2020年1月27日(月)公開のACS Applied Materials & Interfaces 誌にオンライン掲載されました。また,本研究は,文部科学省科学研究費補助金「基盤研究B」(17H03026),「二国間交流事業(ドイツ(DAAD)との共同研究)」,「人・環境と物質をつなぐイノベーション創出ダイナミック・アライアンス」による支援を受けて行われました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
水が炭化水素ガスを見分けることを発見~ガス分離の省エネルギー化に期待~(PDF)
2020-02-13
本学院生物圏科学専攻の宗原弘幸教授(北方生物圏フィールド科学センター)と博士後期課程(当時)の鈴木将太さんらの研究グループは,半クローン生物が組み換え世代を取り入れることで,ゲノムをリフレッシュし,遺伝的多様性を獲得していることを明らかにしました。
アイナメ属は,ホッケと並び,北海道を代表するアイナメ科の磯魚です。この仲間には6種が知られ,その他にスジアイナメとクジメのゲノムを持つ雑種の生息が最近明らかになりました。アイナメ属の野外雑種はすべて雌で,受精して成体になるまでは父種(クジメ)ゲノムも使いますが,卵形成過程で消失し,母種(スジアイナメ)ゲノムだけがクローン的に子に受け継がれます。アイナメ属雑種は,父種の雄と戻し交配をする限りクローンを保ちますが,母種の雄と交配するとスジアイナメゲノムが2セットになり,通常の減数分裂をする組み換え世代へ移行します。
本研究によって,雑種は両方の親種と同率で交配している(双方向戻し交配)ことが明らかになり,組み換え世代で有害変異の削減と遺伝的多様性を回復したのち,偶発的な交雑で半クローン世代に移行することが実証されました。本研究は,半クローン世代と有性生殖(遺伝子組み換え)世代を持つことで有害変異の削減と遺伝的多様性を回復するという仮説を実証し,クローンゲノムが永続的に存続できる仕組みを発見した世界で初めての研究です。
なお,本研究成果は,2020年1月7日(火)公開のEvolution誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
https://www.hokudai.ac.jp/news/200205_pr2.pdf
クローンゲノムが永続する仕組みを世界で初めて発見~クローン生物最大の欠点を克服~(PDF)
2019-12-02
本学院地球圏科学専攻の中山佳洋助教らの研究グループは,南極沿岸域で最も海面上昇に寄与している二つの棚氷(パインアイランド棚氷とスウェイツ棚氷)に着目して,東アムンゼン海の超高解像度海洋モデルを開発しました。
南極大陸には,地球上の氷の約90%が存在し,南極の氷が全て融解すると海水準は約60m上がるとされています。南極の氷は,その上に雪が降り積もることで形成され,徐々に大陸沿岸部へと流れ,一部の地域では海へと流れ込みます。その中でもアムンゼン海東部では,多量の氷が南極大陸上から海へと流出し,南極氷床による海面上昇の寄与の約70%に相当します。南極氷床から海への氷の流出は,温かい海水が棚氷下部へ流入することによって引き起こされます。そのため,どのように南極沿岸域の海が棚氷融解を引き起こしているかを理解することが,南極氷床による海面上昇を予測するために必要な課題となっています。
研究グループが開発した超高解像度海洋モデルは,南極沿岸/棚氷域に着目した既存の海洋モデルと比較しても 3-4倍以上細かい世界最高の空間解像度を実現し,モデル結果から(1)パインアイランド,スウェイツ棚氷への高温の水塊の流入経路や(2)融解量を決める上での棚氷下部の海洋循環の重要性などが明らかになりました。さらに,棚氷の融解量をモニタリングするために必要な海洋観測も示唆されました。観測データの限られる南極沿岸域において,観測データの再現性の高い海洋モデルを開発し,その結果をもとに,現実の海洋で起きていることを理解するという研究は,棚氷融解量,将来的な南極による海面上昇の見積もりを精緻化する上で必要不可欠です。
本研究成果は,2019年11月22日(金)公開の英国の科学誌であるScientific Reports電子版に掲載されました。なお, 本研究は,NASAジェット推進研究所との共同研究として実施されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
パインアイランド,スウェイツ棚氷への高温水塊の流入経路の解明~南極最大の氷損失域における棚氷海洋相互作用の理解~(PDF)
2019-12-02
本学院地球圏科学専攻の力石嘉人教授(低温科学研究所)は,東北大学,海洋研究開発機構,米国NASAゴダード宇宙飛行センターの研究者らと共に,2種類の炭素質隕石からリボースやアラビノースなどの糖を初めて検出しました。
リボースは核酸(RNA)を構成する主要な糖分子です。隕石からリボースなどの糖を検出したことは,宇宙にも生命を構成する糖が存在することを示す発見です。そのような糖は生命誕生前の地球にも飛来し,地球上の生命の起源につながる材料の一部となった可能性があります。
本研究の成果は令和元年11月19 日午前5時(日本時間),米国科学アカデミーが発行する 「Proceedings of the National Academy of Sciences, USA(米国科学アカデミー紀要)」に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
生命を構成する糖を隕石から初めて検出-宇宙にRNAの材料となる糖の存在を証明-(PDF)
2019-12-02
本研究院の中村哲博士研究員,山崎孝治名誉教授,佐藤友徳准教授(環境起学専攻),新潟大学の浮田甚郎教授の共同研究グループは,温暖化時の北極海の海氷減少を想定した気候変化のシミュレーションを行い,陸域の土壌温度や積雪を介したメモリ効果の寄与を定量的に見積もる手法を開発しました。海氷減少は近年増加傾向にある中緯度の寒波の一因であると指摘されていますが,本研究により,寒波の記憶がユーラシア大陸に蓄積されることで,翌冬,翌々冬の寒波をさらに強めるという,増幅(フィードバック)効果を持つことがわかりました。このメモリ効果は,海氷減少によって生じる寒波の強さを約2 倍に強めます。
本研究では,陸域のメモリ効果がどのような物理的プロセスで生じているのか,詳細に調べました。日本で強い寒波が発生する際には,ユーラシア大陸全域が寒冷で,積雪が多い傾向があります。多量の積雪が春の雪解けの時期を遅くすることで,日射による地面の温度上昇が妨げられ,寒冷なシグナルが土壌温度に記憶されます。夏場の大気状態の影響を受けにくい土壌温度の寒冷なシグナルは秋まで持続し,初冬の積雪時期を早めます。積雪は日射を強く反射して地面付近が温まることを妨げるため,早い冬の到来となり,強い寒波が形成されやすくなります。このような季節サイクルの繰り返しが蓄積されることで,持続的に強い寒波をもたらす気候状態を作り出しています。
急速な温暖化が進む北極と,その影響を受ける中緯度の気候変化の予測には,大きな不確実性があるとされています。本研究の成果で得られた陸域のメモリ効果は,一旦ある方向に向かった気候状態をさらに推しすすめるような正のフィードバック効果があることを示しています。陸域の状態を調べることで,長期的な傾向の予測に役立つことが期待されます。
本研究は,文部科学省北極域研究推進プロジェクト「ArCS: Arctic Challenge for Sustainability Project」,及び科学技術振興機構「ベルモント・フォーラム CRA InterDec」の一環として⾏われ,Nature Communications誌にて,2019年11月8日(金)19時にオンライン公開されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
ユーラシア⼤陸の気候メモリ効果が北極温暖化に伴う冬の寒波を強める〜⻑期気候変動におけるフィードバックメカニズムの⼀端を解明〜(PDF)
2019-10-31
本学院生物圏科学専攻の仲岡雅裕教授(北方生物圏フィールド科学センター)と同専攻博士後期課程の須藤健二さん(当時)らの研究グループは,北日本のコンブ類の分布域が今後地球温暖化の進行に従って大きく減少すること,また分布が限られている複数の種が日本の海域から消失する可能性が高いことを明らかにしました。
なお,本研究成果は,2019年10月28日(月)公開のEcological Research誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
地球温暖化により北日本のコンブが著しく減少する可能性を予測~沿岸生態系の海洋生物多様性や生態系サービスに負の影響~(PDF)
2019-10-03
本学院環境起学専攻の平田貴文特任准教授(北極域研究センター)は,同センターの齊藤誠一研究員(研究推進支援教授)らとともに北海道大学及び東北大学が中心となって研究開発された国際理学観測衛星ライズサット(RISESAT:Rapid International Scientific Experiment Satellite)に搭載した海洋観測カメラ OOC(OceanObservation Camera,北海道大学,東北大学,株式会社パスコ及び国立台湾海洋大学が共同開発)による有色溶存有機物(CDOM:Colored Dissolved Organic Matter)の観測に成功しました。なお,ライズサットは JAXA 革新的衛星技術実証1号機を構成する 7 衛星の一つとして,イプシロンロケット4号機により打ち上げられました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
海洋観測カメラによる有色溶存有機物の観測に成功~超小型人工衛星を利用した北極域観測技術の構築に期待~(PDF)
2019-09-25
本学院地球圏科学専攻の関宰准教授は,高知大学海洋コア総合研究センターの松井浩紀特任助教,池原実教授らと共に,九州付近から沖ノ鳥島を経てミクロネシアのパラオ付近に至る南北 3000 km に渡る海底山脈である九州・パラオ海嶺で 1973 年に採取された Site 296 海洋コアを再解析しました。レガシー試料である Site 296 海洋コアは黒潮流路に近い九州・パラオ海嶺の北端から採取されたことから,黒潮の長期的な変遷を記録していると期待されます。コアレポジトリーの適切な保管・管理により,46 年の時を経たのちも Site 296 海洋コアを全く問題なく解析に資することができました。Site 296 海洋コアに含まれる微小なプランクトン化石の産出状況を再解析するとともに,ストロンチウム同位体比と炭素・酸素安定同位体比を統合することで,掘削当時は発展途上で十分に確立できていなかった Site 296 海洋コアの年代モデル(微化石層序・地球化学層序)を 46 年ぶりに再編することができました。この成果により Site 296 海洋コアが過去2000 万年間の海洋環境を連続的に記録した,北太平洋における極めて貴重な試料であることを明らかにしました。こうした過去 2000 万年間にわたって連続的に堆積した海洋コア試料は北太平洋では極めて稀であり,黒潮の流域では Site 296 海洋コアが唯一の報告例です。特に,現在よりも顕著に温暖だった時代における黒潮の流路や強さを解明していく上で,過去 3000 万年間において最も温暖な時代であったとされる中期中新世(約 1600 万年前〜1160 万年前)の連続的な試料は貴重で,今後も Site 296海洋コアの活用が期待されます。
本成果は学術誌「Newsletters on Stratigraphy」オンライン版に 2019 年 9⽉20⽇に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
九州・パラオ海嶺に過去 2000 万年間の連続的な堆積物があることを発見―1973 年に掘削されたレガシー試料の再解析―(PDF)
2019-09-12
本学院生物圏科学専攻の工藤岳准教授は,市民ボランティアと共同で,北海道大雪山における高山植物の長期開花調査を行い,地球温暖化によって高山植物群落の開花期間が将来どのように変化するのかを予測しました。
高山植物の開花時期は温度や積雪期間の変化に敏感であるため,地球温暖化の影響を強く受けると予測されていますが,その実態と将来予測に必要なモニタリング例はごくわずかでした。そのため本研究では,環境省生物多様性センターが行っている生態系長期モニタリングプロジェクト「モニタリングサイト 1000」の高山帯調査の一環として,市民ボランティアによって集積された高山植物開花調査データを解析しました。詳細な開花状況と気温・積雪データの解析により,気候変動に対して高山植物群落の開花時期がどのような影響を受けるのかを予測しました。その結果,積雪の少ない場所に生える高山植物は気温の影響を強く受け,温度が高いほど開花の進行が早く,1 度の気温上昇により開花期間は約 4 日間短縮されると予測されました。一方で雪解けの遅い場所に生育する植物は,気温よりも雪解け時期の影響を強く受けることが明らかになりました。更に温暖化によって 1 度の気温上昇と 10 日間の雪解けの早期化が起こった場合,高山帯の開花時期は約 5 日間短縮されるという予測が得られました。温暖化に伴う高山植物群落の開花シーズンの短縮は,花を利用する昆虫へも影響が及ぶことが懸念されます。本研究は,市民ボランティアによる生態系モニタリングの有効性を実証したものとして重要な成果です。
本研究成果は2019年8月2日(金)公開のEnvironmental and Experimental Botany 誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
地球温暖化は高山植物群落の開花シーズンを短縮する~市民ボランティアにより明らかにされた温暖化影響予測~(PDF)
2019-09-02
本学院環境起学専攻の先崎理之助教らの研究グループは,日本で繁殖する海鳥10種類の過去36年間の個体数変化を解析し,ウミガラスやエトピリカといった絶滅危惧種だけでなく,ウミネコやオオセグロカモメなどの,分布域が広く個体数が多いと思われていた種類も長期的に減少していることを明らかにしました。
本研究成果は,2019 年 8 月 28 日(水)公開の Bird Conservation International 誌でオンライン出版されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
日本で繁殖する主要海鳥種の個体数変化を初めて解明~ウミガラス・エトピリカ・ ウミネコ・オオセグロカモメの減少を確認~(PDF)
2019-08-06
本学院環境起学専攻の佐藤友徳准教授と中村哲博士研究員(地球環境科学研究院)の研究グループは,中・高緯度で近年しばしば発生する熱波の発生要因を解明するために,気候モデルによって再現された大量の過去気候データを解析し,過去のユーラシア大陸における夏の気温変動を,「地球温暖化に起因する気温変化」と「自然変動に起因する気温変化」に分離することに成功しました。
さらに,「自然変動に起因する気温変化」のうち,偏西風の蛇行に関連した,高温域と低温域が東西方向に交互に連なる波列状の気温分布が発生する要因を調べ,ユーラシア大陸における夏の気温パターンが北極域における晩冬~春の積雪深変動の影響を強く受けることを明らかにしました。波列状の気温分布が夏に卓越する年には,数か月前の晩冬~春の時点でロシア西部の積雪が普段に比べて多く,このような多雪の影響は,春の融雪を経た後には,高い土壌水分量として春から夏まで持続し,この地域の夏の気温を低温化します。地域的な低温化は偏西風の蛇行を促し,その周辺地域では反対に高温になりやすくなると考えられます。
中・高緯度帯では,日々の天気の移り変わりの早さに比べて,海洋や陸面状態(積雪や土壌水分など)は比較的ゆっくりと時間変化するため,その影響は長期間持続し,大気に継続的な影響を与える傾向があります。特に広大なユーラシア大陸では,陸面状態を詳細に調べることで,季節予報の精度向上が期待されます。また,本成果により北極域の陸面状態の変化が中・高緯度の夏の天候に影響を与えていることが明らかとなりました。これは,気候変動の要因分析において陸面環境と大気・海洋との相互作用系の理解が重要であることを指摘しています。
本研究は,文部科学省北極域研究推進プロジェクト「ArCS: Arctic Challenge for Sustainability Project」及び科学研究費補助金「日本およびアジア地域における過去の地域気候変動のアトリビューション」の一環として行われ,2019 年 7 月 26 日(金)公開の Scientific Reports 誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
北極域の積雪がユーラシア大陸の熱波を強めることを解明~雪氷圏のモニタリングによる夏の季節予報の改善を示唆~(PDF)
2019-07-30
本学院生物圏科学専攻の日浦勉教授(北方生物圏フィールド科学センター)らの研究グループは,気候変動によって原生状態の針広混交林に生育する針葉樹の割合が年々低下していることを明らかにしました。
気候変動は森林生態系に様々な影響を与えていると考えられていますが,樹種ごとの応答やそのメカニズムについてはまだ不明な点が多く,特に長期モニタリングデータに基づいた研究例はわずかです。
本研究では,北海道大学中川研究林の原生保存林において17.5ヘクタールに及ぶ森林の樹木1本1本を個体識別して成長や死亡などを約40年間モニタリングし,森林生態系の変化に対する気候変動や地形などの影響を調べました。その結果,夏期の気温上昇と降水量増加がトドマツなど針葉樹の成長に負の影響を与えている一方,イタヤカエデなど広葉樹の成長には正の影響を与えていることがわかりました。2004年の台風による死亡も,針葉樹でより深刻であることが判明しました。その結果,針葉樹の割合が約20%も減少した森林がありました。これらの結果は,気候変動によって森林の姿が大きく改変されるだけでなく,その機能にも影響を及ぼしてしまう可能性を示すものです。
本研究成果は,2019年7月22日(月)公開のForest Ecology and Management誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
北海道の針葉樹は衰退している!~約40年間のモニタリングから原生林生態系への気候変動影響を解明~(PDF)