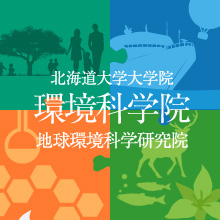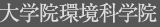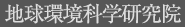南極海の二酸化炭素吸収:微細藻類の量だけでなく種類が鍵となる
2020-04-17南極海(南大洋)は,人類がこれまで放出してきた二酸化炭素(CO2)の約1割を吸収してきたと見積もられており,地球規模の炭素循環を理解する上で重要な海域です。本学院地球圏科学専攻の鈴木光次教授,吉川久幸名誉教授(地球環境科学研究院)らは,国立環境研究所,東京海洋大学,国立極地研究所の研究者らとともに,浮遊性微細藻類(植物プランクトン)の優占グループの変化が南極海のインド洋区における夏期の CO2 吸収量に影響を及ぼすことを,船舶観測と衛星画像解析により初めて明らかにしました。具体的には,特定の群集(珪藻類)が優占する年ほど,植物プランクトンの正味の炭素固定量は大きくなり,海洋への CO2 吸収量も増加することが分かりました。本研究で得られた知見は,温暖化等の気候変動によって生じる可能性がある植物プランクトンの群集変化が,海洋の炭素循環を通じて気候変動に及ぼす影響を評価・予測する上でも重要な情報です。
本研究成果は,海洋学分野の学術誌「Deep-Sea Research Part I」に2020年3⽉19日付でオンライン先行公開されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。