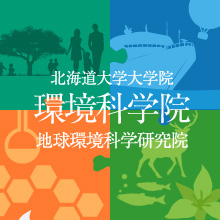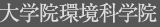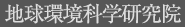海洋微生物の「老い」が雲の生成を抑える
2020-10-23本学院地球圏科学専攻の宮﨑雄三助教,西岡純准教授(低温科学研究所),鈴木光次教授,山下洋平准教授(地球環境科学研究院)らの研究グループは,亜寒帯西部北太平洋での船舶による大気と海水の同時観測から,海洋植物プランクトンの細胞老化が進むほど,海しぶきによって大気へ移行する有機物の量が増えることを明らかにし,大気微粒子(エアロゾル)がもつ雲粒の生成能力を抑制する可能性を初めて示しました。
大気エアロゾルは太陽光を散乱・吸収するほか,雲の量や降水過程に影響を与えるなど,気候変動に重要な役割を果たします。エアロゾルに最大80~90%含まれる有機物は雲生成の促進・抑制を決定づけると考えられています。地球の表面積の約7割を占める海洋の表面では,微生物の活動に伴う有機物が海しぶきにより大気へ放出されますが,海洋大気中の有機物量を支配する要因は明らかではありません。研究グループは海洋植物プランクトンの細胞「老化」に着目した指標を新たに用い,細胞老化が進むほど,海水中及び海しぶきとして大気へ放出される有機物の量が増えることを明らかにしました。さらにこの細胞老化に伴う大気エアロゾルの有機物量の増加は,雲の生成を「抑制」する可能性があることを見出しました。本成果は,温暖化等による海洋表層の植物プランクトンの活動度の変化が,大気への有機物の放出を通して雲の生成に影響することで起こる,将来的な気候影響を評価・予測する上で重要な知見となることが期待されます。
なお,本研究成果は,2020年10月12日(月)公開のScientific Reports誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
海洋微生物の「老い」が雲の生成を抑える~雲の生成を制御する大気中の有機物量の指標として,海洋微生物の老化度を新たに提唱~(PDF)