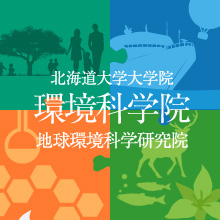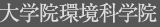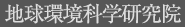過去の活動記録
2018-08-30
環境科学院では在学中に行った優れた研究を学術論文として発表した在学生および元在学生を表彰する松野環境科学賞を設けています。
厳正な選考の結果、第四回の受賞者は以下の4名に決定いたしました。
※授賞理由、論文概要などはリンク先をご覧ください。また、北大リポジトリHUSCAPへの登録があるものについては、論文全文もご覧いただけます。
樋口ゆかり 氏
【対象論文と授賞理由(PDF)】
【論文概要(学外サイト)】
Astrid Müller 氏
【対象論文と授賞理由(PDF)】
【論文概要と全文(オープンアクセス:学外サイト)】
【論文全文(HUSCAP)】
朝倉一星 氏
【対象論文と授賞理由(PDF)】
【論文概要(学外サイト)】
小原怜子 氏
【対象論文と授賞理由(PDF)】
【論文概要(学外サイト)】
授賞式は2018年9月28日(金)15時より行われる学院ホームカミングデーにおいて執り行われます(詳細は同窓会ホームページ)。
参考:「松野環境科学賞の創設について」
2018-08-28
本学北極域研究センターの漢那直也研究員,本学院地球圏科学専攻の杉山慎教授,深町康准教授(低温科学研究所)らの研究グループは,グリーンランドの氷河の融け水による湧昇流(プルーム)が,フィヨルドの中層(深さ 200 m)から栄養塩を汲み上げるポンプとして機能していることを,初めて定量的に明らかにしました。
プルームによって表層へ運ばれた栄養塩は,その後,亜表層(深さ 10~50 m)に水平的に広がっていきます。プルームの真上では,植物プランクトンがこれらの栄養塩を利用して大増殖を起こす様子が明らかとなりました。本研究は,氷河の融解が著しいグリーンランドにおいて,氷の融け水がフィヨルドの基礎生産(光合成等によって有機物が生産されること。食物連鎖の基底をなす)に果たす重要な役割を明らかにしたものです。
なお,漢那直也研究員をはじめ,共著者の大橋良彦研究員(低温科学研究所),榊原大貴研究員(北極域研究センター),野村大樹助教(水産科学研究院)はいずれも本学院を修了し、活躍されている方々です。
本研究成果は,2018年5月23日(水)公開のJournal of Geophysical Research–Biogeosciences誌にオンライン掲載されました。また,米国地球物理学連合の Research Spotlightに選ばれ,機関誌 Eos(オンライン版)に取り上げられました。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
フィヨルドの生態系を支える「氷河ポンプ」を発見~プルームによる栄養塩輸送が植物プランクトンを育む~(PDF)
2018-08-27
本学院環境起学専攻のJorge García Molinos助教(北極域研究センター)と藤井賢彦准教授,山中康裕教授(地球環境科学研究院)は,国立環境研究所,国立極地研究所の研究者らとともに,国内の温帯で急速に進行している海藻藻場の分布縮小と造礁サンゴ群集の分布拡大の全貌を初めて明らかにし,気候変動と海流輸送,海藻を食害する魚類の影響を組み込んだ解析によって,海藻藻場からサンゴ群集への置き換わりが進行するメカニズムを世界で初めて解明しました。今後も温帯では海藻藻場の減少とサンゴ群集の増加が進行するという予測結果が得られており,生態系機能・サービスも大きく変化すると予想されます。本研究は,海藻藻場やサンゴ群集への気候変動の影響の大きさを実証し,海藻を食害する魚類の個体数管理など,海藻藻場やサンゴ群集を保全していくための具体的な気候変動適応策の立案に貢献するものです。
本研究成果は,2018年8月20日(月)公開のProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(米国科学アカデミー紀要)に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
生態系の“熱帯化”:温帯で海藻藻場からサンゴ群集への置き換わりが進行するメカニズムを世界で初めて解明-気候変動,海流輸送,海藻食害による説明-(PDF)
2018-08-08
[ja]本学院地球圏科学専攻の杉山慎教授(低温科学研究所)は,山梨大学,国立環境研究所,千葉大学,国立極地研究所,東京農業大学,国立遺伝学研究所,マドリード工科大学の研究者らと共同で,世界各地の雪氷環境に生息する雪氷藻類に対して遺伝子解析を行い,特定の藻類種が北極と南極の両極から共通で検出されること,またそれらは現在も分散,交流している可能性があることを明らかにしました。
本研究成果は、2018年8月6日(月)付けのNature Communications誌にオンライン掲載されました。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
北極と南極の雪を赤く染める藻類の地理的分布の解明(PDF)
[en] Hokkaido University issued a joint press release regarding the research conducted by the international research group that includes Prof. Shin Sugiyama (Division of Earth System Science).
This research outcome is published in Nature Communications.
Please visit links below for more details.
Research Press Release (PDF in Japanese)
”Bipolar dispersal of red-snow algae” Nature Communications (open access. external link)[/en]
2018-07-27
本学院地球圏科学専攻の堀之内武准教授(地球環境科学研究院)が、米国パサデナで開催されたCOSPAR2018(2018年7月14〜22日)にて招待講演を行いました。COSPAR(国際宇宙空間研究委員会)は宇宙科学に関する国際組織で、2年に1度開催される国際会議は宇宙科学分野で最大規模です。今回、堀之内准教授は、COSPAR総裁や事務局長らによって選出されるLatest Resultsセッションの4講演のうちの1件として講演を行いました。このセッションは、世界トップクラスの研究者による最先端の研究成果が発表される場です。堀之内准教授は昨年にも本学からプレスリリースを行った金星探査機「あかつき」による金星大気の研究で国際的に高く評価され、世界をリードしています。

詳細については、COSPAR2018の公式サイトをご覧ください。
COSPAR2018(※学外サイトが開きます)
過去のプレスリリースについては以下をご覧ください。
金星大気に未知のジェット気流を発見(PDF)
2018-06-05
本学院生物圏科学専攻の三輪京子准教授(地球環境科学研究院)と博士後期課程の相原いづみさんらの研究グループは、シロイヌナズナのホウ素輸送体タンパク質である BOR1の発現が、今までに見つかっていたタンパク質「分解」による制御に加えて、タンパク質を「合成」する翻訳の段階でも環境に応じて制御されることを明らかにしました。
植物は必須栄養素であるホウ素を土壌から吸収しますが、ホウ素は多すぎると害になるため、ホウ素を取り込む量を厳密に制御する必要があります。BOR1はホウ素が少ない環境で積極的にホウ素を体内に取り込むための輸送体タンパク質です。ホウ素が十分存在する環境では BOR1はタンパク質分解を受けて量が減少することがわかっていました。本研究ではこのタンパク質分解制御に加えて、タンパク質を合成するステップである翻訳の段階においても BOR1が制御されることを示し、その機構を解明しました。輸送体の発現量の調節機構において、翻訳における制御の例は今までほとんど示されていませんでした。
また、BOR1の翻訳の制御は、分解による制御よりもホウ素濃度が高い環境で引き起こされることが明らかになりました。これは、BOR1が明らかに必要でない環境で、BOR1タンパク質を作っては壊すという制御よりも、そもそもの合成を抑制しようとする働きであると考えられます。さらに、翻訳と分解の二つの制御を失った植物体を利用して、これら二つの制御が過剰なホウ素の取り込みを防ぎ、植物の高濃度ホウ素環境への適応に貢献することを実証しました。
本研究は、植物が幅広い無機栄養環境に適応するために緻密な応答機構を獲得してきたことを示す一例となります。また今回の知見は、無機栄養の輸送の調整を通じた、栄養が少ないやせた土地や栄養が過剰に存在する不良な土壌環境にも耐える作物品種の開発への貢献が期待されます。
なお、本研究成果は、米国東部時間 2018年5月4日(金)にPlant Physiology誌にオンライン掲載されました。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
植物が過剰な栄養の取り込みを防ぐ仕組みを解明〜環境に応答して栄養輸送体の量を多段階で微調節〜(PDF)
2018-05-23
6月7日(木)10:30-12:00にEES seminarを開催します。
演者は、都市における生物の進化についてSCIENCE誌に昨年論文を発表したトロント大学のMarc Johnson博士です。
場所は、北方生物圏フィールド科学センター研究棟2F大会議室(農学部裏に隣接する建物、農学部を通って入れます)になります。
どなたでも奮ってご参加ください。
ポリコムも使用できるようにしますので、ポリコムを通じて参加される方は内海(下記連絡先)までご連絡ください。
EES seminar
Date&Time: 7 Jun 2018, 10:30-12:00
Place: Meeting Room 207, Research Laboratory, Field Science Center for Northern Biosphere (see the attached map)
Title: Evolution in life in cities
Speaker: Prof. Marc T. J. Johnson (University of Toronto, Mississauga)
Abstract:
Urban areas represent the fastest growing ecosystem on earth, in which the development of cities dramatically changes the biotic and abiotic environment to create novel ecosystems.
Despite the importance of urbanization, we have little understanding of how urbanization affects the evolution of species that live in cities.
In this talk, I will review our current knowledge of about the effects of cities on multiple evolutionary processes, including mutation, gene flow, genetic drift and natural selection.
I will then describe our work examining how these evolutionary processes affect the ability of plants to adapt to urban environments.
I will conclude with a discussion of existing gaps in our knowledge and a description of the first global study of urban evolution, in which we are looking for Japanese collaborators.
Relevant literature:
Johnson MTJ, Munshi-South J. (2017) Evolution of life in urban environments. Science 358, aam8327.
Thompson KA, Renaudin M, Johnson MTJ. (2016) Urbanization drives the evolution of parallel clines in plant populations.
Proceeding of the Royal Society B: Biological Sciences 283, 20162180.
Santangelo JS, Johnson MTJ, Ness RW. (In Press) Modern spandrels: the roles of genetic drift, natural selection and gene flow in the formation of parallel clines. Proceeding of the Royal Society B: Biological Sciences (https://www.biorxiv.org/content/early/2018/03/27/289777)
Johnson MTJ, Thompson KA, Saini HS. (2015) Plant evolution in the urban jungle. Am. J. Bot. 102, 1951-1953.
【Contact】:
Shunsuke Utsumi
Field Science Center for Northern Biosphere
Kita 9 Nishi 9, Sapporo, Hokkaido 060-0809
Tel : 011-706-2589
Email : utsumi@fsc.hokudai.ac.jp
2018-05-11
本学院地球圏科学専攻の三寺史夫教授(低温科学研究所)らの研究グループは、水深約 5,500m の深海におけるわずかな海底起伏が、実は海の表面の海流や水温前線をコントロールしている、という新たな海流形成 メカニズムを発見しました。
2000 年代になって、北海道の東方 1,000 kmの沖合に黒潮を源とする海流(通称・磯口ジェット)が見出されました。温かい黒潮水を運ぶ磯口ジェットは、親潮による亜寒帯海水との間に強い水温前線を作るため、その周辺海域は好漁場となっています。またその変動は、北半球規模の気候変動を引き起こす要因であることも最近の研究でわかってきました。しかし、磯口ジェットがなぜ岸から 1,000kmも離れた海域に安定して存在するのか、その形成メカニズムは謎のままでした。
本研究では、従来見過ごされてきた、水深約 5,500mの深海底における500m程度の低い緩やかな海底地形(北海道海膨 かいぼう)が、渦−地形相互作用を通して海洋表層の磯口ジェットと海面水温前線を驚くほど効率的に生み出すという、新たなメカニズムを発見しました。背の低い緩やかな海底地形は 世界中の海のいたるところにあるため、中高緯度の様々な海で、今回発見した海流形成メカニズムが働いていることが予想されます。本研究を基礎にした海洋学、水産学、気候学の進展が期待されます。
本研究成果は、2018年3月22日(木)公開のNature Communicationsに掲載されました。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
深海底の緩やかな起伏が表層海流と海面水温前線を生む〜亜寒帯の表層海流と強い海面水温前線をつくり出す新メカニズムを発見〜(PDF)
2018-03-16
本学院地球圏科学専攻の飯塚芳徳助教(低温科学研究所)が参画する国際共同研究グループが、日本の南極地域観測隊により南極ドームふじで掘削されたアイスコアを分析することで、過去72万年間の南極の気温と周辺海域の水温変動を復元しました。本研究のように、海水温も含めてアイスコアから復元したデータとしては、過去最長だった 42 万年間の記録を 30 万年延長するものです。地球温暖化をはじめとする気候変動を正確に予測することが社会的にも大きな課題となっています。今回の研究は、環境が大きく異なっていた過去について、二酸化炭素濃度や日射量の変動と気温変動との関係を明らかにしたもので、地球の気候変動のメカニズムの解明に役立つと期待されます。
本研究成果は、2018年3月6日(火)付けのNature Communications誌にオンライン掲載されました。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
南極の気温と二酸化炭素変動の不一致は日射量が引き起こす‐過去 72 万年間の南極と周辺海域の温度変動を復元‐(PDF)
2018-03-16
本学院生物圏科学専攻の鍵谷進乃介さん(博士後期課程)と内海俊介准教授(北方生物圏フィールド科学センター)らの研究グループは、樹木の遺伝的な違いから、その樹上に生息する多様な昆虫の種の組合せを予測する法則を発見しました。
生物種の集合において、「どの種とどの種が同じエリアに生息するか(種の組合せ)」は場所や年によって異なるのが一般的です。また、種の組合せの違いによって、地域全体の生物多様性の豊かさは大きく変わってきます。つまり、種の組合せは、生物多様性を効果的に保全するうえで極めて重要な情報です。しかし自然生態系では、気象条件や多様な生物のつながりなど複雑な要素が影響するため、種の組合せの予測は一般に困難と考えられてきました。
そこで、内海准教授らは、樹木のゲノム情報からその樹上に集まる昆虫種の組合せの違いを予測するというアプローチによってこの問題に取り組みました。その結果、昆虫種の組合せは樹木の遺伝的な変異が大きいほど異なっており、その予測精度は、位置情報や周囲環境の効果をはるかに上回っていることがわかりました。また、年による虫の変化パターンも、樹木の遺伝的な変異から説明できました。樹木の遺伝的な変異は、昆虫―植物間や昆虫間の様々な生物間相互作用を通して昆虫群集全体に大きな波及効果を持っていたのです。これは、複雑な自然生態系において、植物の遺伝子が従来考えられていたよりはるかに強く生物の集合に影響していることを示す結果です。同時に、種内の遺伝的変異の損失という一見小さな事象でさえ、その地域の生物間の関係性に甚大な影響を及ぼすリスクが潜んでいることも示しています。
本研究成果は、2018年3月6日(火)公開のMolecular Ecology 誌(進化生物学・生態学の国際トップジャーナル)に掲載されました。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
樹のゲノムは虫のコミュニティを左右する〜樹木の遺伝的な違いから昆虫種の組合せを予測〜(PDF)
Research Press Release (英語版)
2018-03-09
本学院生物圏科学専攻の日浦勉教授(北方生物圏フィールド科学センター)は、筑波大学の佐伯いく代准教授、平尾章助教、田中健太准教授らとともに、カエデの一種で絶滅が危惧されるクロビイタヤについて、生育地周辺の森林の状況と、遺伝的な変異のパターンとの関係(景観遺伝学)の調査を行いました。
その結果、クロビイタヤは生育地周辺の森林が消失し、連続性が途絶えている場所ほど、他の地域の個体との遺伝的な違いが大きくなる傾向があることがわかりました。これは、森林が消失すると、花粉を媒介する昆虫が少なくなり、個体間での遺伝的な交流(以下、遺伝子流動)が起こりづらくなるためと考えられます。他地域からの遺伝子流動が途絶えると、遺伝的に近縁な個体どうしが交配しやすくなるため、種の存続にマイナスの影響を与えるおそれがあります。
クロビイタヤは、宮部金吾博士(北海道大学植物園初代園長)によって北海道で発見され、北海道大学植物園のシンボルマークにも使われています。本種は河川の氾濫原にある湿地などに生育しますが、こうした場所は人にとっても利用しやすく、農地や宅地として開発が進められてきました。森と河川の豊かな我が国では本来、もっと多くの場所でクロビイタヤを見ることができたことでしょう。本研究では、景観遺伝学の解析手法を用い、森林の消失によって遺伝子流動が弱くなっている地域を推定することができました。そのような場所を中心に森林の保護や復元を進めていくこと、また遺伝子流動に影響を与えると予測される1km2以上の森林開発をできるだけ行わないことなどが、本論文では提案されています。
本研究成果は、2018年2月28日「Biological Conservation」電子版で公開されました。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
森の分断・消失が希少種に及ぼす影響〜絶滅危惧種クロビイタヤの景観遺伝学的研究からの提言〜(PDF)
2018-03-01
環境科学院では、学院での研究活動について構成員相互に、また広く社会一般に知っていただくことを目的に、環境科学院写真コンテストを毎年実施しています。
このコンテストでは、環境科学院・地球環境科学研究院に所属する教員および学生、PD等を対象に、研究活動中の風景や研究対象、 実験や作業風景、活動スナップなど環境科学院での研究にかかわる写真を幅広く募集し、環境科学院広報委員会での審査により各賞を選出いたします。
今年は15名から53作品のご応募を頂き、厳正な審査の結果、以下の7点が2017年の受賞作品に選出されました。受賞作品は、環境科学院正面ロビーに展示されます。また、応募作品は環境科学院紹介パンフレット等の広報写真として掲載される予定です。
![]()
最優秀賞
「さあ、行こう」山本淳博氏(地球圏科学、M2)
『アルゼンチン・ペリートモレノ氷河で先輩と2人きりの観測の様子です。GPSなどを用いて氷河の上を歩き回りました。』
![]()
優秀賞
「Mighty step into vast tundra」Shakhmatov Ruslan 氏 (地球圏科学、D1)
『Fieldwork in tundra requires covering of long distances over moist terrain on foot. Stunning view. (Chokurdakh, Russia)』
![]()
優秀賞
「雪中松柏」松下 侑未 氏 (地球圏科学、M2)
『トマムに設置してある気象観測測器のメンテナンス中のひとコマ』
![]()
優秀賞
「トゥスニンケ—願い事の神様—」渡辺 充 氏 (生物圏科学、M2)
『木の実を食べる様子が願い事をしているように見える事から、エゾリスはアイヌ語でトゥスニンケカムイと呼ばれていたようです。』
![]()
カバーフォト賞
「Walking along the beach with the sea wind」ZHOU JINGHUI 氏 (環境起学、M2)
『Last year, I took the course of field work integrated environmental geography. We went to Tokachi and the beach near the Tokachi. In the photo we are looking for a good point to measure with the simple measuring equipment.』
![]()
カバーフォト賞
「寒い冬に備えて」内田 健太 氏 (生物圏科学、D3)
『秋のエゾリスは寒い冬に備えてご多忙です。いつもは樹上にいるリスもこの時は地面を忙しく走り回ります。暖かそうな巣材です。』
![]()
カバーフォト賞
「真空系」藤元 もも 氏 (環境物質科学、M1)
『真空系のメンテナンスをしている様。』
2018-02-05
本学院地球圏科学専攻の力石嘉人教授(低温科学研究所)は国立研究開発法人海洋研究開発機構海洋生命理工学研究開発センターの布浦拓郎主任研究員らとともに、南部沖縄トラフの熱水活動域から採取した試料より単離した細菌が、アミノ酸など生命に必須の化合物の生合成に不可欠なTCA 回路(tricarboxylic acid 回路:クエン酸回路)の中でも、最も始原的な形態の回路を有することを発見しました。
本研究成果は、米国科学誌Science に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
生命誕生に迫る始原的代謝系の発見〜多元的オミクス研究による新奇 TCA 回路の証明〜(PDF)
Research Press Release (英語版)
2018-01-26
本学院生物圏科学専攻の野田隆史教授らの研究グループは、様々な自然災害の野生生物へのダメージを比較する新たな方法の開発に成功しました。
自然災害は生物の個体群に急激な減少をもたらします。これまで、台風、寒波、津波といった異なる種類の自然災害が種類の異なる生物の個体群に及ぼす被害を総合的に比較する方法はありませんでした。野田教授らの研究グループはこの比較方法を新たに開発し、海藻やフジツボなど海岸の岩礁に生息する生物にとっての東日本大震災の津波の被害と、様々な生物にとっての気象災害を比較しました。その結果、驚くべきことに、津波の強度は爆弾低気圧などの気象災害と比べて極めて大きいにも関わらず、岩礁の生物における津波の被害はこれらの気象災害より小さかったことが明らかになりました。
本研究で開発した自然災害が生物個体群へ及ぼす被害の比較方法は、自然災害のリスクの評価やその予測に貢献することが期待されます。
本研究成果は、Scientific Reports 誌に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
岩礁の生物への巨大津波の影響は意外に小さかった!(PDF)
2018-01-24
本学院地球圏科学専攻の飯塚芳徳助教(低温科学研究所)らの研究グループは、21 世紀になってからの北極の硝酸エアロゾルフラックス(流束)が、周辺国による NOx(窒素酸化物)の排出抑制政策を反映せず、高い値を維持していることを明らかにしました。
同グループは北極グリーンランド氷床にいくつかある頂上(ドーム)のうち、最も雪が多く降る南東部で約90mのアイスコア掘削に成功し、氷床ドームアイスコア史上最高の年代精度で過去60年間の北極大気環境を復元しました。このアイスコアに含まれる過去60年間のNO3–(硝酸イオン)の季節フラックスの変動を求め、各国からのNOx排出量の変動割合と比較したところ、両者は一致していませんでした。NOx排出量は1970–80年以降、減少傾向を示していますが、アイスコアのNO3–フラックスは1990 年代が最も高く、2000年以降(21世紀)は1960-80年代よりも高いという特徴があります。
今回の結果は、北極大気のNO3–フラックスが周辺国(米国や欧州)における排出抑制政策によるNOxの減少割合を反映せず、高い値を維持していることを示しています。今後、北極NO3–フラックスがNOx 排出量と連動せず高い値を維持している原因と、将来の人間活動への影響を評価する必要があります。
本成果は、2報の学術論文として、2017年10月26日と2018年1月4日(Web版)のJournal of Geophysical Research: Atmospheres 誌に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
北極の硝酸エアロゾルは NOx排出抑制に関わらず高止まり〜過去60年のグリーンランド氷床に記録された北極大気NO3–フラックスの変遷〜(PDF)
2017-12-18
本学院生物圏科学専攻の落合正則准教授(低温科学研究所)と佐賀大学農学部の早川洋一教授らの国際共同研究グループは、環境ストレスに応答する昆虫サイトカインの受容体の同定にはじめて成功しました。サイトカインは様々な細胞間相互作用を橋渡しするタンパク質性因子で、外部からの影響に対して体内の環境を一定に保とうとする「恒常性」の維持に重要な役割を担っています。昆虫の発育阻害ペプチド(Growth-blocking peptide、 GBP)は多機能性のサイトカインで、外部の環境から受ける様々なストレスに応答し、免疫や代謝などをコントロールしています。
本研究では、これまで特定されていなかった GBP 受容体をキイロショウジョウバエにおいて同定し、その性質を明らかにしました。また、この受容体が環境ストレス応答において重要な役割を果たしているだけでなく、生体の寿命にも影響していることがわかりました。本研究は、健康長寿に対する一つの提案として基礎的な研究知見を提供するものです。
本成果は、米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
ストレスに対抗するための遺伝子が昆虫の寿命を縮める〜ストレスに応答する昆虫サイトカインの受容体を同定〜(PDF)
2017-11-01
極東ロシアでは、人為的な要因などにより山火事が頻発しています。山火事は、樹木などを燃焼することで木の中に蓄えられた炭素を二酸化炭素(CO2)として放出することは既にわかっていました。
今回、本学院生物圏科学専攻の小林真助教(北方生物圏フィールド科学センター)はロシア科学アカデミーの研究者らと共に、山火事で生成され土壌に混入した炭が、枯死した状態で土壌に残された根の分解を促進することを明らかにしました。本成果は、山火事はその発生時の燃焼によるだけでなく、炭を作り出すことで発生後にも長期的に森林からのCO2の放出速度を高めるという新たなメカニズムの存在を示しています。
本成果は、土壌生物学に関する国際誌『Soil Biology & Biochemistry』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
山火事がロシアの森林からのCO2放出速度を長期的に高める新メカニズムを発見(PDF)
2017-10-12
生態系は、別の生態系から運ばれてくる資源に支えられています。例えば、河畔域に生息する陸上捕食者(鳥、昆虫など)は、陸上の生物に加え、河川から羽化してくる水生昆虫をエサとして利用します。しかし、こうした「生態系間のつながり」は広く知られている一方、河川内で生じた変化が、陸上生態系にどれほどの影響力を持つのかはよくわかっていません。今回、本学農学研究院の照井慧研究員、中村太士教授、本学院環境起学専攻の根岸淳二郎准教授、博士後期課程の渡辺のぞみさんからなる研究グループは、河川内の藻類生産(一次生産)の影響に注目し、隣接する陸上生態系(砂礫河原)への波及効果を調べました。その結果、川の中の藻類生産の増加は、羽化昆虫を介して陸上捕食者(オサムシ科甲虫)の増加をもたらすだけでなく、砂礫河原上のエサ資源(人為的に添加したエサ)の減少にまでつながることがわかりました。
以上の成果は、ある生態系の基盤の変化が、隣接する別の生態系の“食う-食われる”関係にまで波及することを野外で示した数少ない研究事例です。
本成果は、生態系生態学に関する国際誌『Ecosystems』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
川の中の藻類が、陸の上の“食う-食われる”関係まで左右する(PDF)
2017-09-08
北海道最高峰である旭岳では、雪解けが進む春、低温環境でも生育できる氷雪藻(ひょうせつそう)が作る色素により雪面が鮮やかに染まる、彩雪という現象が起こります。例えば、氷雪藻の光合成色素(葉緑素)は緑色に、補助色素(カロチノイド色素)の細胞内蓄積はオレンジや赤色に、それぞれ雪を彩ります。氷雪藻は日本の高山でも長く観察されていますが、旭岳の彩雪がどのような微生物群集(氷雪藻などの集まり)によるものかは明らかになっていませんでした。
本学院生物圏科学専攻の寺島美亜助教、博士後期課程の梅澤和寛さん、小島久弥助教、福井学教授(低温科学研究所)らの研究グループは、今回、旭岳で雪を採取し、次世代シーケンスによる微生物群集の解析と氷雪藻の単離を行いました。微生物群集解析からは、ベータプロテオバクテリアと呼ばれる種類の細菌が高い割合で氷雪藻と共存していたことが明らかになりました。また、単離に成功した氷雪藻を培養したところ、やはりベータプロテオバクテリアの細菌が検出されました。
本研究は、旭岳彩雪の原因となる微生物群集を確認しただけではなく、氷雪藻とベータプロテオバクテリアが互いに助け合っている可能性を明らかにしました。また、観光客が少ない融雪期の山岳地帯(旭岳「姿見の池」周辺)ならではの彩雪現象は、新たな観光資源にもなり得ます。
本成果は、微生物に関する専門誌『Frontiers in Microbiology』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
北海道最高峰の旭岳を染める彩雪の謎を探る〜藻類と細菌が織りなす生態系〜(PDF)
2017-09-01
環境科学院では一昨年度より、在学中に行った優れた研究を学術論文として発表した在学生および元在学生を表彰する松野環境科学賞を創設しております。
厳正な選考の結果、第三回の受賞者は以下の4名に決定いたしました。
※授賞理由はリンク先をご覧ください。
Md. Shariful Islam 氏
【対象論文と授賞理由(PDF)】
【論文概要】
佐伯立 氏
【対象論文と授賞理由(PDF)】
【論文概要】
Venus Leopardas 氏
【対象論文と授賞理由(PDF)】
【論文概要】
藤田彩華 氏
【対象論文と授賞理由(PDF)】
【論文概要】
授賞式は2017年9月29日(金)15時より行われる学院ホームカミングデーにおいて執り行われます(詳細は同窓会ホームページ)。
参考:「松野環境科学賞の創設について」
2017-08-31
本学院地球圏科学専攻の堀之内武准教授(地球環境科学研究院)らの国際研究チームは、金星大気の分厚い雲を透かして観測できる探査機「あかつき」の観測データを使って金星大気の風速を求めました。その結果、2016 年のある時期に、中・下層雲領域(高度45〜60km)の風の流れが赤道付近に軸をもつジェット状になっていたことがわかり、これを赤道ジェットと命名しました。これまで、この高度帯の風速は水平一様性が高く、時間変化も少ないと考えられてきましたが、予想外に大きな変動があることが、「あかつき」の観測による今回の研究ではじめて明らかになりました。
金星の大気の流れは地面から雲頂(高度約70km)にかけて急激に増加し、自転をはるかに上回る速さで流れる「スーパーローテーション」と呼ばれる状態になっていますが、そのメカニズムはまだ解明されていません。今回発見された赤道ジェットの形成を理論や数値計算に取り入れることで、その謎に一歩迫れると考えられます。
本成果は、英科学誌『Nature Geoscience』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
金星大気に未知のジェット気流を発見(PDF)
2017-08-30
北極海の夏の海氷面積はこの 40 年で半減し、北極海は一年中海氷に覆われる多年氷域から、夏には海氷がなくなる季節海氷域へとシフトしつつあります。この海氷の激減については、いくつかの要因が指摘されています。柏瀬陽彦研究員(国立極地研究所)と本学院地球圏科学専攻の大島慶一郎教授(低温科学研究所)が中心となり実施された本研究では、海氷−海洋アルベドフィードバックが重要な要因であることを、衛星観測による海氷データ等の解析から明らかにしました。海氷−海洋アルベドフィードバックとは、日射に対する反射率(アルベド)が黒い開水面では白い海氷表面より小さいため、海氷域で水開き(開水面)が一旦広がると、開水面から吸収された日射による熱により海氷が融解され、さらに開水面を広げ、海氷融解を加速するというものです。融解初期に海氷の発散量(海氷が拡がる方向に動く割合)が大きいと、このフィードバックが有効に働き、融解が進みます。2000 年代以降、多年氷などの厚く動きにくい海氷が減ることで発散量が増加し、フィードバックが働きやすくなったことが海氷激減の一因と考えられます。 本成果は、英科学誌『Scientific Reports』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
北極海の夏の海氷が激減したメカニズムを解明―黒い開水面が吸収する日射の効果―(PDF)
2017-08-22
大気中の浮遊微粒子(エアロゾル)は雲の生成に大きな役割を果たしていますが、非常に多くの自然発生源をもちます。特に温暖化等の影響を受けやすい寒冷域の陸上生態系で発生する有機物は、雲の生成等を通して気候の変化に影響を与えるため、その起源や気候影響の理解が近年、特に重要視されています。本学院地球圏科学専攻のAstrid Müllerさん、宮崎雄三助教、生物圏科学専攻の日浦勉教授らのグループは冷温帯林の代表的な植生を有する北海道大学苫小牧研究林において長期的な大気観測を行い、大気エアロゾルが雲を生成する能力は微粒子に含まれる硫酸塩と水溶性有機物の質量比によって制御されることを明らかにしました。雲の生成を促進する硫酸塩と比べ、有機物の存在割合が相対的に大きくなる秋に、この生成能力が最小となることを発見し、この季節に土壌や落ち葉など森林内の地表付近から大気へ放出される有機物がエアロゾルの雲粒生成能力を抑制する可能性を初めて示しました。 従来、大気に対する影響要因としては植物の葉から放出される有機物が主要であるとの考えが主流でしたが、雲粒の生成能力に対する地表付近の有機物の重要性を初めて指摘した本研究の成果は、温暖化等による植生・土地利用の変化に伴う将来的な気候への影響を精度よく予測する上で重要な知見となることが期待されます。 本成果は、英科学誌『Scientific Reports』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
冷温帯林の地表付近からの有機物放出が雲の生成を抑える証拠を発見(PDF)
2017-08-21
本学院の鈴木仁教授(生物圏科学専攻)らのグループはこれまで30年以上にわたり、日本列島を含むユーラシア産ハツカネズミの遺伝的多様性の調査を行ってきました。今回、遺伝子塩基配列の解析により、長年不明であった日本産ハツカネズミの起源と渡来の時代背景を明らかにしました。野生ハツカネズミは、有史以前の人類の農耕技術の革新的発展とともに、約4000年前に中国南部から一度、そして、約2000年前に朝鮮半島より2度目の移入があったことが示されました。これら2つの系統は西日本で最初に混合しましたが、北日本では西日本より1000年ほど遅れて混合していたことも明らかとなりました。さらに、これら2系統の移入以前にも、南アジア起源の系統が日本列島に移入した可能性があることも示唆されました。 本成果は、生物学分野の英国学術誌『Biological Journal of the Linnean Society』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
日本産ハツカネズミのルーツをはじめて特定〜日本人の起源を考える上で重要な発見〜(PDF)
2017-08-10
福井県立大学の大石善隆講師と本学院の日浦勉教授(生物圏科学専攻、苫小牧演習林)の研究グループは、コケ植物を利用して、都市の大気環境を効率よく評価する方法を開発しました。単純な構造の体をもつコケは環境の変化に敏感に反応し、特に、大気環境の影響を強く受けることが知られています。本研究成果から、コケに含まれる窒素重量やその安定同位体比を解析することで、都市で深刻になりつつある窒素汚染の状況を評価できることが明らかになりました。またコケの形(生育形)を利用して、ヒートアイランド現象に伴って生じる乾燥化の程度が把握できることもわかりました。なお、これらのコケ指標を同時に利用することで大気環境問題の相互関係を考察することもできます。
本成果は、景観生態学の専門誌『Landscape and Urban Planning』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
身の周りの「コケ」を利用して都市の大気環境を診断(PDF)
2017-08-05
本学の高等教育推進機構は、全学教育科目にかかる授業アンケートの総合評点上位の教員の中から「全学教育科目に係る授業アンケートにおけるエクセレント・ティーチャーズ」を選定しています。
今回、昨年度の授業に対するエクセレント・ティーチャーズ32科目が発表され、本学院の大原雅教授と山崎健一准教授(ともに生物圏科学専攻)が選出されました。大原教授は5年連続の選出です。
選定対象となった授業
基礎科目(第2位)「生物学?」大原雅教授
基礎科目(第5位)「生物学?」山崎健一准教授
詳細については、以下の高等教育推進機構ホームページをご覧ください。
http://educate.academic.hokudai.ac.jp/center/enquete/enquete.htm
2017-07-25
北海道の日本海側ではコンブ等の大型海藻類が消失し、それを餌とするウニやエゾアワビ等の生産が減る「磯焼け」が喫緊の課題です。磯焼けの一因としては、海の天然肥料である栄養塩との関連性が指摘されていますが、磯焼けが発生する以前(1930 年頃)の栄養塩の状態を知ることのできる科学データはこれまで存在しませんでした。
この問題を解決するため、栗林貴範博士(本学院で社会人学生として学位取得。北海道原子力環境センター)は、本学総合博物館の阿部剛史講師、本学院生物圏科学専攻の門谷茂特任教授とともに、本学総合博物館が所蔵する 1881 年から 134 年分のコンブ標本の窒素安定同位体比を調べ、この海域の過去の栄養状態の復元を試みました。
その結果、1881〜1920 年(明治から大正期)の日本海側の栄養状態が他の年代や海域と大きく違っていたことがわかりました。明治から大正期の北海道では、現在の 500 倍から 1000 倍に及ぶ大量のニシンが漁獲され、その90%以上は日本海側のものでした。このことから沿岸に押し寄せたニシンの卵や精液、水産加工で出る煮汁などがコンブの栄養源となっていたことが考えられます。本成果は、科学誌『PLOS ONE』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
北海道の栄華をかつて極めたニシンはコンブをも育てていた〜ニシンが栄養源として寄与、100 年以上前のコンブから検証〜(PDF)
論文PDFは『PLOS ONE』誌公式サイトから無料でダウンロードできます。
Historical δ15N records of Saccharina specimens from oligotrophic waters of Japan Sea (Hokkaido) (学外サイト)
2017-07-12
国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)の藤田実季子技術研究員と本研究院統合環境科学部門の佐藤友徳准教授は、GPS衛星電波が大気中の水蒸気の多さによって遅延することを利用し、日本各地における過去15 年間の大気中の水蒸気量(可降水量)を推定しました。そして、日平均地上気温との関係を解析したところ、これまでに予想されていたよりも大きい変化率で気温上昇に対して可降水量が増加していることを明らかにしました。本結果は水蒸気量の観測結果ですが、上空の水蒸気量と地上の降水量には密接な関係があるため、将来の降水強度の変化を理解する上でも大いに役立つと考えられます。本成果は、英科学誌『Scientific Reports』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
気温上昇で急激に増加する水蒸気量―降水がより激しくなる可能性を指摘―(PDF)
論文PDFは『Scientific Reports』誌公式サイトから無料でダウンロードできます。
Observed behaviours of precipitable water vapour and precipitation intensity in response to upper air profiles estimated from surface air temperature (学外サイト)
2017-07-04
本学院地球圏科学専攻の杉山慎教授と平野大輔助教(共に低温科学研究所)が第59次南極地域観測隊夏隊に参加することが決定いたしました。
詳細については、以下の文部科学省webサイトをご覧ください。
第59次南極地域観測隊員等の決定について(学外サイト)
2017-06-05
黄砂は健康への影響リスクが懸念されており、黄砂飛来の情報を正確に捉えることはとても重要です。しかしながら、気象庁が行う目視観測では黄砂を捉えきれないケースも過去にあり課題となっています。今回、北海道大学大学院工学研究院の安成哲平助教らの研究チームは、 衛星画像で北海道に到達する黄砂と思われるモヤが確認できるものの、気象庁による黄砂の観測報告がなかった2016年3月7日を対象とし、北海道大学構内(札幌市)及び滝川市での大気汚染観測機器から得られたデータ及び NASA 作成の全球グリッド再解析データを用いて、客観的手法による黄砂判別解析を試みました。研究チームには本学院地球圏科学専攻の的場澄人助教(低温科学研究所)も参加しています。 本成果は、日本気象学会の英文レター誌『Scientific Online Letters on the Atmosphere (SOLA)』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
黄砂観測の判定精度向上に資する観測的手法を提案(PDF)
2017-04-25
魚類に寄生するウオノエやタイノエは釣り人にはなじみの深い生物です。ウオノエ類は世界中で約400種が知られており、淡水域から深海まで生息し、寄生する場所も魚の口やエラ、体表など多様化していますが、その進化の道筋はこれまでほとんどわかっていませんでした。愛媛大学の畑啓生准教授は、本研究院統合環境科学部門の川西亮太特任助教、弘前大学、総合地球環境学研究所の共同研究者らと共に、日本国内外に生息するウオノエ類とその近縁科のDNAに基づく系統解析を行い、ウオノエ類の共通祖先が深海に生息していた可能性を示しました。また、淡水魚に寄生する種は南米大陸とアフリカ大陸とで別々の時期に独立に進化したことも明らかとなりました。本成果は、海洋生物学分野の学術雑誌『Marine Biology』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
淡水・汽水・海水 どこでも魚に寄り添う生き物「ウオノエ」の起源は深海だった(PDF)
2017-04-25
北部北太平洋における植物プランクトンの成長は、鉄(Fe)の利用能によって制限されることがよく知られています。今回、本学院地球圏科学専攻の西岡純准教授(低温科学研究所)と東京大学大気海洋研究所の小畑元准教授の研究チームが、北部北太平洋の鉄(Fe)濃度の東西断面分布を世界で初めて捉えることに成功しました。そして、北西部北太平洋中層付近に北方の縁辺海(えんぺんかい)から Fe が供給されることで、同海域が高い生物生産域となっていることを解明しました。本成果は、米国海洋陸水学会の学会誌『Limnology and Oceanography』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
縁辺海からの鉄分供給によって北西部北太平洋は高生物生産域になることを解明(PDF)
2017-04-17
本学院地球圏科学専攻の青木茂准教授(低温科学研究所)が人工衛星画像を用いて南極の昭和基地沖の定着氷の崩壊を調査し、定着氷の崩壊の強さが熱帯太平洋の海面水温と相関していることを発見しました。定着氷とは、陸などに固着して成長するほとんど動かない海氷のことで、昭和基地周辺はこの定着氷に閉ざされて南極の沿岸でも到達が難しい場所として知られます。今回の成果を基に、今後定着氷の振る舞いや性質の理解を進め、より高い精度でそれらを予測することができるようになれば、南極観測艦「しらせ」による輸送計画の長期的な見通しも立てやすくなると期待されます。本成果は、地球物理学の専門誌『Geophysical Research Letters』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
熱帯太平洋が熱いと南極昭和基地の氷が割れる!?(PDF)
2017-04-13
「星野リゾート トマム」などを運営する星野リゾート(所在地:長野県北佐久郡軽井沢町、代表:星野佳路)と北海道大学大学院環境科学院との長期的な産学連携活動に関する研究論文が、観光の学術誌『Journal of Sustainable Tourism』に掲載されました。同誌が注目するのは、社会・経済的な利益をもたらしながら環境資源や地域の文化遺産を尊重するという、持続可能な観光です。今回掲載された論文は、産学の大規模な連携における珍しい成功例であるとともに、持続可能な観光の大きな可能性を示すものとして評価されました。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
星野リゾートと北海道大学大学院環境科学院の産学連携活動の持続可能な観光創造の可能性が評価(PDF)
2017-04-10
本学院環境起学専攻の吉村暢彦さん(博士後期課程3年)と生物圏科学専攻の日浦勉教授(北方圏FSC)は、SNS(Flickr)で共有されている位置情報付きの写真から、景観の文化的価値を評価する方法を開発しました。本手法は景観の価値を広域的かつ詳細に評価でき、また様々な場所に適用可能です。需要と供給の両面から自然の文化的価値(生態系サービス)を認識できることから、環境保全や観光利用等をどこで行うかを決定する際に役立つことが期待されます。本研究の成果は、生態系サービスに関する専門誌『Ecosystem Services』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
SNS に投稿された写真から北海道の景観の価値を評価〜需要と潜在的価値の空間分布〜(PDF)
2017-04-10
筑波大学の佐伯いく代准教授、本学院生物圏科学専攻の日浦勉教授(北方圏FSC)らの研究グループは、樹上性カタツムリの一種であるサッポロマイマイがなぜ木の上という特殊な空間を利用するのかを明らかにするため、その生態を調査しました。その結果、林床での冬眠を終えたカタツムリは樹上に移動し、秋になると再び冬眠のため林床に移動すること、樹上の捕食圧は林床よりも低いこと、樹上では林床性のカタツムリとは異なる食物を利用していることなどが判明しました。
風通しのよい木の上は、カタツムリの生息にはあまり適していないと一般的には考えられています。しかし本研究から、サッポロマイマイは、捕食者が少ない上に食物に不自由しない樹上という環境にうまく適応進化していることがわかりました。
本研究は、樹上生活への適応的意義を、カタツムリという超スローライフな樹上性動物に着目することにより、自然環境下で実験的に証明した点で評価されます。また、高木の生える原生林を保護することの意義を考える上でも示唆に富む成果です。
本研究の成果は、動物行動学に関する学術誌『Animal Behaviour』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
木登りカタツムリはなぜ木に登る?〜樹上生活性が進化した適応的意義〜(PDF)
2017-03-23
大学院地球環境科学研究院 物質機能科学部門 七分勇勝准教授が,第31回となる平成28年度日
本化学会「若い世代の特別講演会」の講演者に選定されました。
研究業績「核数・形状制御された金属サブナノクラスターの光化学特性と電子構造解析」
日本化学会年会 若い世代の特別講演会 歴代講演者一覧
http://www.csj.jp/nenkai/standing/young.html
2017-02-20
本学院生物圏科学専攻の三浦徹准教授らと名古屋大学、ワシントン州立大学、モンタナ大学の研究者からなる研究グループが、クワガタムシの発達した大顎(おおあご)を形作る際に重要となる遺伝子群を特定しました。本成果は、発生生物学分野の国際専門誌『Developmental Biology』に掲載されています。なお、責任著者の後藤寛貴博士(現:名古屋大学特任助教)は本学院の修了生であり、今年度の本学院松野環境科学賞受賞者でもあります。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
クワガタムシの大顎を形作る遺伝子を特定(PDF)
2017-02-20
国立極地研究所の川村賢二准教授と本山秀明教授、東京大学大気海洋研究所の阿部彩子教授を中心とする 31 機関 64 名からなる研究グループが、南極ドームふじで掘削されたアイスコアの解析と気候シミュレーションから過去72万年間の気候の不安定性を解明しました。本学院からは、地球圏科学専攻の吉森正和准教授(地球環境科学研究院)、Ralf Greve教授、飯塚芳徳助教(低温科学研究所)が参加しています。本成果は、アメリカ科学振興協会(AAAS)のオープンアクセス学術雑誌『Science Advances』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
過去 72 万年間の気候の不安定性を南極ドームふじアイスコアの解析と気候シミュレーションにより解明(PDF)
2017-02-20
本学院博士後期課程の山千登勢さんと本研究院の小泉逸郎准教授による乱婚性ヤツメウナギの繁殖生態に関する研究成果が日本動物行動学会の英文誌『Journal of Ethology』に発表されました。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
100 回も交配する乱婚性ヤツメウナギ 実はほとんどが偽りの交配(PDF)
2017-02-02
環境科学院に所属する下記4名の教員が,平成28年度北海道大学研究総長賞および教育総長賞を受賞しましたので,お知らせします。
【研究総長賞】
<奨励賞>
生物圏科学専攻 生態遺伝学コース 三浦 徹 准教授 (地球環境科学研究院)
地球圏科学専攻 大気海洋化学・環境変遷学コース 西岡 純 准教授(低温科学研究所)
【教育総長賞】
<奨励賞>
地球圏科学専攻 大気海洋化学・環境変遷学コース 鈴木 光次 教授(地球環境科学研究院)
環境起学専攻 人間・生態システムコース 藤井 賢彦 准教授 (地球環境科学研究院)
2017-01-23
地球環境科学研究院 山本正伸准教授が,「2016年度有機地球化学賞(学術賞)」を,環境科学院地球圏科学専攻の滝沢侑子さんが「ポスター発表賞」を受賞しましたので,お知らせいたします。
受賞に関する詳細については,下記URLを参照願います。
http://ogeochem.jp/pdf/NL65.pdf
2017-01-13
本学院は、文部科学省の「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」に採択されており、平成27年から現在までに合計12名(スーパーグローバル大学枠2名を含む)の外国人留学生が入学し、研究や勉学に励んでいます。今回、入学から1年が経過した修士および博士後期課程大学院生による研究成果の報告セミナーが12月27日に開催されました。セミナーには、特別プログラムの留学生全員のほか、プログラム運営委員会や指導教員の先生方8名も出席され、活発な議論が行われました。



2017-01-11
本研究院の小泉逸郎准教授および本学院の大学院生らの研究チームは、夏場に水が干上がった小さな河川(大河川の支流)で魚類群集を調査し、わずか4ヵ月後の冬期には推定10,000匹の魚類が戻ってきていることを明らかにしました。この中にはニジマスやウグイのように遊泳能力が高い魚類だけでなく、フクドジョウのような遊泳能力が低いと思われる魚も含まれていました。本成果は、一見して取るに足らない小さな支流が魚類の重要な越冬場所となっている可能性を示唆しており、今後の河川管理に重要な視点を提供するものです。この成果は、日本魚類学会の英文学術誌『Ichthyological Research』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
夏場干上がった川に,冬 1 万匹の魚が戻って来た!河川管理に重要な示唆(PDF)
2017-01-06
本学院地球圏科学専攻の飯塚芳徳助教(低温科学研究所)と北見工業大学、国立極地研究所の研究者を中心とする共同研究チームが、南極のドームふじで採集されたアイスコア最深部の物理化学的性質を解明しました。この成果は、米国科学雑誌「Journal of Geophysical Research: Earth Surface」に掲載され、当該号のカバーイメージにも採用されました。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
南極ドームふじアイスコア最深部の物理化学的性質を解明(PDF)
2017-01-06
ジャコウネズミは英語でHouse Shrew(人家にすむトガリネズミの意)と呼ばれ、人間活動の歴史と密接に関係していると考えられる小型の哺乳類です。今回、本学院生物圏科学専攻の大舘智志助教(低温科学研究所)、鈴木仁教授(地球環境科学研究院)ら、8カ国の研究者からなる国際共同研究チームは、日本から東アフリカ沿岸に至る広域から捕獲したジャコウネズミのミトコンドリアDNAの塩基配列を解析し、その遺伝的な関係性を明らかにしました。その結果、ジャコウネズミの分布は、これらの地域間での広範で複雑な人類の移動・交流の歴史を反映していることが示唆されました。この成果は、日本哺乳類学会の英文学術誌『Mammal Study』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
小さなジャコウネズミが明かした、インド洋〜東シナ海の沿岸域における広大で複雑な人間活動の軌跡(PDF)
2016-11-17
本研究院の小泉逸郎准教授および本学院の大学院生らの研究チームは、「世界の侵略的外来種ワースト 100」に選定されているニジマスが、冬期に小さな支流に集まることを発見しました。本成果は低コストでの効果的な外来種管理に繋がるだけでなく、生物が新しい環境に適応するメカニズムを理解することにも貢献します。この成果は、日本魚類学会の英文学術誌『Ichthyological Research』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
外来種ニジマスが小支流に越冬大集合?!個体群管理に有用か(PDF)
2016-10-19
本研究院の池田敬日本学術振興会特別研究員(現:国土交通省国土技術政策総合研究所研究官)、小泉逸郎准教授および本学院博士後期課程の内田健太さんらの研究チームは、ヒグマ、エゾシカ、キタキツネ、ユキウサギ、ホンドテン、アライグマ、タヌキ、エゾリスが明確な日周活動性を示すこと、一部の哺乳類は日周活動性を季節的に変化させることを、カメラトラップ調査による長期モニタリング(延べ 13,279 枚の撮影写真)により明らかにしました。本研究は、膨大なデータで北海道を代表する哺乳類の基礎生態を明らかにするとともに、野生動物管理にも大きく役立つ知見を提供しました。この成果は、米国科学誌『PLoS One』に掲載されています(オープンアクセス論文ですので、どなたでもご覧いただけます)。
詳細にいては、以下のプレスリリースをご覧ください。
ヒグマ、エゾシカ、キタキツネなど北海道に生息する哺乳類の活動時間を明らかに:赤外線カメラを用いた長期調査(PDF)
2016-10-13
本研究院の川口俊一准教授らの発明が平成28年度の北海道地方発明表彰で文部科学大臣賞を受賞しました。
受賞対象となった発明:
自己組織化法によるフッ素成膜(特許第5857145号)
詳細については、以下の公益社団法人発明協会ホームページをご覧ください。
http://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/H28/jusho_hokkaido/index.html
2016-10-04
本学院の宗原弘幸准教授(生物圏科学専攻水圏生物学コース)と大学院生らの研究チームが、北海道で「アブラコの合いの子」として知られている半クローン雑種のゲノム維持戦略を明らかにしました。この成果は、生態学と進化学の専門誌『Ecology and Evolution』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
アイナメ属半クローン雑種の正体はホストを乗り換えて永続するゲノムだった(PDF)
2016-09-20
生物圏科学専攻博士後期課程3年 辻 泰世さんが、9月7日〜10日に熊本県立大学で開催された日本ベントス学会・日本プランクトン学会合同大会において、口頭発表内容が高く評価され、日本プランクトン学会の学生優秀発表賞を受賞しました。
発表タイトルは、「汽水域生態系の多角的理解に向けた植物プランクトン・底生微細藻類・アマモ付着藻類の同時定量評価」です。
辻さんは、同学会の学生優秀発表賞を一昨年度、昨年度に引き続き3年連続受賞しています。
2016-08-19
環境科学院では昨年度より、在学中に行った優れた研究を学術論文として発表した在学生および元在学生を表彰する松野環境科学賞を創設しております。
厳正な選考の結果、第二回の受賞者は以下の4名に決定いたしました。
※授賞理由、論文概要などはリンク先をご覧ください。また、北大リポジトリHUSCAPへの登録があるものについては、論文全文もご覧いただけます。
Md. Tajuddin Sikder 氏
【対象論文と授賞理由(PDF)】
【論文概要】
【論文全文(HUSCAP)】
中田和輝 氏
【対象論文と授賞理由(PDF)】
【論文概要】
後藤寛貴 氏
【対象論文と授賞理由(PDF)】
【論文概要】
【論文全文(HUSCAP)】
福永直人 氏
【対象論文と授賞理由(PDF)】
【論文概要】
授賞式は2016年9月23日(金)14時より行われる学院ホームカミングデーにおいて執り行われます(詳細は同窓会ホームページ)。
参考:「松野環境科学賞の創設について」
2016-08-10
FM北海道の毎週日曜の番組『ほっかいどう宝島』で、8月の特集として「北海道大学」が紹介されます。先日(8月7日)の第1回では、本学山口学長が出演いたしました。
第3回となる8月21日(日)の放送では、本学院生物圏科学専攻の大原雅教授(地球環境科学研究院)がゲスト出演し、「エルムの森とオオバナノエンレイソウ」というテーマでトークを繰り広げます。その収録が先日行われました。
エルムはハルニレの木のことで、北大キャンパスには多くの並木が見られます。また、オオバナノエンレイソウは北海道大学の校章のモチーフであり、大原教授はエンレイソウの生態や保全の研究に取り組んでいます(大原研究室ホームページ)。
放送日:8月21日(日)18:30〜18:55
放送局:FM北海道(AIR-G’)
番組名:ほっかいどう宝島
テーマ:エルムの森とオオバナノエンレイソウ

(写真)収録中の大原教授
2016-08-05
本学の高等教育推進機構は、全学教育科目にかかる授業アンケートの総合評点上位の教員の中から「全学教育科目に係る授業アンケートにおけるエクセレント・ティーチャーズ」を選定しています。
今回、昨年度の授業に対するエクセレント・ティーチャーズ30名が発表され、本学院生物圏科学専攻の大原雅教授(地球環境科学研究院)が選出されました。大原教授は4年連続で選出されており、授業内容が学生から熱く支持されています。
選定対象となった授業
基礎科目(必修)「生物学?」大原雅教授
詳細については、以下の高等教育推進機構ホームページをご覧ください。
http://educate.academic.hokudai.ac.jp/center/enquete/enquete.htm
2016-07-29
平成28年7月29日付で、下記研究成果に関するプレスリリースを行いましたので、お知らせいたします。
シマフクロウとタンチョウを保全することで他の鳥類も守られる −アンブレラ種としての価値を市民科学で実証−(PDF)
2016-07-06
6月23日(木)、環境科学院と中国・厦門大学地球科学・技術学部との間で、コチュテル・プログラムに関する覚書の締結が行われました。昨年12月にコチュテル・プログラムの制度を北海道大学で導入して以来、本学全体で初めてのプログラム覚書締結となります。
コチュテル・プログラムとは、本学と外国の大学との間で協定等を締結し、博士後期課程の学生に対し、両大学の教員が計画的にそれぞれ原則1年以上の研究指導を行うプログラムのことで、その共同研究指導を受けた学生が本籍大学の修了要件を満たした場合、「博士課程修了に必要な研究指導は○○大学(注:連携大学名が入ります)と共同で実施したものである」との文言が記載された学位記が発行されます。
厦門大学は、1921年に華僑の実業家である陳嘉庚によって創設された華南地区を代表する名門大学であり、27学部、約4万人の学生を擁する総合大学です。本学と厦門大学は2010年11月25日に大学間交流協定を締結して以来、相互訪問や国際学会等に加え、北海道大学交流デーを通じて交流を深めてきました。
本覚書の締結により、海洋学、地球化学、生態学、気候学などの地球環境科学分野における、両大学の更なる教育・研究交流の推進が期待されます。
2016-07-06
2016年7月19日(火)午後2時からD101室にて、H28年度北海道大学招へい教員として滞在中のHongbin Liu教授(香港科技大学)による研究院アワー(EESセミナー)を開催致します(下記参照)。奮ってご参加願います。
鈴木光次(地球圏科学部門)
Prof. Hongbin Liu (Hong Kong University of Science and Technology) as a visiting professor of Hokkaido University is going to give a seminar at Rm. D101 from 2 pm, 19 July 2016 (see below). Your attendance would be greatly appreciated.
Koji Suzuki (Division of Earth System Science)
—
EES Seminar
Date: Tuesday, 19 July 2016, 14:00–15:30
Venue: Room D101
Speaker: Prof. Hongbin Liu (Hong Kong University of Science and Technology/Hokkaido University)
Title: Geographical niche differentiation of Synechococcus communities in the Western Pacific Marginal Seas
Chair: Koji Suzuki (Division of Earth System Science)
Abstract: Synechococcus, a cosmopolitan pico-unicellular cyanobacteria, are important primary producers in marine environments. They are both highly phylogenetically and phenotypically diverse. In order to draw a map about the abundance, pigment phenotypic diversity (revealed by cpe genes), and phylogenetic diversity (revealed by rpoC1 gene) of Synechococcus in the western Pacific Ocean and its marginal seas, we collected surface samples in eight cruises from 2009 to 2014, and studied both the phylogenetic types and phenotypes (pigment genetics) of Synechococcus using 454 pyrosequencing and clone library construction and sequencing methods. Synechococcus abundance in this vast area was also determined through flow cytometric analysis. Our results show that the abundance and genetic diversity of Synechococcus were the highest in the East China Sea. Clades I and II were the dominant lineages in the western Pacific Ocean surface waters. We reiterated the global distribution pattern of these two lineages. Clade I Synechococcus may contain six different subclades corresponding to cold and warm water ecotypes. Clade IV Synechococcus were rarely found in this study, though it often co-occurs with clade I. Clade III, VI, VII and S5.3 were also the major Synechococcus lineages in the warm waters of the western Pacific Ocean, but with relatively narrower niche than clade II. There is a latitudinal niche partitioning in Synechococcus pigment phenotypic compositions. Pigment type 3a was abundant in the ECS, while type 3c and/or type 3dB was largely dominant at the SCS. Most strikingly, chromatic acclimaters of the 3dA type constituted almost the sole pigment type in the western subarctic Pacific and the Bering Sea. Our results also showed that Synechococcus communities with a similar phylogenetic composition could have distinct pigment phenotypic compositions, suggesting that the PE-encoding genes have undergone multiple lateral transfers between Synechococcus lineages during the evolution of this genus. The GC and GC3 contents of cpe genes of Synechococcus communities in the ECS are higher than those in other geographic locations, indicating that the pigment genes in the ECS suffered the least pressure. Our results show a geographical differentiation of Synechococcus phylogenetic and pigment phenotypic compositions in the western Pacific Ocean, which can be explained by the adaptation of different clades/types to environmental conditions.
2016-06-20
本学院の池田幸資さん(環境起学専攻博士後期課程)、根岸淳二郎准教授らの研究チームが、河川の水に含まれている生物由来のDNA(環境DNA)を分析することにより、絶滅が危惧されているニホンザリガニの生息の有無を把握することに成功しました。この成果は、保全遺伝学に関する科学雑誌『Conservation Genetics Resources』に掲載されています。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
環境DNA解析により水を汲むだけで絶滅危惧種ニホンザリガニの生息を把握−(PDF)
なお、この成果は日本経済新聞や朝日新聞デジタルでも取り上げられています。
日本経済新聞「希少ニホンザリガニの生息、水中のDNA分析で確認 北大など」
朝日新聞デジタル「ニホンザリガニ、川の水で生息分かる 環境DNAで確認」
2016-05-26
本学院副学院長の大原雅教授が4月9日〜11日の日程で韓国ソウルを訪問し、北大を卒業した韓国の方の同窓会「韓国北海道大学ヨルリョンチョ会」発足記念式典で講演を行いました。また、今回の式典の主催として、北大ソウルオフィス所長でもある本学院生物圏科学専攻の車柱榮准教授にもご尽力をいただきました。
 4月9日(土)、韓国ソウル市内のプレジデントホテルにおいて、「韓国北海道大学ヨルリョンチョ会発足式及び北海道大学アンバサダー・パートナー委嘱式」が行われました。上田理事・副学長を含む大学関係者のほか卒業生あわせて約40名が出席し、午後6時より記念式典が遂行されました。
4月9日(土)、韓国ソウル市内のプレジデントホテルにおいて、「韓国北海道大学ヨルリョンチョ会発足式及び北海道大学アンバサダー・パートナー委嘱式」が行われました。上田理事・副学長を含む大学関係者のほか卒業生あわせて約40名が出席し、午後6時より記念式典が遂行されました。
 記念講演会では大原教授による「北大の花、オオバナノエンレイソウの生活史」と題した講演がありました。ヨルリョンチョとは、韓国語で「エンレイソウ」という意味です。講演ではオオバナノエンレイソウが長く生き、多くの花が集まって開花する植物であることを紹介し、「ヨルリョンチョ会」がこのエンレイソウのように多くの卒業生が集い、長く続く会となることを願いたいと話されました。続く懇親会も盛大に行われ、素晴らしい式典となりました。
記念講演会では大原教授による「北大の花、オオバナノエンレイソウの生活史」と題した講演がありました。ヨルリョンチョとは、韓国語で「エンレイソウ」という意味です。講演ではオオバナノエンレイソウが長く生き、多くの花が集まって開花する植物であることを紹介し、「ヨルリョンチョ会」がこのエンレイソウのように多くの卒業生が集い、長く続く会となることを願いたいと話されました。続く懇親会も盛大に行われ、素晴らしい式典となりました。
 翌日には北大ソウルオフィスを訪問し、事務所内を見学させていただきました。北大では海外オフィスをソウル(韓国)、ヘルシンキ(フィンランド)、ルサカ(ザンビア)の計3か所に構えています。
翌日には北大ソウルオフィスを訪問し、事務所内を見学させていただきました。北大では海外オフィスをソウル(韓国)、ヘルシンキ(フィンランド)、ルサカ(ザンビア)の計3か所に構えています。


2016-03-28
日本生態学会が生態学に大きな貢献をしている若手会員の研究業績を表彰する第20回宮地賞を、本学院を修了した高橋一男博士(岡山大学)と松田一希博士(京都大学)が、2016年3月23日に同学会仙台大会において受賞されました。
おめでとうございます。
なお、お二人を加え、本学院の同賞受賞者は8名を数えます。
過去の受賞者:工藤岳(第1回; A,S)・三浦徹(第7回; S)・相場慎一郎(第10回; A)・岸田治(第13回; S)・内海俊介(第16回; S)・中村誠宏(第17回; S)(S, 教員;A, 修了者)
日本生態学会ホームページ
https://www.esj.ne.jp/esj/award/miyadi/list.html
















 4月9日(土)、韓国ソウル市内のプレジデントホテルにおいて、「韓国北海道大学ヨルリョンチョ会発足式及び北海道大学アンバサダー・パートナー委嘱式」が行われました。上田理事・副学長を含む大学関係者のほか卒業生あわせて約40名が出席し、午後6時より記念式典が遂行されました。
4月9日(土)、韓国ソウル市内のプレジデントホテルにおいて、「韓国北海道大学ヨルリョンチョ会発足式及び北海道大学アンバサダー・パートナー委嘱式」が行われました。上田理事・副学長を含む大学関係者のほか卒業生あわせて約40名が出席し、午後6時より記念式典が遂行されました。 記念講演会では大原教授による「北大の花、オオバナノエンレイソウの生活史」と題した講演がありました。ヨルリョンチョとは、韓国語で「エンレイソウ」という意味です。講演ではオオバナノエンレイソウが長く生き、多くの花が集まって開花する植物であることを紹介し、「ヨルリョンチョ会」がこのエンレイソウのように多くの卒業生が集い、長く続く会となることを願いたいと話されました。続く懇親会も盛大に行われ、素晴らしい式典となりました。
記念講演会では大原教授による「北大の花、オオバナノエンレイソウの生活史」と題した講演がありました。ヨルリョンチョとは、韓国語で「エンレイソウ」という意味です。講演ではオオバナノエンレイソウが長く生き、多くの花が集まって開花する植物であることを紹介し、「ヨルリョンチョ会」がこのエンレイソウのように多くの卒業生が集い、長く続く会となることを願いたいと話されました。続く懇親会も盛大に行われ、素晴らしい式典となりました。 翌日には北大ソウルオフィスを訪問し、事務所内を見学させていただきました。北大では海外オフィスをソウル(韓国)、ヘルシンキ(フィンランド)、ルサカ(ザンビア)の計3か所に構えています。
翌日には北大ソウルオフィスを訪問し、事務所内を見学させていただきました。北大では海外オフィスをソウル(韓国)、ヘルシンキ(フィンランド)、ルサカ(ザンビア)の計3か所に構えています。