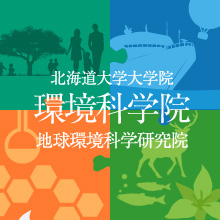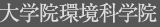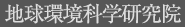【プレスリリース】森の分断・消失が希少種クロビイタヤに及ぼす影響
2018-03-09本学院生物圏科学専攻の日浦勉教授(北方生物圏フィールド科学センター)は、筑波大学の佐伯いく代准教授、平尾章助教、田中健太准教授らとともに、カエデの一種で絶滅が危惧されるクロビイタヤについて、生育地周辺の森林の状況と、遺伝的な変異のパターンとの関係(景観遺伝学)の調査を行いました。
その結果、クロビイタヤは生育地周辺の森林が消失し、連続性が途絶えている場所ほど、他の地域の個体との遺伝的な違いが大きくなる傾向があることがわかりました。これは、森林が消失すると、花粉を媒介する昆虫が少なくなり、個体間での遺伝的な交流(以下、遺伝子流動)が起こりづらくなるためと考えられます。他地域からの遺伝子流動が途絶えると、遺伝的に近縁な個体どうしが交配しやすくなるため、種の存続にマイナスの影響を与えるおそれがあります。
クロビイタヤは、宮部金吾博士(北海道大学植物園初代園長)によって北海道で発見され、北海道大学植物園のシンボルマークにも使われています。本種は河川の氾濫原にある湿地などに生育しますが、こうした場所は人にとっても利用しやすく、農地や宅地として開発が進められてきました。森と河川の豊かな我が国では本来、もっと多くの場所でクロビイタヤを見ることができたことでしょう。本研究では、景観遺伝学の解析手法を用い、森林の消失によって遺伝子流動が弱くなっている地域を推定することができました。そのような場所を中心に森林の保護や復元を進めていくこと、また遺伝子流動に影響を与えると予測される1km2以上の森林開発をできるだけ行わないことなどが、本論文では提案されています。
本研究成果は、2018年2月28日「Biological Conservation」電子版で公開されました。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
森の分断・消失が希少種に及ぼす影響〜絶滅危惧種クロビイタヤの景観遺伝学的研究からの提言〜(PDF)