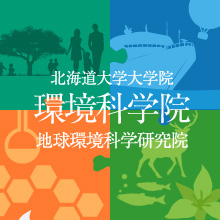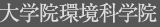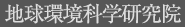プレスリリース
2023-06-12
本学院地球圏科学専攻生物地球化学コースの飯塚睦氏(博士後期課程)、関宰准教授(低温科学研究所)、入野智久准教授(地球環境科学研究院)、山本正伸教授(地球環境科学研究院)、富山大学の堀川恵司教授、国立極地研究所菅沼悠介准教授、産業技術総合研究所の板木拓也研究グループ長、高知大学の池原実教授、ロンドン大学のデビット・J・ウィルソン博士、インペリアルカレッジのティナ・ファンデフリアート教授らの研究グループは、東南極沖の海底堆積物コアの解析から、地球表層が温暖化していた最終間氷期(13-11.5万年前)において、東南極の一部の氷床が後退し、当時の海面上昇に大きく寄与したことを解明しました。
近年の温暖化で、西南極氷床の融解は加速しており、今後これが数メートル規模の海面上昇につながる可能性があります。一方、東南極氷床は西南極氷床に比べて、温暖化に対して安定的だと考えられていました。しかし、近年になり東南極氷床の一部で融解が観測され始めたため、今後の温暖化により、東南極氷床の著しい融解が起きるかどうかに注目が集まっています。
そこで、本研究では、過去の温暖な時代(最終間氷期)の東南極氷床の変動を復元し、将来の温暖化で東南極氷床が縮小する可能性があるのかを検証しました。その結果、13-11.5万年前の最終間氷期に、東南極氷床の著しい縮小が2回発生していたことが明らかになりました。これらの氷床の縮小は、海面を約0.8m上昇させるほどの規模であったと見積もられました。よって、地球温暖化が持続した場合、西南極氷床だけでなく東南極氷床の一部も融解し、より大きな海面上昇が引き起こされる可能性があることが示されました。
本研究成果は、2023年4月18日(火)公開のNature Communications誌に以下のように掲載されています。
論文名:Multiple episodes of ice loss from the Wilkes Subglacial Basin during the Last Interglacial(最終間氷期におけるウィルクス海盆からの複数の氷床縮小エピソード)
詳細(PDF)
2023-03-15
本研究院の甲山隆司名誉教授は、東京大学大学院農学生命学研究科・生圏システム学専攻の甲山哲生助教をはじめとするワーゲニンゲン大学・群馬大学など内外の共同研究者と共に、インドネシアやマレーシアの熱帯林から台湾や沖縄の亜熱帯林、そして鹿児島の暖温帯林から北海道の亜寒帯林に至る 60 の森林の継続調査のデータを用いた解析から、より温暖な森林ほど、相対的な(炭素量当たりの)年間炭素生産量が高い低木性樹種の比率が高くなることによって、同じ樹木炭素量を持つ森林の炭素生産量がより高くなることを明らかにしました。
従来の研究では、気温と樹木種多様性、そして森林生産の間の相関関係を示すに留まっていましたが、樹木種レベルの生産に注目した本研究では、これらの間の結びつきをはじめて機能的に解明しました。自然林の持続的管理では、炭素量が大きく、生産量も大きい高木種の保全が強調されてきましたが、本研究によって、低木種を含む樹木種多様性の保全が森林生産量の維持にとって重要であることが明らかにされました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
なぜ温暖な森林は生産量が大きいのか? ――樹木群集の炭素量分布が森林の生産量に貢献する――(PDF)
2023-03-03
本学院生物圏科学専攻博士後期課程 2 年の長谷川稜太氏と同生物圏科学専攻の小泉逸郎准教授(地球環境科学研究院)は、口に寄生する甲殻類(サルミンコーラ)が、宿主である淡水魚イワナの釣られやすさに影響することを明らかにしました。特に、イワナの肥満度(コンディション)に応じて、寄生された時の釣られやすさが変化することを発見しました。
魚釣りは世界中で広く行われている経済・レジャー活動です。釣り人はより大きく、美しく、美味しい魚が釣れると満足度が高まります。一方、釣った魚の体表や口の中、あるいはお腹の中から寄生虫が出てくることがまれにあり、このような寄生虫は釣り人の満足度を低下させます。しかし、寄生虫に感染された魚が釣られやすくなるかどうかは、これまで全く注目されてきませんでした。一般に、寄生虫は宿主から栄養を奪うため、宿主の活動性が低下し感染魚は釣られづらくなると予測できます。特に本研究の対象種は口腔内に寄生するため、宿主魚類の採餌の邪魔になるとも考えられます。
そこで研究チームは、サルミンコーラに寄生されたイワナが実際に釣られづらくなるかどうかを調べました。調査の結果、寄生されたイワナの釣られやすさは魚のコンディションによって異なり、痩せている感染イワナは釣られづらくなり、逆に太っている感染イワナは釣られやすくなることが明らかとなりました。前者は餌を追う体力がなく活動性が低下するため、釣られなくなったと考えられます。一方、後者は寄生虫の感染により消費するエネルギーを補償するために積極的に餌を食べるようになった可能性があります。本研究の成果は、寄生と魚の釣られやすさの関係を科学的に示しただけでなく、寄生虫が釣り人の満足度や釣魚の食料消費にも影響しうることを示唆しています。
なお、本研究成果は、2023 年 2 月 21 日(火)公開の The Science of Nature 誌にオンライン掲載されました
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
寄生虫に感染した魚は釣られなくなる?~渓流河川のイワナで検証~(PDF)
2023-03-03
本学院地球圏科学専攻の山下洋平准教授(地球環境科学研究院)、西岡 純教授(低温科学研究所)は、オホーツク海とベーリング海の陸棚堆積物に由来する鉄分の主な形態が、中層水循環に伴い北太平洋へと長距離輸送される間に変化することを解明しました。
鉄分は海洋の光合成生物に必須な栄養素ですが、海水に溶けにくい性質を持ちます。北太平洋の亜寒帯域は鉄分が不足し、光合成生物の増殖が抑制されることが知られていますが、オホーツク海の堆積物から長距離輸送される鉄分がその抑制を緩和させていることが分かってきました。一方、海水に溶けにくい鉄分が、どのように輸送されているのかは不明で、その将来変化の予測は困難でした。
そこで研究グループは、極東ロシア海洋気象学研究所との国際共同観測などを実施して、オホーツク海とベーリング海、北太平洋の広範な海域における鉄分の濃度と鉄分を溶かす機能を有する腐植物質の濃度の分布を世界で初めて同時に観測し、両者の比較から鉄分の形態を評価しました。その結果、堆積物から海水へと移行した直後の鉄分は、粒子状やコロイド状が主な形態であるのに対し、中層水循環により長距離輸送され、亜熱帯循環域やアラスカ循環域に到達した鉄分は腐植物質との相互作用により溶けた状態であることが明らかになりました。
オホーツク海の堆積物から海水へと供給される鉄分の量は、オホーツク海の海氷生成と関係がある事が考えられています。オホーツク海の海氷生成量が減少すると、堆積物から海水へ供給される鉄分の量や形態が変化することが考えられるため、本研究成果は北太平洋への鉄分供給の将来変化を予測する上で重要な知見となります。
なお、本研究成果は、2023 年 2 月 22 日(水)公開の Journal of Geophysical ResearchBiogeosciences 誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
縁辺海から北太平洋に輸送される栄養素~中層水による輸送中に鉄分の主な形態が変化する事を発見~(PDF)
2023-02-27
オホーツク海は北半球で最も南まで海氷(流氷)が到達する海域です。冬季から春先にかけ、世界自然遺産・知床をはじめとした北海道の沿岸には流氷が接岸しますが、オホーツク海の海氷は年によって多い年と少ない年があります。その変動理由の解明は、地球温暖化の進行に伴う海氷の減少傾向を理解する上でも、流氷観光など社会経済活動への影響を考える上でも、重要な研究課題です。
本学院地球圏科学専攻の三寺史夫教授(低温科学研究所)は、筑波大学生命環境系の植田宏昭教授と共同で、シベリア高気圧、アリューシャン低気圧、太平洋などで構成される「環オホーツク気候システム」の観点から、長期の観測データ(全球大気データや人工衛星データ)に基づき、オホーツク海全域の海氷の発生量が年ごとに変動するメカニズムを解析しました。
その結果、海氷が平年よりも多い年は、アリューシャン低気圧が北太平洋の全域で強まっていることが分かりました。これに伴い、シベリアからの北西風(寒気流)がオホーツク海上で強まり、寒気の蓄積量も多くなっていました。一方、熱帯域との関係に注目すると、海氷が多い年はエルニーニョ的な海水温分布になっており、アリューシャン低気圧の強化とも連動していることが確認されました。これに対し、海氷が少ない年の熱帯域では、ラニーニャ的な海水温分布になっていました。
さらに、海氷が多い年は、海氷の面積が増え始めてから数カ月後に、アリューシャン低気圧が強まることが分かりました。アリューシャン低気圧の強化は、ユーラシア大陸からの寒気の流入を促進します。このため、寒気蓄積→海氷増加→アリューシャン低気圧の強化という連鎖的な季節進行は、海氷の維持につながる正のフィードバック関係にあることが示唆されます。
本研究が示した「環オホーツク気候システム」の観点から海氷の変動機構のメカニズム解明をさらに進めることで、季節予報の精度向上や温暖化予測の理解が深まることが期待されます。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
高緯度と熱帯からの遠隔影響がオホーツク海氷の年々変動を引き起こす~「環オホーツク気候システム」の端緒を開く~(PDF)
2023-02-14
本学院地球圏科学専攻の山下洋平准教授(地球環境科学研究院)と、同地球圏科学専攻博士前期課程(研究当時)の森雄太郎氏は、東京大学大気海洋研究所の小川浩史教授と共同で、東太平洋海膨における深海熱水域から熱成炭素である溶存黒色炭素が供給されていることを明らかにしました。
森林火災や化石燃料燃焼に伴い、不完全燃焼産物である煤や炭などの熱成炭素が生成されます。熱成炭素の多くは、環境微生物による分解を受けにくく、土壌や海洋に蓄積されやすいため、地球表層の炭素循環から二酸化炭素を隔離する機能を持つと考えられています。熱成炭素の一部は、水と共に移動可能な形態である溶存黒色炭素に変質し、河川や大気を経由して海洋へと輸送されることが知られています。海洋中では、溶存黒色炭素は太陽光により分解もしくは沈降粒子に吸着され、除去されます。しかし、海洋への溶存黒色炭素の年間の供給量はその除去量よりも小さく、海洋には溶存黒色炭素のミッシングソース(未知の供給源)がある事が指摘されていました。そこで研究グループは、学術研究船白鳳丸により東太平洋を中心とした観測を行い、高温かつ高圧である深海熱水域で生成された溶存黒色炭素が深海に供給されていることを世界で初めて明らかにしました。
海洋に存在する難分解な溶存有機物の総量は大気中の二酸化炭素の総量に匹敵しますが、その起源や生成メカニズムはよく分かっておらず、炭素循環におけるブラックボックスとされています。本研究成果は、難分解な溶存有機物である溶存黒色炭素が深海熱水域から供給されている事を明示しており、炭素循環における溶存有機物の役割を理解する上でも貴重な知見となります。
なお、本研究成果は 2023 年 2 月 11 日(土)公開の Science Advances 誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
深海温泉を源とする微生物に分解されない有機物~深海熱水から溶存黒色炭素が供給されていることを発見~(PDF)
2023-02-09
本学院環境起学専攻の先崎理之助教(地球環境科学研究院)は、ノースカロライナ⼤学グリーンズボロ校の照井 慧助教、北海道⽴総合研究機構の⼘部浩⼀研究主幹、国⽴極地研究所(当時)の⻄沢⽂吾⽒と共同で、⿂のふ化放流は多くの場合で放流対象種を増やす効果はなく、その種を含む⽣物群集を減らすことを明らかにしました。
飼育下で繁殖させた在来種を野外に放す試みは、野外個体群の増強を⽬的として様々な動植物で⾏われています。特に、漁業対象種のふ化放流は、国内外に広く普及しています。⼀⽅、こうした放流では⾃然界には⽣じえない規模の⼤量の稚⿂を放つため、⽣態系のバランスを損ね、放流対象種を含む⿂類群集全体に⻑期的な悪影響を及ぼす可能性があることが懸念されています。
そこで研究チームは、シミュレーションによる理論分析と全道の保護⽔⾯河川における過去 21 年の⿂類群集データによる実証分析を⾏い、放流が河川の⿂類群集に与える影響を検証しました。実証分析で対象とした保護⽔⾯河川には、放流が⾏われていない河川とサクラマスの放流が様々な規模で⾏われている河川が含まれます。これらの分析の結果、放流は種内・種間競争の激化を促すことで、放流対象種の⾃然繁殖を抑制し、さらに他種を排除する作⽤を持つため、⻑期的に⿂類群集全体の種数や密度を低下させることが明らかになりました。本研究結果は、持続可能な⿂類の資源管理や⽣物多様性保全に対する放流の効果は限定的であり、⽣息環境の復元などの別の抜本的対策が求められることを⽰しています。
なお、本研究成果は、2023 年 2 ⽉ 7 ⽇(⽔)公開の Proceedings of the National Academy ofSciences 誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
放流しても⿂は増えない 〜放流は河川の⿂類群集に⻑期的な悪影響をもたらすことを解明〜(PDF)
2023-02-06
2021 年にユネスコ世界自然遺産に登録された奄美群島は、その植物相の豊かさや特異性でもよく知られています。今後、世界自然遺産を効果的に管理するためには、植物相の特徴を定量的に評価し、その多様性に影響する要因を明らかにすることが必要です。国立環境研究所、鹿児島大学、北海道大学、琉球大学、九州オープンユニバーシティの研究グループは、奄美群島、沖縄島北部、南九州における計 16 地点の全維管束植物を対象とした植物群落の比較から、奄美群島の植物相の特徴を明らかにしました。本学院からは、生物圏科学専攻の相場慎一郎教授(地球環境科学研究院)が参加しています。具体的には、奄美群島の植物相は、周辺地域と比べると常緑広葉樹やシダ植物が豊富で、熱帯・亜熱帯で多様化している分類群が多くみられるという特徴を持っていました。加えて、草本層は絶滅危惧種・固有種の割合が高く、地域の種多様性を特徴づけるものでした。また、奄美群島の植物相は地史的な要因に加え、気温などの環境要因にも規定されていることが明らかになりました。
本研究は、奄美群島の植物多様性を、草本層を含めて定量的に評価した初めての研究です。そして、今後の世界自然遺産モニタリングの起点データを提供しています。本成果は、2023 年 1 月 11 日付で Wiley から刊行される生態学分野の学術誌『Ecological Research』に掲載されました。また、得られたデータは 2022 年 7 月 19 日付『Ecological Research』に掲載され、公開されています
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
世界自然遺産・奄美群島の多様性は足元から!全維管束植物のモニタリング起点データを提供(PDF)
2023-02-03
本研究院の鈴木 仁名誉教授らの研究グループ、並びに元大阪市立大学の原田正史氏、島根自然保護協会の野津 大氏は、島根県隠岐の島町で 2 匹のアズマモグラの捕獲に成功しました。
アズマモグラは地下性のモグラ科哺乳類で、日本列島にのみ生息する固有種です。青森県を北限に、主に東日本に広く生息していますが、かつては日本全国に生息していたとされています。現在、アズマモグラが西日本に生息していない原因は、今から 100 万年以上前、日本列島が朝鮮半島と陸続きであった時代に大陸から移入してきた近縁種であるコウベモグラが西日本に生息地を広げ、アズマモグラを東方に追いやったからではないかと推測されています。現在に至るまで両種は競合関係にあり、その生息域の境界は変化し続けています。通常アズマモグラに比べて体の大きなコウベモグラは優位ですが、土壌の質や地形によってはコウベモグラの侵攻を免れた地域もあり、中国地方や四国、紀伊半島などがアズマモグラの生息する飛び地として西日本に残っています。
2021 年 11 月、島根県隠岐諸島で行われた小型哺乳類の採集調査で体の小さい 2 匹のモグラが捕獲されました。詳細な観察の結果、2 匹はこれまで隠岐諸島に生息が確認されていなかったアズマモグラであると判明しました。本報告はモグラがどのように日本に広まって現在の生息地に収まったかを知るうえで重要な知見となります。また、アズマモグラの生息する未発見の飛び地がまだ存在する可能性も示唆しています。
なお、本研究成果は、日本時間 2023 年 1 月 31 日(火)公開の「哺乳類科学」誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
未確認のアズマモグラの生息地を発見~西日本に新たな飛び地があることが判明~(PDF)
2023-01-30
本研究院客員教員の川西亮太准教授(北海道大学大学院地球環境科学研究院特任助教(当時)、同大総合博物館資料部研究員)(北海道教育大学釧路校(現在))、北海道大学大学力強化推進本部の佐藤崇 URA(京都大学総合博物館、農学研究科研究員(当時))、近畿大学農学部の宮崎佑介准教授(白梅学園短期大学准教授(当時))の研究グループは、伊豆諸島ベヨネース列岩および八丈島で採集されたダツ科の魚類(ヒメダツ)のエラから未知のウオノエ類を発見し、新種 Mothocya kaorui(標準和名リュウノロクブンギ)として記載しました。
ウオノエ科はダイオウグソクムシやダンゴムシなどと同じく等脚目に属する甲殻類ですが、魚の口やエラ、体表などに寄生して暮らしており、「かわいい」寄生虫としても人気があります。今回発見されたリュウノロクブンギは、「六分儀」の由来ともなった黒色で三角状の腹尾節や、節が融合した小触角など、ウオノエ科全体を見渡しても非常にユニークな形態的特徴を持っていました。一方で、リュウノロクブンギのミトコンドリア DNA を調べた結果、釣り人に馴染み深いサヨリのエラに寄生するサヨリヤドリムシと同じエラヌシ属Mothocya に属することがわかりました。どのような進化の歴史を経て、リュウノロクブンギが誕生したのかはまだ明らかではありませんが、大陸から遠く離れた離島環境が独自の形態を生み出したのかもしれません。
今回の発見は、過去に採集されて博物館に収蔵されていた魚類標本が起点となりました。宿主の自然史標本は、その寄生生物の多様性を解明する上でも貴重な資料であり、後世に引き継いでいくことが日本の生物多様性を解明していく上でも重要であると考えられます。
本研究成果は、日本時間 2023 年 1 月 25 日(水)に Systematic Parasitology 誌(寄生虫分類学の国際誌)にてオンライン公開されました
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
絶海の岩礁ベヨネース列岩から新種のウオノエ科甲殻類を発見〜龍のような宿主で暮らす「六分儀」〜(PDF)
2023-01-26
本大学院地球圏科学専攻の西岡 純教授(低温科学研究所)、鈴木光次教授(地球環境科学研究院)、香港科学技術大学のカイリン リュウ研究員及びホンビン リュウ教授らの研究グループは、親潮域上流の東カムチャツカ海流域から西部ベーリング海の栄養物質循環及びプランクトン生態系の構造と制御機構を、極東ロシア海洋気象学研究所との国際共同観測から世界で初めて明らかにしました。
これまで、日本の水産資源の多くを支える北太平洋亜寒帯域は、オホーツク海の影響を強く受けていることが知られていました。これに加え、北太平洋亜寒帯域の水塊形成は、東カムチャツカ海流とさらに上流に位置する西部ベーリング海の影響を受けていますが、これらの海域は観測データの圧倒的不足のため、栄養物質循環とプランクトン生態系の構造や制御機構は不明のままでした。
本研究では、東カムチャツカ海流とその上流に位置する西部ベーリング海及びアナディル湾の観測を実施し、これら未知の海域の栄養物質循環と、植物プランクトンの成長速度と微小動物プランクトンの捕食速度の空間パターンを明らかにしました。プランクトン生態系構造のデータを解析した結果、カムチャツカ半島沖から西部ベーリング海の植物プランクトンの増殖は、海洋循環で供給される窒素や河川などを通じて供給される鉄分などの栄養物質の利用可能性と、水温の影響を受ける微小動物プランクトンの捕食の有無によって決定されることを見出しました。これらの知見から、東カムチャツカ海流と西部ベーリング海を含む北太平洋亜寒帯域では、海洋温暖化に対するプランクトンの増殖応答が海水中の栄養条件の違いにより異なることが予想されました。
なお、本研究成果は、2023 年 1 月 16 日(月)公開の Limnology and Oceanography 誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
未知の海域である西部ベーリング海と東カムチャツカ海流上流のプランクトン生態系構造の制御要因を解明~気候変動に伴う北太平洋プランクトン生態系変化の将来予測に貢献~(PDF)
2023-01-25
本学院地球圏科学専攻の的場澄人助教、飯塚芳徳准教授ら(いずれも低温科学研究所)の研究グループは、グリーンランドで採取されたアイスコア中の化学成分の分析を行い、2002 年以降、夏に海洋プランクトンの増殖によって海洋から大気へ放出される硫黄化合物(メタンスルホン酸)の濃度が、それ以前と比べて 3〜6 倍増加していることを検出し、海氷の融解時期が早期化したことがその要因であることを示しました。
大気中に浮遊する不純物(エアロゾル)の組成や濃度は、それを採取・分析する必要がありますが、長期間のデータは非常に少なく、特に北極域では殆どありません。氷床には、大気中のエアロゾルを含む雪が連続的に降り積もっています。氷床を表面から深部に向かって円柱状にくり抜いて採取されるアイスコアに含まれる化学成分は、大気中のエアロゾルの連続的な変化を反映し、長期間のエアロゾルの変化を復元することができます。
アイスコア中の夏のメタンスルホン酸濃度は、2002 年から増加し始めました。それと連動してグリーンランド東部沖の海氷が融解する時期が約 1 ヶ月早くなり、夏に植物プランクトンの増殖が見られることが、人工衛星データとの比較から分かりました。温暖化が引き起こす海氷融解の早期化は、海洋表層の成層化、海水中に届く太陽光の増加、海氷に付着している藻類(アイスアルジー)の再配布などを生じ、植物プラントンの増殖を促進するプロセスが提案されていましたが、本結果は、夏の海洋プランクトンの増殖による海洋から大気への硫黄化合物の放出量が実際に増加している観測的証拠を初めて示しました。
大気中の硫黄化合物は雲の形成に重要であり、地球の気温をコントロールする放射収支に大きく影響します。本研究の成果は、地球温暖化のメカニズムを理解する上で重要なプロセスを示すもので、将来予測の精度向上に寄与することが期待されます。
なお本研究成果は、2022 年 12 月 26 日(月)公開の Communications Earth & Environment 誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
北極の海氷融解の早期化が夏の植物プランクトンを増殖~夏に海洋プランクトンが大気へ放出するエアロゾルの増加をアイスコアから検出~(PDF)
2023-01-05
本学院生物圏科学専攻の小泉逸郎准教授(地球環境科学研究院)、摂南大学(学長:荻田喜代一)農学部の増田太郎准教授、京都大学大学院農学研究科の下野嘉子准教授、岐阜県水産研究所の岸大弼専門研究員の共同研究グループは、ゲノム網羅的(ゲノムワイド)な多型解析により、本州の河川源流に棲息するイワナ亜種の判別と分布境界の決定に成功しました。各亜種の生息域は分水嶺を挟んで隣接しており、分布境界では地形変化による亜種間の分布拡大のせめぎ合いが起こっていることを示しました。本研究は、在来生物種の分布から地形形成史を検証する手段を提案します。
悠久の時の流れを象徴する川の流路は時代とともに大きく変化してきました。特に、動的な地質を持つ日本列島の河川源流付近では、地形の浸食で河川の流域のある一部分を隣接する河川が奪う「河川争奪」と呼ばれる地理的事象により、河川の逆流など流路再編が頻繁に繰り返されて現在に至ります。今回、河川争奪の指標生物として、本州では河川源流部にのみ棲息するイワナに着目し、イワナゲノムの個体間の違いを詳細に調べました。その結果、本州のイワナを、日本海型(ニッコウイワナ)、太平洋型(ヤマトイワナ)、琵琶湖型という遺伝的に異なる3グループに分類することに成功しました。
このように、本研究で採用した調査手法により、魚類在来個体群の自然分布から地形形成史を紐解くことができる可能性が示されました。
なお、本研究の成果は、生物地理学に関する英国の学術誌「Journal of Biogeography」に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
イワナゲノムの違いで地形進化を解明 日本海型・太平洋型・琵琶湖型に3分類 「河川争奪」で分布に変化(PDF)
2022-12-22
昭和電工株式会社(社長:髙橋秀仁 以下、昭和電工)と日本製鉄株式会社(社長:橋本英二 以下、日本製鉄)、および6つの国立大学(大分大学、大阪大学、京都大学、千葉大学、名古屋大学、北海道大学)が共同して進める事業(以下、本事業)が、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、「NEDO」)の「グリーンイノベーション基金事業」に採択され、10月より技術開発を本格始動しました。本学院からは、環境起学専攻の野呂真一郎教授(地球環境科学研究院)が参加しています。本事業は、両社および大学が持つ技術を使って、低圧・低濃度(大気圧・CO2濃度10%以下)の排出ガスから効率的にCO2を分離・回収するもので、1トンあたり2,000円台という画期的な低コスト実現をターゲットに、2030年代後半の社会実装を目標にしています。さらに昭和電工は、回収したCO2を化学品の原料として再利用し販売するまでのビジネスモデルの構築を目指します。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
昭和電工と日本製鉄、6 つの国立大学と連携し、 工場排出ガスに含まれる低濃度 CO2の分離回収技術開発を本格始動 低コストで省エネルギー型の CO2分離回収技術の早期社会実装により カーボンニュートラル社会への貢献を目指す(PDF)
2022-12-09
本学院地球圏科学専攻の豊田威信助教、西岡 純教授、三寺史夫教授(いずれも低温科学研究所)、同大学北方生物圏フィールド科学センターの野村大樹准教授らの研究グループは、オホーツク海南部(北緯46度以南)の海氷域の海氷面積・氷厚・海氷体積量の年々変動の特性を解明しました。
オホーツク海南部は、沿岸結氷を除けば世界で最も低緯度に位置する海氷域として知られ、その海氷域の概況は主に防災の観点から、航空機や衛星で以前より観測が行われてきました。しかし、その面積や氷厚の経年変動はこれまで統計的に十分には解析されてきませんでした。特に、氷厚の長期間に渡る体系的な観測がなかったため、海氷体積量の経年変動は全く知られていませんでした。
本研究は現場で得られた氷厚などのデータを衛星データと組み合わせて解析を行い、オホーツク海南部海域の海氷面積は、その北部・中部とは顕著に異なる変動特性を持つこと、海氷体積量の年々変動は大きく熱力学的な結氷条件よりも力学的な氷盤の積み重なりが重要であること、顕著な氷盤の積み重なりは現在多くの気候モデルで用いられている海氷レオロジーの理論でおおよそ説明が可能なことが分かりました。これらの結果は他の季節海氷域の数値モデル化にも適用可能と考えられます。
なお、本研究成果は、2022年12月2日(金)公開のJournal of Geophysical Research: Oceans誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
オホーツク海南部冬期の海氷体積量の年々変動を解明~気候変動に伴うオホーツク海海氷の変動予測への貢献に期待~(PDF)
2022-12-09
本学院生物圏科学専攻修士課程(研究当時)の長谷川貴章氏と同生物圏科学専攻の仲岡雅裕教授(北方生物圏フィールド科学センター)、東京農工大学の高田秀重教授、水川薫子助教、ヨー ビーギョク研究員を中心とした研究グループは、魚類がマイクロプラスチックの摂取を通じて、プラスチック製品に含まれる添加剤を筋肉や肝臓などの体組織に取り込み蓄積することを、世界で初めて実証しました。
添加剤は、プラスチックが細分化されると周辺環境に溶出しやすくなります。魚類はマイクロプラスチックを海水中及び餌生物から取り込むため、その2つの経路を介して添加剤が体組織に移行・蓄積する可能性が指摘されていました。そこで、肉食性魚類シモフリカジカとその餌生物であるイサザアミ類を用いて、魚類のマイクロプラスチック摂取による添加剤の組織への移行について、両経路の相対的重要性を検証しました。
その結果、添加剤入りマイクロプラスチックを含む海水中で魚を飼育した場合及びマイクロプラスチックを含む餌生物を魚に摂食させた場合に、魚の筋肉や肝臓に添加剤が蓄積することが示されました。両経路の相対的重要性は添加剤の種類や組織により異なっており、それには化学物質の特性が関連していることが示唆されました。
マイクロプラスチックを通じて魚類の体内組織に蓄積した添加剤は、食物連鎖を通じて人間を含む高次消費者の体内に濃縮され、さまざまな悪影響を与える可能性があります。それらの影響を解明するための研究のさらなる進展が期待されます。
本研究成果は、2022 年 11 月 18 日(金)公開の Marine Pollution Bulletin 誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
マイクロプラスチックに含まれる添加剤が食物連鎖を通して魚類の組織に移行することを世界で初めて実証~餌生物の摂食によるプラスチック添加剤の垂直輸送の重要性を解明~(PDF)
2022-12-08
本学院生物圏科学専攻の先崎理之助教(地球環境科学研究院)、森林総合研究所の青木大輔研究員、北海道大学大学院農学院博士後期課程の北沢宗大氏、日本渡り鳥保全・研究グループの原 星一氏と共同で、これまで夜間に単独で渡ると考えられていたヤマシギのうち一定数が、日中の生息環境や生態が異なるアオバトなどの他種とペアになって渡ることを発見しました。
毎年、おびただしい数の鳥類が、遠く離れた繁殖地と越冬地の間を行き来する渡りを行います。タカの仲間や大型の水鳥などの一部を除き、多くの鳥類は、天敵からの捕食リスクが低く、気象条件が飛翔に適している夜間に単独で渡ることが知られています。しかし、夜空を渡る鳥類を識別することは難しく、夜間に渡る鳥類にどのような種間関係があるのかについては解明されてきませんでした。
こうした中で研究チームは、北日本の二カ所(室蘭鳥類観測所・津軽鳥類観測所)で、デジタル機器を用いた地上観察から夜空を渡る鳥類を識別する手法を確立し、ヤマシギと他種が 2羽で一定の距離を保ちながら渡るという未知の現象を目撃しました。そこで、2021年10~11月に上記二カ所において、どのくらいのヤマシギが他種と一緒に渡るのかを調べたところ、観察された48羽のヤマシギのうち、約17%(8羽)が他種とペアになって渡っていました。ペア種の内訳は、アオバト(5羽)、キジバト(1羽)、オオコノハズク(1羽)、ツグミ属鳥類の 1種(1羽)でした。ヤマシギは暗闇の中から単独で渡る他種のパートナーを見つけだして一緒に渡ることで、捕食者をいち早く見つけたり、目的地への飛翔距離を短縮したり、飛翔エネルギーを節約したりしている可能性があります。
なお、本研究成果は、2022 年12月1日(木)公開の Ecology 誌に掲載されました
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
夜空で密会するシギとハト~鳥類の夜間渡りにおける驚きの種間関係を発見~(PDF)
2022-11-28
本学院環境起学専攻の佐藤友徳准教授(地球環境科学研究院及び北極域研究センター)と本研究院統合環境科学部門(研究当時)の中村 哲博士(現・気象庁大気海洋部)、三重大学大学院生物資源学研究科の飯島慈裕教授、名古屋大学宇宙地球環境研究所の檜山哲哉教授の研究グループは、海氷面積の縮小や海水温の上昇など、近年急速に温暖化が進行する北極海周辺における大気中の水蒸気の流れを解析し、北極海から蒸発した水蒸気がユーラシア大陸や北米大陸に向かって近年多く輸送されていることを解明しました。
北極域では地球全体の平均に比べて早いペースでの温暖化が進行しており、この傾向は今後も継続することが予測されています。このような北極の温暖化は様々な環境変化を誘発することが懸念されています。研究グループは特定の地域から蒸発した水蒸気の、大気中における動きを追跡できる数値計算手法を用いて、北極海から蒸発した水蒸気の輸送経路や輸送量を明らかにしました。
1981 年から 2019 年までの期間について解析したところ、北極海を起源とする水蒸気の輸送が 9 月から 12 月にシベリア地域で増加していることが分かりました。このことはシベリアにおける地域的な積雪増加傾向とも整合的であり、北極海の海氷減少や水温上昇が、ユーラシア大陸や北米大陸の水循環や生態系にも影響を与えることを示唆する結果と言えます。
なお、本研究成果は、2022 年 11 月 24 日(木)公開の npj Climate and Atmospheric Science 誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
温暖化する北極海から大陸に向かう水蒸気量の増加を発見~北極の温暖化に伴う中・高緯度の気候変動や水循環過程の理解向上に寄与~(PDF)
2022-11-22
本学院生物圏科学専攻博士後期課程の藤田凌平氏、本学院生物圏科学専攻の星野洋一郎教授(北方生物圏フィールド科学センター)、同大学院医学研究院の神 繁樹特任助教と的場光太郎講師、による共同研究グループは、ハスカップの機能性成分の改変のために、近縁種のミヤマウグイスカグラとの種間雑種を育成し、ハスカップ種間雑種の果実でβ-クリプトキサンチンを合成させることに成功しました。
ハスカップは、北海道に自生する小果樹で、北海道特産のベリーとして注目されています。研究グループは、これまでにハスカップの遺伝資源の探索やハスカップの新規系統の育成を行ってきました。ハスカップ果実にはアントシアニン類が多く含まれていますが、赤色や黄色を呈するカロテノイド類はあまり含まれていません。そこで、カロテノイドを多く含み、赤い果実をつける、ハスカップの近縁種ミヤマウグイスカグラとの種間交雑を行いました。
解析の結果、種間雑種の果実でカロテノイドが合成され、ハスカップではほとんど検出されない機能性成分のβ-クリプトキサンチンが、種間雑種で合成されていることがわかりました。これは、ミヤマウグイスカグラのβ-クリプトキサンチン合成能がハスカップ種間雑種に付与されたことを示しています。また、種間交雑がハスカップの機能性成分の育種に有効であることを示すものであり、ハスカップに新たな付加価値を与えるものと考えられます。さらに興味深いことに、種間雑種の果実で、β-カロテンの含有量が両親よりも高くなっていました。また、種間雑種のβ-クリプトキサンチンの含有量は系統間差が大きく、β-クリプトキサンチンの合成能が高い系統の選抜により、β-クリプトキサンチンが豊富な果実を選ぶことができる可能性を示しています。
今後、ハスカップの機能性成分にカロテノイドの選択肢が加わることとなります。なお、本研究成果は、2022 年 9 月 29 日(木)公開の Scientia Horticulturae 誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
ハスカップ種間雑種の果実でβ-クリプトキサンチンを合成~種間交雑によりカロテノイド生合成を改変・機能性成分を強化したハスカップの育種~(PDF)
2022-11-18
本学院地球圏科学専攻の杉山 慎教授、西岡 純教授 (いずれも低温科学研究所)、山下洋平准教授(地球環境科学研究院)、同大学低温科学研究所の王 鄴凡博士研究員、同大学院水産科学研究院の山口 篤准教授、松野孝平助教らの研究グループは、東京大学大気海洋研究所の漢那直也助教(元北海道大学北極域研究センター)と共同で、複数のカービング氷河が流入するグリーンランドのフィヨルドで観測を行い、氷河の激しい融解によってフィヨルドの基礎生産が活発になることを解明しました。
グリーンランドで記録的な氷河融解が起きた 2019 年の夏、氷河が流入するフィヨルドには窒素、リン、鉄分などの栄養素が前年より豊富にあり、大型植物プランクトンが大増殖しました。解析の結果、氷河の融け水に起因する海水の汲み上げ機能(氷河ポンプ)が強く働き、中層から栄養豊富な海水が大量に湧昇し、高い栄養環境で増殖する大型ケイ藻類が出現したことが分かりました。
この研究結果は、氷河の融解によってフィヨルドの栄養環境が良好になり、基礎生産が増加することを示しています。しかし長い目で見ると、温暖化によりグリーンランドからカービング氷河が失われてしまうと氷河ポンプは機能不全に陥るため、海洋生態系への甚大な影響が予想されます。従って氷河の融解が海洋環境に与える影響を、今後も注意深く観察し、理解を深める必要があります。
本研究成果は、2022 年 11 月 4 日(金)公開の Global Biogeochemical Cycles 誌にオンライン掲載されました
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
氷河ポンプが駆動するグリーンランドの海洋環境~氷河の融解加速により海のプランクトンの群集構造が変わる~(PDF)
2022-10-22
本学院地球圏科学専攻の大島慶一郎教授(低温科学研究所)、国立極地研究所の伊藤優人研究員らの研究グループは、南極地域観測隊によるケープダンレー沖での観測から、海中で大量に海氷が生成されるメカニズムを発見し、それによって南極底層水の起源水となる重い水が作られることを明らかにしました。
世界で一番重い海水は南極海で作られ、南極底層水として沈み込み、海洋の大循環が駆動されます。研究グループは10年ほど前に、南極底層水の生成域として、それまで知られていた3ヶ所に加え、新たに南極・昭和基地の東方1,200kmのケープダンレー沖が南極底層水生成域であることを発見しました。しかし、なぜここで底層水が生成されるのかはよくわかっていませんでした。
本研究では、底層水起源水が生成されると推定される沿岸ポリニヤ内において、通年の連続観測を行い、海中100m深近くまで海氷(フラジルアイス)が生成される、極めて効率的な海氷生成メカニズムの存在を発見しました。さらに衛星観測から、このケープダンレー沖が全南極で最もこのメカニズムが働く海域であることも明らかにしました。大量に海氷が生成されると塩分の大半が氷からはき出されることで低温・高塩の重い水が作られ、この海域が底層水を形成する海域となるわけです。
海洋大循環の起点となる南極底層水の形成過程の一つを明らかにした本研究は、気候変動の理解や予測にも繋がります。また、フラジルアイスが海中深くまで達すると、生物生産を誘起する物質を海底から取り込むことができ、海氷を介する物質循環や生物生産の理解にも繋がる研究と言えます。
本研究は科学研究費補助金・基盤研究S(課題番号20221001; 20H05707)等の助成を受け、現場観測は南極地域観測の公開利用研究として実施されました。なお、本研究成果は、日本時間2022年10月21日(金)公開のScience Advances誌にFOCUS論文としてオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
全海洋の深層に広がる南極底層水の起源水形成機構を発見~海中深く大量に生成される海氷が海洋大循環を駆動する~(PDF)
2022-10-21
本学院地球圏科学専攻の飯塚芳徳准教授(低温科学研究所)を含む、国立極地研究所の猿谷友孝特任研究員を中心とする研究グループは、南極ドームふじ基地で掘削された深層アイスコアに含まれる氷の結晶の主軸方位分布を高精度で計測し、気候変動に伴った変化や含有不純物との関係性を明らかにしました。
これまでに掘削された様々なアイスコアでも結晶主軸方位分布の解析は行われてきましたが、測定方法の制約から細かい変動の検出は困難でした。研究グループは結晶主軸方位分布を解析する新たな手法として「誘電異方性計測法」を世界で初めて開発し(図 1)、これまでに類を見ない水準の高空間分解能かつ統計的信頼性をもった結晶主軸方位分布データが取得可能となりました。
氷の結晶の軸の方位は、氷床の浅い部分のアイスコアではばらつきが大きく、深くなるほどばらつきが小さくなって鉛直方向に揃っていくことが知られています。本研究では、高分解能での計測が可能な「誘電異方性計測法」を用いることにより、結晶主軸方位分布の深さ方向の変化は直線的ではなく、ばらつきが大きくなったり小さくなったりという“ゆらぎ”を繰り返しながら変化することを明らかにしました。さらに、深い部分のアイスコアほど“ゆらぎ”が大きいことや、今からおよそ 13 万年前や 24 万年前の間氷期から氷期へ移り変わる時期に、結晶の方位のばらつきが大きくなること、また、アイスコアの中に含まれる塩化物イオンの濃度や固体微粒子の数もばらつきの変化に関与していることが分かりました。
結晶主軸方位分布は、南極氷床の流動のしやすさに直接影響します。本成果は、将来の海面上昇予測に不可欠な、今後の氷床流動の予測に重要な知見です。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
氷結晶の主軸方位分布を深さ 2400m にわたり詳細に分析 〜南極ドームふじアイスコアで計測、氷床流動の理解に貢献~ (PDF)
2022-09-30
本学院環境起学専攻の根岸淳二郎准教授(北海道大学大学院地球環境科学研究院)らの研究グループは、北海道東部十勝川支流札内川において、川底地下に生息するカワゲラ科昆虫一種(イシカリミドリカワゲラ)の生活史と食物網における餌資源の長期観測に成功しました。
長期観測の結果、孵化直後の本種幼虫は11月頃から地下30-50センチの深度に現れ、その後、約2年半かけて成長した後に成虫として羽化することが明らかになりました。羽化成虫は6月と7月に河畔で多く見られ、羽化のタイミングは河川水温の高い年に早まる傾向が確認されました。成虫は最大10日程度で寿命を終えるので、成虫の河川での産卵後、計約3年程度を地下で幼虫として過ごすと考えられます。
また、食物網構造の解析から、川底地下で共存するその他の動物(ユスリカ科幼虫やミミズ類)を通年捕食する2次消費者であることも明らかになりました。本研究の成果により、河川地下の動物群集の動態や生物多様性の解明と効果的な保全に一歩近づくことが期待されます。
なお、本研究成果は、2022年9月27日(火)公開のHydrobiologia誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
「石の下にも3年」水生昆虫生活史を解明~地下を含めた河川環境保全への貢献に期待~(PDF)
2022-09-30
本学院地球圏科学専攻のエヴゲニ ポドリスキ准教授(北海道大学北極域研究センター)らは、電子タグを装着したイッカクの行動を長期間にわたってモニタリングし、そのデータをカオス理論の数理技術を使って分析しました。その結果、潜水や海面での休息など、昼間の行動パターンが初めて明らかにされました。
イッカクは北極の海に生息する鯨類ですが、その変則的な行動を分析する方法は、センサーなどの技術が発達した現在でも乏しく、生息の実態はまだ不明な点が多いのが実情です。また、長期モニタリングのデータに基づいた研究例も、ごくわずかです。
ポドリスキ准教授は、グリーンランド天然資源研究所のMads Peter Heide-Jørgensen教授と共同で、極めて複雑だとされるイッカクの行動パターンを解明する手法を確立しました。この手法で83日間にわたるモニタリングを行い、得られたデータを解析した結果、特徴的な潜水スタイルや、昼間に海面近くで休息する行動が見られました。当初、これらは変則的な行動と考えられましたが、詳細なデータ分析から、通常のパターンであることが判明しました。
北極域は、温暖化や海氷減少など、深刻な環境変化の影響を強く受けてきました。イッカクもその例外ではなく、準絶滅危惧種に指定されています。本研究は、イッカクを含む、北極圏に生息する動物の保護をめぐる課題を浮き彫りにし、今後の対策の一助になると期待されています。
なお、本研究の成果は2022年9月22日(木)公開のPLOS Computational Biology誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
「海のユニコーン」イッカクの行動の謎に迫る~行動パターンをカオス理論で解明。北極域での絶滅危惧種の保護対策に活用へ~(PDF)
2022-09-26
本学院博士後期課程(地球圏科学専攻)の波多俊太郎氏と本学院地球圏科学専攻の杉山慎教授(低温科学研究所)、同大学の日置幸介名誉教授(元理学研究院教授)らの研究グループは、人工衛星データ解析から南米チリ・パタゴニアで発生した氷河湖決壊洪水を発見し、その規模とメカニズムを明らかにしました。
人工衛星データを用いて同地域の氷河変動を解析中に、氷河が流れ込む湖としては世界で4番目に大きなグレーベ湖で、2020年4月に水位が約20メートル急激に低下したことが判明しました。さらなる解析から、同年7月までに3.7 km3の湖水が流出したことが示されました。この氷河湖決壊洪水は、人工衛星によって地球が観測されるようになって以来、世界最大規模のものです。高解像度の人工衛星画像などを駆使して決壊原因を調査したところ、地形の崩壊によって湖から流出する河川の流れが移動し、河床の侵食が進んで排水が起きたことが確認されました。さらに、GRACEと呼ばれる地球重力を測定する人工衛星のデータを解析した結果、排水による重力場の変化を捉えました。氷河湖決壊洪水に伴う質量変化が、GRACE衛星で観測されたのは初めてのことです。
パタゴニアでは急速に氷河が後退して氷河湖が拡大していますが、アクセスが困難で研究が十分に行われていません。研究グループは同地域での長い研究実績を活かして、稀に見る規模の氷河湖決壊を世界に先駆けて発見することに成功しました。この結果は、氷河湖の決壊による災害、氷河の将来変動、重力衛星による地球観測の可能性について、貴重なデータを提供するものです。
本研究成果は、2022年8月26日(金)公開の Communications Earth & Environment誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
世界最大規模の氷河湖決壊を宇宙から発見!~南米パタゴニアで起きた氷河湖の決壊洪水を世界に先駆けて衛星データで解明~(PDF)
2022-09-20
本学院地球圏科学専攻の飯塚芳徳准教授(低温科学研究所)らの研究グループはグリーンランドのアイスコアに保存されている硫酸エアロゾルの粒径分布の復元にはじめて成功し、人為硫黄酸化物の排出最盛期である1970年代の硫酸エアロゾルは主に0.4µmより小さかったことを解明しました。
硫酸エアロゾルの組成や粒径分布は、地球の放射収支を考える上で重要な要素です。しかし、過去の硫酸エアロゾルの組成や粒径分布については、信頼できる観測がないためほとんど情報がなく、過去のエアロゾルの組成と輸送をモデル化することに不確実性が大きいのが現状です。今回、研究グループは、グリーンランドのアイスコアに保存されている硫酸エアロゾルの粒径分布の復元に成功し、1970年代に北極で小さな硫酸塩粒子が増加したことを示す最初の観測的証拠を提示しました。今回の研究結果はエアロゾルと雲の相互作用の理解を深めるとともに、モデルにおけるパラメータ設定に新たな制約を与えるものです。これは、地球温暖化のメカニズムの理解向上につながり、将来予測の精度を高めることが期待されます。
なお、本研究成果は、2022年8月25日(木)公開のJournal of Geophysical Research, Atmospheres誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
1970年代の硫酸エアロゾルの粒径復元にはじめて成功~硫酸エアロゾルが雲をつくる作用の解明による、地球温暖化メカニズム研究の進展に期待~(PDF)
2022-07-28
本学院生物圏科学専攻の小林 真准教授(北方生物圏フィールド科学センター)らの研究グループは、地球温暖化にともなって雪解けの時期が早まると、北海道の森林に生育する植物がどのような影響を受けるのかを調査した結果、雪解け時期の早まりはダケカンバ等の大きな木(成木)の成長には影響を与えず、林床植物のみ稈(かん: 枝にあたる部分)の成長を約15%増加させることを明らかにしました。
研究では大型ヒーターに接続した温風の出るダクトを森中に張り巡らせ、森林全体(合計1,600平方メートル)の雪を溶かすという世界でも類を見ない大規模な野外実験を行いました。実験により10日間ほど雪解け時期が早まると、土壌中の微生物が活発になり、春先に植物が成長に利用しやすい土壌中の窒素が多く作られました。一方、養分の増加は、成木の成長促進には影響を与えなかった一方で、林床植物であるササの成長を促進することが分かりました。
本研究は、”雪解け時期の早まり”という冬に起こる気候変動は、森林の植物へ等しく影響するのではなく、林床植物と成木ではその影響の受け方が異なることを、人工的に雪解け時期を早める大規模実験により示した世界で初めての成果です。
雪解け時期の早まりに対して林床植物の成長が、より敏感に増加することが明らかになったことで、将来の森林が大気中の二酸化炭素を固定する機能を推定する際には、成木だけではなく林床植物による二酸化炭素の吸収を評価することが重要であることが分かりました。今後は、より正確に将来の森林による気候調整機能の理解が深まることが期待されます。
なお、本研究成果は、2022年7月26日(火)公開のEcosphere誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
温暖化で雪解け時期が早まるとササが伸びる~人工的に雪解けを起こした世界初の大規模研究で、雪降る森の正確なCO2吸収量把握に期待~(PDF)
2022-07-12
本学院地球圏科学専攻博士前期課程(研究当時)の福本峻吾氏と、本学院地球圏科学専攻の杉山慎教授(低温科学研究所)、三寺史夫教授、白岩孝行准教授らの研究グループは、人工衛星データによって、ロシア・カムチャッカ半島における氷河の質量変動を明らかにしました。
現在、世界各地の山岳地域で氷河の急激な衰退が報告されています。山岳域の氷河は地球上の氷総量の1%に過ぎませんが、その氷損失量は南極やグリーンランドの氷床よりもずっと激しく、21世紀の氷河氷床全融解量の80%を占めています。しかしながら、ロシア・カムチャッカ半島の氷河については研究例が少なく、氷河変動の正確な理解が求められていました。
そこで研究グループは、人工衛星データを使ってカムチャッカ半島全域で氷河の表面標高変化を解析し、2000~2016年の氷量変化を測定しました。その結果、21世紀に入って半島全域で4.9Gtの氷が失われ、0.013mmの海水準上昇に相当する融解水が流出したことが明らかになりました。また2010年以降は氷河の縮小が特に激しく、毎年1mを超える世界的にも顕著な質量減少が確認されました。また、気候変動の経年変化(太平洋十年規模振動)を解析した結果、同半島における氷減少が今後も加速することが示唆されました。以上の結果は、温暖化とそれに伴う気候変動に対して、カムチャッカ半島の氷河が敏感に反応していることを示します。本研究成果によって、海水準上昇の正確な把握と予測が実現し、カムチャッカ周辺の水文環境の理解が進むことが期待されます。
本研究成果は、2022年7月4日(月)公開のJournal of Glaciology誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
ロシア・カムチャッカ半島で最新の氷河変動を解き明かす~近くて遠い、極東ロシアに見る気候変動~(PDF)
2022-07-12
本学院地球圏科学専攻の青木茂准教授(低温科学研究所)は、国立極地研究所の平野大輔助教、海洋研究開発機構の草原和弥研究員らの共同研究グループと共に、インド洋区にあるアメリー棚氷とケープダンレーポリニヤ付近の南極海沿岸において、海氷の少なかった2016/17年の夏季は海面水温が例年より0.5~1℃も高く、ポリニヤ域表層海水中の棚氷融解成分が約30%高かったことを観測しました。融解成分の高い状態は冬まで継続しました。
人工衛星データや数値実験結果の解析から、夏季に海氷が少ないときには海面付近に通常より多く熱がたまり、風により表層の暖水が棚氷の下に押し込まれ、棚氷を底面から融解させるメカニズムが働くことを見出しました。その後、アメリー棚氷方面から低塩分の暖水が流れてくることでポリニヤでの秋季の海氷形成が遅れ、深層大循環に関わる高密度水の形成が遅れることもわかりました。これまで棚氷の融解には水深数百メートルにある暖水が主要な役割を果たしていると考えられてきましたが、今回の研究は高温になった夏季表層水の沈み込みも大きく寄与することを示しています。
今後、地球温暖化が進行すると南極の海氷も減少すると予想されていますが、海氷減少に伴って海洋表面の貯熱量も加速度的に増大し、棚氷の融解を通じて南極氷床に影響を与えると同時に、海氷の生産が遅れることを通じて深層大循環にも影響する可能性を示しています。
本研究成果は、2022年6月22日(水)公開のCommunications Earth&Environment誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
南極海の表層にたまった熱が氷河を底から融かす~海氷の生成を遅らせて深層大循環に影響する可能性も~(PDF)
2022-06-15
本学院生物圏科学専攻の早川卓志助教(地球環境科学研究院)と、明治大学研究・知財戦略機構の糸井川壮大研究推進員は、京都大学、アデレード大学、オーストラリア国立大学、コペンハーゲン大学との国際共同研究チームをつくり、卵を産む哺乳類(単孔類)であるカモノハシとハリモグラが持つ苦味センサータンパク質(苦味受容体)の機能を網羅的に分析しました。水中の多様な生物を食べるカモノハシは、幅広い種類の苦味物質を検知できる万能型苦味受容体を持つが、アリ・シロアリ食に特化したハリモグラは、カモノハシのような万能型受容体を持たず、検出できる苦味物質が少ないことが分かりました。ハリモグラがアリやシロアリを専門に食べるようになったことで苦味の重要性が下がり、限られたものにしか苦味を感じなくなった一方で、水中で様々な生物を摂食するカモノハシは苦味受容体を使って食べられるものの選択を行っている可能性を示しています。
さらにカモノハシやハリモグラでも、植物などに含まれる有毒な配糖体を検知する苦味受容体は残されており、この苦味受容体の機能はヒトを含む全ての哺乳類グループで共通のものであることも分かりました。ヒトやその他の哺乳類がカモノハシ・ハリモグラと分かれたのは約2億年前まで遡ります。大型恐竜が繁栄し、花を咲かす被子植物の多様化が始まろうとしていた時代です。恐竜と競合しながら、植物や昆虫などの毒を含みうる食べ物を口にして進化した哺乳類において、苦味感覚の進化が非常に重要であったことを本研究は意味します。
なお、本研究成果は、日本時間2022年6月1日(水曜)公開のMolecular Biology and Evolution誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
卵を産む哺乳類カモノハシとハリモグラの苦味感覚を解明~恐竜時代から続く哺乳類の毒物に対する味覚の適応進化~(PDF)
2022-05-30
本学院環境起学専攻の先崎理之助教(地球環境科学研究院)は,北海道大学大学院農学研究院の中村太士教授及び同大学院農学院博士後期課程の北沢宗大氏,同博士前期課程の埴岡雅史氏(研究当時)と,森林総合研究所の山浦悠一氏,大橋春香氏,小黒芳生氏,松井哲哉氏と共同で,明治時代以降,森林や湿原の農地への転換によって,石狩平野で繁殖する鳥類の個体数が約 150 万個体減少したと推定しました。
森林の伐採や湿原の埋め立てなど,自然生態系の転換は生物多様性への大きな脅威であると考えられています。特に農地は世界の陸上面積の 30%近くを占めるため,自然生態系の大規模な農地への転換は,陸上の生物多様性に大きなインパクトを与えてきた可能性があります。しかしながら,北半球,特に農業の歴史が長い温帯の多くの地域では,1700 年代までに自然生態系が大規模に農地へ転換されたため,生物多様性への詳細な影響(時期や規模)を定量化することは困難でした。
そこで本研究では,1860 年代以降に大規模に農地が造成された北海道石狩平野に着目し,鳥類の個体数に与えた影響を定量化しました。開拓期の古地図などをデジタル化して四時期(開拓前・1900年・1950 年・1985 年)の土地利用図を復元し,研究グループが野外調査から求めた鳥類個体数密度をあてはめて,石狩平野の過去 166 年間の鳥類個体数の変遷を推定しました。その結果,1850 年に石狩平野で繁殖していた約 210 万個体*1の鳥類は 2016 年に 60 万個体まで減少したと推定されました。
すなわち,鳥類の個体数は過去 166 年間で約 70%減少したと推定されました。本研究結果は,大規模な土地利用の変化とそれに続く生物の減少が,北半球の広い地域で過去に生じたことを示唆しています。
そして,平野部の湿原や森林の保護・再生活動が,かつて大きく数を減らした森林性・湿原性鳥類を保全する上で重要であると考えられます。また,各地で拡大している耕作放棄地(農業を中止した農地)が森林性・湿原性鳥類の再生に寄与するのか,今後も研究を続ける予定です。
本研究成果は,2022 年 5 月 25 日(水)公開の Proceedings of the Royal Society B: BiologicalSciences 誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
過去166年間にわたる石狩平野の鳥類分布の変遷~鳥類の個体数が約150万個体(70%)減少したと推定~(PDF)
2022-05-26
本学院地球圏科学専攻の青木茂准教授(低温科学研究所)は,東京海洋大学の嶋田啓資特任助教らの研究グループと共に,オーストラリア南方の南極海の中深層で水温が下がり,溶存酸素濃度が高くなる傾向が広がっていることを見いだしました。これまで,主に氷河・氷床の融解促進により南極海の広い領域で塩分が低くなっており,それにより海水の密度は低下し,南極底層水の生成量は少なくなっていると考えられていました。南極海で低温な水の沈み込みが弱くなることで全球を巡る深層大循環*4 が弱まり,南極海の底層を中心に高温化していることが指摘されていました。今回見いだされた中深層の低温化,高酸素濃度化は低密度化によって底層に沈み込めなくなった低温・高酸素濃度の海水が,より浅い中深層に大量に広がっていることを示しており,深層大循環変貌の実態をさらに包括的に捉えたものと言えます。」こうした海の変化の実態は,南極地域観測事業の一環として東京海洋大学の練習船「海鷹丸」により2010年度以降継続して観測した結果を,過去の観測データと併せて解析することで判明しました。今後も南極海の低塩分化,沈み込みの浅化が継続すると,深層大循環の変化に伴い熱や炭素などの輸送が大きく変わり大規模な気候変動をもたらすことが危惧されるため,引き続き海鷹丸の観測を維持し変化の動態を注視していく要があります。
なお,本研究は東京海洋大学,北海道大学,国立極地研究所,上海海洋大学の共同で実施されました。本研究成果は,日本時間 2022 年 5 月 19 日(木曜)に Communications Earth & Environment 誌に掲載されました
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
海洋深層大循環に激変の兆しを検出~低密度化により南極大陸縁辺の沈めぬ冷水が大量に中深層へ~(PDF)
2022-05-16
本学院生物圏科学専攻の工藤 岳准教授(地球環境科学研究院)は,日本最大の高山生態系を有する北海道大雪山系で30年におよぶ高山植物の生態調査の結果,虫媒花植物の多くが他家受粉に特化していることを突きとめました。寒冷な高山環境では昆虫の活性が低いため,高山植物は十分な受粉サービスを受けられず,自家受粉によって子孫を残す種が多いのではないかと考えられてきました。ところが40種以上の高山植物を調べた結果,全体の85%の種は自殖能力を持たず,他殖のみを行っていることが明らかになりました。これは,陸域生態系全般で見られる傾向よりも顕著に他家受粉に偏ったものであり,高山植物の繁殖システムを根本的に見直す必要性を示唆するものです。
ほとんどの高山植物はハエ・アブ類かマルハナバチに花粉媒介を頼っていますが,両媒花グループで結実率の季節的傾向は異なりました。ハエ媒花植物では季節的な傾向が見られなかったのに対し,ハチ媒花植物の結実率は季節進行と伴に顕著に増加していました。生育期前半に開花すると受粉がうまく行われず,結実が制限されていた一方で,働きバチが現れる生育期後半に開花すると,結実率は大きく高まりました。ハチ媒花植物の種子生産はハチの季節性に強く依存しており,今後の気候変動で高山植物の開花時期が早まると,ハチと植物の共生関係が崩壊する可能性があります。
本研究成果は,2022年5月9日(月)公開のEcological Research誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
高山植物がきれいなのは虫に花粉を運ばせるためだった ~他家受粉に特化した高山植物の繁殖システムを解明~(PDF)
2022-04-01
北海道大学大学院地球環境科学研究院の山本正伸教授,同大学低温科学研究所の関 宰准教授,同大学環境科学院修士課程(研究当時)の土屋優子氏,東京大学大気海洋研究所の大石龍太特任研究員,阿部彩子教授の研究グループは,ベンガル湾堆積物に含まれる植物起源脂肪酸の炭素同位体比が過去の大気中二酸化炭素変動を表していることに気がつき,新手法として提案するとともに,過去150万年間の大気中二酸化炭素濃度の変動を明らかにしました。
大気中二酸化炭素は地球の気候を決定する重要因子です。将来の温暖化を予測するうえで,二酸化炭素が過去の気候変動にどのように影響したのか,詳細に解明することが必要です。これまで過去の二酸化炭素濃度は,南極の氷を掘削して得られたアイスコアに含まれるガスを分析することで明らかにされてきました。研究グループは,ベンガル湾堆積物に含まれる植物起源脂肪酸の炭素同位体比が,過去の大気中二酸化炭素変動を表していることを,アイスコアの二酸化炭素濃度を比較によって示しました。そしてその関係を利用し,80万年以前の大気中二酸化炭素濃度変動を,初めて高精度・高時間解像度で明らかにしました。
本研究の結果,80万年前以前でも二酸化炭素濃度が陸上氷床体積にほぼ同調して変動していたことが明らかになりました。しかし,予想外に100万年前よりも前の温暖だった時代でCO2濃度は決して高くはなかったことがわかりました。また,100万年前よりも前の時代では,二酸化炭素が陸上氷床よりも早く変動していたのに対し,80万年前より後の時代では陸上氷床が二酸化炭素よりも早く変動していたこともわかりました。
なお,本研究成果は,2022年4月1日(金)公開のNature Geoscience誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
過去150万年間の大気中二酸化炭素濃度を解明(PDF)
2022-03-28
北海道大学低温科学研究所のグレーべ・ラルフ教授とチェンバース・クリストファー博士は,西暦3000年までのグリーンランドの氷床の変動についてシミュレーションを行い,21世紀の温暖化がもたらす長期的な影響について調べました。
これまで,本研究チームも参画する氷床モデル比較相互プロジェクト(ISMIP6)は,気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書に研究内容を提供してきましたが,その氷床変動計算は西暦2100年まででした。本研究では,西暦2100年以降は温暖化の傾向に変化がないとの仮定のもと,西暦3000年までのシミュレーションを行いました。「温暖化進行」経路シナリオで12の数値実験,「地球温暖化ガス排出量の削減」の経路シナリオでは2つの実験をそれぞれ行いました。「温暖化進行」のシナリオでは,氷の損失の海面水位相当(SLE)は,12の実験のアンサンブル平均で1.8 mに上りました。「ガス排出量削減」のシナリオでは,氷の損失は,2つの実験のアンサンブル平均で0.25mSLEに留まることがわかりました。
本研究の結果では,温暖化は,たとえ21世紀末に進行が停止したとしても,効果的な気候変動緩和策が取られない限り,その後数百年にわたりグリーランドの氷床への影響があり,世界的な海面上昇につながる危険を示唆しています。
本研究は,2022年3月14日(月)公開のJournal of Glaciology誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
西暦3000年までのグリーランド氷床の変動を予測~このまま温暖化が進むと氷床の体積が半分に減る可能性を示唆~(PDF)
2022-03-28
北海道大学大学院地球環境科学研究院の山本正伸教授と同低温科学研究所の関 宰准教授は,過去4000年間の北海道北部の気候変化を復元し,文化圏の変遷のタイミングが気候変化と合うことを明らかにしました。
気候変化が人間社会に与える影響を理解することは,温暖化の進行に伴う人類社会の将来を予測したり,気候変動の社会への影響を緩和したりする上で非常に重要です。北海道は1万年前から19世紀まで,狩猟採集文化の人口密度の高い社会が変化を伴いながら存続していた,世界でも稀な地域です。縄文時代以降,気候が社会や文化に与えた影響が示唆されてきましたが,北海道には,それを実証するのに十分な時間解像度を持つ古気候記録がなかったため,今まで検証されていませんでした。
紀元後の海洋型のオホーツク文化の南方への拡大は,対馬暖流の弱化と偏西風の南下により,冷たく乾燥した気候に変化した後に起こったことがわかりました。11世紀ごろのオホーツク文化の衰退は対馬暖流及びその延長の宗谷暖流の強化に対応していました。一方で,内陸型の続縄文文化,擦文文化,アイヌ文化の空間分布は,南北の縁が緯度方向に移動するものの,北海道島にとどまりました。文化圏の北縁はオホーツク文化の盛衰に,南縁は偏西風の南北移動に対応した稲作文化の北限の移動に規制されていたようにみえます。
なお,本研究成果は,2022年3月12日(土)公開のGeophysical Research Letters誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
北海道の縄文時代以降の歴史からみた気候と人間社会の関係(PDF)
2022-03-22
北海道大学北方生物圏フィールド科学センターの内海俊介准教授,安東義乃学術研究員が参画する国際共同研究チームGLUE(Global Urban Evolution Project)は,都市化が地球規模で生物進化に影響を与えていることを明らかにしました。人は地球環境を大きく作り変えています。なかでも,地球上で最も環境改変が進んでいるのは都市です。今回の研究では,地球規模で,気候帯も異なる様々な都市において,平行的に類似した進化が繰り返し起きているのかという問いについて初めて検証しました。5大陸・26か国・160都市で,都市環境と約11万個体のシロツメクサを分析した結果,世界中の都市の環境条件は,近くの郊外よりも地理的に離れた都市間でよく似ており,シロツメクサはしばしば類似したパターンで進化していることが明らかになりました。シアン化水素を生成するシロツメクサの性質は,植食者への防衛や乾燥ストレス耐性に貢献しますが,多くの都市でこの性質が喪失していく進化が起きていました。シロツメクサという身近で世界中に存在する植物から,人々の暮らす都市が生命の進化のありかたを変える決定的な証拠が得られました。
本研究成果は,2022年3月18日(木)公開のSCIENCE誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
都市は地球規模で植物の進化を促す~国際共同研究チームによる検証~(PDF)
2022-03-14
北海道大学北極域研究センターの安成哲平准教授,同大学院工学院修士課程の若林成人氏(研究当時),同低温科学研究所の的場澄人助教,名古屋大学の松見 豊名誉教授(宇宙地球環境研究所)らの研究チームは,パナソニック製の小型PM2.5センサーを搭載した,寒冷地でも動作温度環境を自動で保つことが可能な自動温度制御断熱ボックスを開発しました(以下,PM2.5測定装置)。室内及び低温室における動作確認・検証実験や,冬季札幌・夏季アラスカでの現地観測による,現地の独立したPM2.5観測データとも比較検証を行うことで非常に寒冷な環境や,森林火災のような高濃度PM2.5環境下においてのPM2.5測定にも,開発した装置が十分実用的であることを確認しました。
北極圏では,夏季森林火災から冬季気温の逆転層形成による大気汚染まで,通年を通じてPM2.5の測定が求められていますが,これまでは厳冬期の観測が非常に困難でした。本研究で開発した寒冷地仕様のPM2.5測定装置は,温度コントローラーの設定温度より少し低くなると,装置内部がヒーターで自動で温められ,外部が極寒でも内部をPM2.5センサー動作環境に保つことができるため,冬季や通年で寒冷な場所でPM2.5観測を安定かつ継続して行うことが可能になります。また,開発実験では,防水ファンによる強制通風が必須であることがわかりました。北海道大学低温科学研究所の−25℃の低温室実験では,ヒーターが正常に動作し,通風口2つの条件で内部の温度環境をプラスに保つことができることも確認しました。さらに,2019年2月に北海道大学工学部屋上で観測を行い,環境省国設局「国設札幌」で測定されたPM2.5の1時間値(確定値)の変動と比較したところ,本研究のPM2.5測定結果の1時間平均値と変動が整合的であることも確認できました。2019年6月からは,アラスカ大学フェアバンクス校(UAF)国際北極圏研究センター(IARC)に同PM2.5測定装置を設置し,夏季(6-7月)アラスカの森林火災時の高濃度PM2.5変動を捉えることに成功しました。
今後,冬季に寒冷になるアラスカやグリーンランドなどの北極圏及び南極など通年で寒冷な場所でも,安定にPM2.5の継続観測を行うことが可能となり,PM2.5測定が希薄な極寒の地域での観測展開が大いに期待されます。
なお、本研究成果は,2022年3月10日(木)公開のJournal of Environmental Management誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
極寒の地域でも使用可能なPM2.5測定用の自動温度制御断熱ボックスを開発~アラスカなどの北極圏から南極まで今後の測器展開と寒冷地PM2.5定常観測の発展に期待~(PDF)
2022-03-03
北海道大学低温科学研究所博士研究員(研究当時/現:東京大学大気海洋研究所 研究員)の西川はつみ氏と同大低温科学研究所の三寺史夫教授,水産研究・教育機構水産資源研究所の奥西 武グループ長,東京大学大気海洋研究所の伊藤進一教授,海洋研究開発機構の美山 透主任研究員らの研究グループは,亜熱帯循環と亜寒帯循環の境界である“北太平洋移行領域"の形成過程を漂流型の海洋気象ブイや海流の仮想粒子追跡手法を用いて解明しました。
日本の東側の北緯 40 度付近に帯状に広がる北太平洋移行領域は,黒潮と親潮の水が混ざり合った特徴的な水塊が形成される海域です。この移行領域は,亜寒帯海域にもかかわらず比較的暖かく栄養が豊富なことから海洋生態系にとって好環境であり,漁場も形成される豊かな海です。さらに,この域での海面水温変動は,中緯度の大気循環に大きく影響することもわかってきています。しかし,行領域での黒潮・親潮水の挙動はこれまで十分には理解されてきませんでした。本研究では,黒潮水・親潮水が移行領域の中を海底地形に対応した流れによって輸送・滞留する様子を可視化し,移行領域の形成過程を解明しました。また,移行領域へ黒潮水が供給されるためには,流れの時間変動成分(=渦)が重要な役割を果たしていることを明らかにしました。
なお,本研究成果は,2021 年 10 月 18 日(月)公開の Progress in Oceanography にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
黒潮と親潮をつなぐ日本東方の海水輸送過程を可視化(PDF)
2022-02-28
北海道大学大学院地球環境科学研究院の中村 哲博士研究員,佐藤友徳准教授の研究グループは,気候モデル実験や気象庁の予報データの分析による多角的な調査を行い,令和2年7 月豪雨(2020年7月)の原因の一つとして北極温暖化の影響があることを発見しました。
2020 年夏6月下旬にシベリアで記録的な熱波が観測され,その直後の7月上旬には中国の長江流域や日本の九州を中心とした地域で記録的な大雨が起こり,大きな被害が出ました。本研究では,シベリアで熱波を引き起こしたブロッキング高気圧に着目し,その発達度合いが大きいほど梅雨前線帯の降水量が強まることを発見しました。気象庁の全球アンサンブル予報データを分析し,ブロッキング高気圧の予測が現実的になるように補正することで,当初の予測では過小評価していた豪雨時の降水量が最大で20%増加し,予測精度が向上しました。さらに,北極温暖化が進行することを仮定した気候予測シミュレーションを行ったところ,シベリアでのブロッキング高気圧の発生頻度が増加し,東アジアの夏の降水量も増加することがわかりました。
北極温暖化は雪氷や永久凍土の融解など北極圈に多大な影響を及ぼすことが知られていますが,これに加えて,大気循環を介した遠隔影響の結果,日本周辺の豪雨災害とも関連することがわかりました。本研究の成果は,これまであまり着目されていなかった北極域から中緯度地域への遠隔影響の一端を明らかにしたことに加え,その影響を気象予報技術に応用することで,豪雨災害の予測精度向上に寄与することが期待されます。
なお,本研究成果は2022年2月3日(木)公開の Environmental Research 誌にオンライン先行公開されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
北極温暖化の遠隔影響により梅雨期の降水量が増加することを発見 ~豪雨災害の予測にむけて新たなメカニズムを提唱~(PDF)
2022-02-02
本学院地球圏科学専攻のグレーベ・ラルフ教授(低温科学研究所)らは,東京大学大気海洋研究所の阿部彩子教授ら,海洋研究開発機構の齋藤冬樹研究員との共同研究チームで,西暦3000年までの南極氷床の変動についてシミュレーションを行い,地球温暖化の長期的な影響について調べました。
これまで,本研究チームも参画する氷床モデル国際比較相互プロジェクト(ISMIP6)は,気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書に研究内容を提供しましたが,その氷床変動計算は西暦2100年まででした。本研究では,西暦2100年まで既存の気候予測データを使用し,その後西暦3000年まで21世紀後期の気候が持続するという仮定のもと,「温暖化進行」経路シナリオで14の数値実験,「地球温暖化ガス排出量の削減」の経路シナリオで3つの数値実験をそれぞれ行いました。その結果,氷の損失を海面水位上昇に換算すると,温暖化進行のシナリオでは西暦3000年までのアンサンブル平均で,3.5mに上りました。また,温暖化の影響を最も受けると仮定した数値実験では5.3m上昇し,排出量削減のシナリオでは0.25mに留まることがわかりました。
本研究成果は,21世紀中に温暖化が一旦進行してしまうと、例えその温暖化進行が21世紀末で停止したとしても21世期末以降に起こる数百年の南極氷床の後退と海水準上昇に大きく影響し,その影響は長期に及ぶことを示しています。
なお本研究成果は,2021年12月22日(水)公開のJournal of Glaciology誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
西暦3000年までの南極氷床の変動を予測〜氷床の崩壊を防ぐための効果的な気候変動対策が重要〜(PDF)
2022-01-13
本学北方生物圏フィールド科学センターの須藤健二博士研究員と仲岡雅裕教授,本学院修士課程(研究当時)の前原せり菜氏と本研究院の藤井賢彦准教授の研究グループは,地球温暖化にともなう海水温上昇により,日本の沿岸地域で熱帯性魚種の分布が将来的に拡大することを詳細に予測しました。有毒魚としてソウシハギ(Aluterus scriptus)とアオブダイ(Scarus ovifrons),草食魚としてノトイスズミ(Kyphosus bigibbus)とアイゴ(Siganus fuscescens),観賞魚としてハマクマノミ(Amphiprion frenatus)とトゲチョウチョウウオ(Chaetodon auriga)に対してそれぞれの分布推定と予測を行ったところ,今後,CO2を含む温室効果ガスの大幅削減を行わない場合,今世紀末には日本沿岸での生息地が現在よりも最大 2 倍程度拡大する一方,温室効果ガスを大幅削減する場合はその生息地が現在から大きく変化しないことがわかりました。本結果成果は,パリ協定に従うなど,温室効果ガスの排出量削減に意欲的に取り組むことで,将来の沿岸地域の地球温暖化影響を大きく緩和できることを示唆しています。さらに,数 kmの高空間解像度の結果は,沿岸地域の地方自治体等が気候変動適応策を策定する際の科学的指針として直接利用することができると期待されます。
なお,本研究成果は,2022年1月5日(水)公開のFrontiers in Built Environment誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
日本沿岸の熱帯性魚種の詳細な分布推定・予測に成功~沿岸の地方自治体等での地球温暖化適応策の策定への貢献に期待~(PDF)
2021-12-28
本学院地球圏科学専攻の青木茂准教授(低温科学研究所)は,国立極地研究所の國分亙彦助教を中心とする研究グループと共に,南極・昭和基地でウェッデルアザラシに水温塩分記録計を取り付けて調査を行い,その観測データから,秋に外洋の海洋表層から暖かい海水(暖水)が南極大陸沿岸に流れ込んでいること,また,その暖水を利用することでアザラシが効率よく餌をとっていたことを明らかにしました。本成果は,秋期から冬期の南極海沿岸の海洋循環のメカニズムと海洋生態系の応答プロセスの解明につながると期待されます。この観測は第58次南極地域観測隊(2016年~2018年)の一環として実施されました。
なお,本研究成果は,2021年10月9日付けのLimnology and Oceanography誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
アザラシによる観測で秋~冬の南極沿岸の海洋環境が明らかに(PDF)
2021-12-17
本研究院の松村伸治学術研究員らのグループは,近年,夏季のグリーンランドで温暖化が減速しているメカニズムを解明しました。グリーンランドの氷床は,温室効果ガスの増加に伴った温暖化によって長期的に見ると融解が進んでいます。ところが,2012年にグリーンランドの気温上昇が過去最高に達してから,最近10年間では低温傾向で氷床融解が減速しつつあると報告されており,その原因はよくわかっていませんでした。
研究グループは大気海洋の観測データの解析を行い,熱帯太平洋からグリーンランドへのテレコネクションが温暖化減速の要因であることを見出しました。気象学的に夏季は熱帯上空が東風であるため,熱帯から北極域へのテレコネクションは発達できません。しかし,2000年代以降,赤道太平洋で発生する従来型のエルニーニョ/ラニーニャ現象よりも亜熱帯太平洋で発生するエルニーニョ/ラニーニャもどき現象が頻発することで,海面水温と降水帯の変化が亜熱帯海域まで北上して東風領域を脱するため,テレコネクションを生み出すことが可能となりました。実際に簡易大気モデルで降水帯の北上を反映させると,グリーンランドへのテレコネクションが再現できました。最近10年間ではエルニーニョもどきが頻発しており,亜熱帯からのテレコネクションがグリーンランド上空で雲を発生しやすい低気圧性循環を強め地上に低温をもたらしています。この低気圧性循環はさらに高緯度の北極海上空にまで及んでおり,最近の海氷減少の減速にも影響している可能性があります。
今後エルニーニョと反対のラニーニャもどきが頻発するとグリーンランドに高温をもたらし,人為起源による温暖化との相乗効果でこれまで以上に温暖化と氷床融解が加速すると予期されます。
なお本研究成果は,2021年12月16日(木)午後7時公開のCommunications Earth & Environment誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
グリーンランドで夏に温暖化が減速している謎を解明~北極海の海氷減少の減速にも影響~(PDF)
2021-12-16
本学院地球圏科学専攻の飯塚芳徳准教授(低温科学研究所)は、国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学大学院環境学研究科の植村立准教授、松井仁志准教授、藤田耕史教授らの研究グループと共に、国立極地研究所、琉球大学との共同研究で、南極ドームふじアイスコアに含まれる硫酸エアロゾルの硫黄同位体比(δ34S)の分析を行い、その供給源地域を解析しました。
硫酸エアロゾルは南極における主要な水溶性エアロゾル成分であり、海洋生物活動、海塩、陸域の表面など複数の起源があります。一方で、「なぜ南極の硫酸エアロゾルの沈着量は、氷期と間氷期で大きく変化しないのか?」や「氷期に陸域からの硫酸エアロゾルの供給が多いとすれば、どの地域が起源なのか?」等の未解明の問題も残されています。
本研究では、南極ドームふじアイスコアの硫黄同位体比の分析結果から、最終氷期では「陸域」を起源とする硫酸エアロゾルの寄与が大きかったことを明らかにしました。この結果は、最終氷期における硫酸エアロゾルの起源は、海洋生物活動であったという従来の有力な説と異なります。さらに、同位体比データから、南米のアタカマ砂漠周辺の高地が最も有力な供給源地域であることが分かりました。これらの結果から、極度に乾燥した低・中緯度の砂漠に存在する水溶性物質が、南極の硫酸エアロゾルの供給源の一つであることを明らかにしました。
本研究成果は、2021年12月3日付地球科学分野の国際学術誌「Earth and Planetary Science Letters」に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
氷期の南極の硫酸エアロゾルはどこから飛来したのか?~南米アタカマ砂漠からの寄与~(PDF)
2021-12-13
宇野裕美 京都大学生態学研究センター特定准教授(研究当時。現:本研究院日本学術振興会特別研究員CPD)、横井瑞士 同修士課程(研究当時。現:河合塾)、福島慶太郎 同研究員、菅野陽一郎 コロラド州立大学准教授らは、本学院生物圏科学専攻の岸田治准教授、内海俊介准教授(北方生物圏フィールド科学センター)、同雨龍研究林の職員・スタッフらと共に研究林内の希少な天然氾濫原において研究を行い、河川の氾濫が氾濫原生態系の生物多様性を維持する上で重要であることを示しました。
現在日本・世界中の多くの自然の氾濫原生態系は失われてしまいました。本研究では河川の氾濫から収束までの間、水の流れの変化と生物の応答を克明に調査し、氾濫と共に様々に形を変えながら流れ下る川の水のダイナミクスが幻の巨魚イトウをはじめとする様々な魚や両生類・水生昆虫やプランクトンなどの多様な生物が氾濫原に生息する秘訣となっていることを示しました。防災上、抑えられがちな河川の氾濫ですが、自然現象の一つとして自然界では多くの生物によって利用されているようです。
本成果は、2021年12月10日に国際学術誌「Freshwater Biology」にオンライン掲載されます。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
水の満ち引きが多様な生物の共存を実現-自然氾濫原において多くの生物の共存を可能とする河川氾濫の役割-(PDF)
2021-11-12
本学院地球圏科学専攻博士後期課程の王鄴凡さんと杉山慎教授(低温科学研究所。北極域研究センター兼務)らの研究グループは,1980年代の航空写真と最新の人工衛星データの解析から,グリーンランド北西部における氷河変動を33年間にわたって解明しました。
1985年から2018年における氷河の表面標高の測定から,全氷河の平均で氷が毎年0.6m薄くなっていることが明らかになりました。この変化を詳しく調べたところ,2001年まではほとんど変化が見られない一方で,2001年以降には毎年1.3mの割合で急速に氷が失われていました。つまり,氷河融解が21世紀に入って急激に加速したことが明らかになりました。さらに融解加速の原因を解析したところ,1990年代後半に顕著となった気温上昇に加えて,海水温の上昇,氷河の流動加速が氷河に強く影響していることが示されました。
この研究結果は,グリーンランドにおける氷の融解を正確に把握し,その原因を理解する上で重要です。特に氷河変動が始まったタイミングとその原因が特定されたことで,氷河の将来変動予測に重要な示唆が得られました。グリーンランド北西部は,日本の研究者が集中的に研究を行っている地域であり,この地域における環境変動を世界に先駆けて解明し報告したものです。
本研究成果は,2021年10月20日(水)公開のJournal of Geophysical Research: Earth Surface誌にオンライン掲載されました。なお本研究は,ArCS北極域研究推進プロジェクト及びArCS II北極域研究加速プロジェクトの助成を受けて実施されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
グリーンランドの氷河融解は21世紀から始まった~1980年代の航空写真と最新の人工衛星データから氷河の縮小を解析~(PDF)
2021-11-04
本学院地球圏科学専攻の杉山慎教授,箕輪昌紘助教(低温科学研究所)および,深町康教授(北極域研究センター)らの研究グループは,南米パタゴニアの氷河が流入する湖で20ヶ月にわたる長期観測に成功し,水温と流速の季節変化を世界で初めて明らかにしました。
夏になると氷河が盛んに融解して,冷たい融け水が湖に流れ込む様子が観測されました。この水は土砂を含んで密度が高いため,湖の底深くに沈み込んで蓄積されます。その結果,湖の深い部分では真夏に水温が最も低くなり(約2℃),逆に表面近くでは年間最高水温(約5℃)が記録されました。湖水の流速,気温・風速のデータからも,夏に湖底付近が氷河の融け水で冷やされる一方で,大気の熱と日射で暖まった水が強い風で表層付近を循環する様子が確認されました。
本研究で明らかになった水温とその季節変化は,氷河の変動メカニズムを考える上で重要です。例えば湖の中で上記の温度分布が生まれると,水温が高い表層付近で氷がよく融けますが,水温が低い中層以深では氷が融けないので氷河が水中に突き出てきます。すると水に浸かった氷に浮力が働き,大規模な氷の崩壊が起きると考えられます。また,氷河が激しく融解すると融け水が湖を冷やすので,氷河の末端部では逆に氷の融解が抑制される効果も予想されます。氷河湖の季節的な水温変化は,過去に報告されたことがなく,湖の生態系を考える上でも重要な知見になると考えられます。
本研究成果は,2021年11月2日(火)にNature Communications誌にオンライン掲載されました。本研究は,科研費基盤研究(A)(20H00186)の助成を受けて実施されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
夏に最も冷える,パタゴニアの湖~氷河が流れ込む湖で水温の季節変化を世界で初めて解明(PDF)
2021-10-27
東南極で最大級の規模を有するトッテン氷河の周辺域では,近年,氷床質量の減少が報告され,また,将来の大規模な氷床流出も懸念されています。本学院地球圏科学専攻の青木茂准教授(低温科学研究所)は,国立極地研究所の平野大輔助教,東京海洋大学の溝端浩平助教,水産研究・教育機構の佐々木裕子研究員らと共に,水産庁漁業調査船「開洋丸」および南極観測船「しらせ」により実施された大規模な海洋観測で取得した現場観測データと衛星観測データを統合的に解析し,トッテン氷河の沖合に定在する巨大な海洋渦が,比較的温度の高い海水を効率的に南極大陸方向へと輸送していることを明らかにしました。氷河末端に流れ込む暖かい海水は,氷床を下から融解することで氷床流出の引き金となるため,本成果は,氷床の質量損失が加速するトッテン氷河域での質量損失プロセスの包括的理解につながると期待されます。
この研究成果は,2021年8月6日付けで「Communications Earth & Environment」誌に公開されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
巨大な海洋渦が暖かい海水を南極大陸方向へ運ぶ 東南極トッテン氷河を下から融かす主要な熱源(PDF)
2021-10-26
大気から積雪に沈着する光吸収性粒子(元々は大気中にエーロゾルとして存在するブラックカーボンと鉱物性ダスト)は,雪面が吸収する太陽光を増加させ,融雪を加速する可能性があります。本学院地球圏科学専攻の的場澄人助教(低温科学研究所)は,気象研究所等の研究者らとともに,気象研究所で開発している世界的に見ても詳細な積雪変質モデルと領域気象化学モデルを組み合わせて,2011-2012冬期の札幌の積雪中に存在する光吸収性粒子が融雪に与える影響を国内・国外由来に分離して推定しました。その結果,同期間に札幌に到達して積雪内部に取り込まれた全ての光吸収性粒子によって消雪日が15日早められ,その内,国外由来の積雪中光吸収性粒子の寄与が約7割あることが分かりました。
この研究成果は,2021年8月21日付けでアメリカ地球物理学連合が発行する科学誌「Geophysical Research Letters」に公開されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
札幌の積雪中に存在する光吸収性粒子が融雪に与える影響を国内・国外由来に分離して推定しました(PDF)
2021-10-19
北海道大学水産学部附属練習船うしお丸は,2021年10月5日から10月13日に実施した第499次航海において,漁業被害が甚大になっている道東沖赤潮の横断観測にはじめて成功しました。昨年度より実施している厚岸沖定点の物理パラメータ(水温塩分・流向流速),化学成分(栄養塩等),植物プランクトン濃度及び種のサンプルを取得し,特に沖合の数点において,茶色から黒色に見える帯状の濃い赤潮を観測しました。本研究には本学院生物圏科学専攻の芳村毅准教授(水産科学研究院)の研究グループが参画しています。
宇宙航空研究開発機構(JAXA)が打ち上げ,運用している人工衛星「しきさい」の植物プランクトン(クロロフィル a)濃度からも,9月中旬から10月にかけて植物プランクトンが増殖し,道東沿岸に沿って南下していることが明らかになっています。本学大学院水産科学研究院は北海道厚岸漁業協同組合にこの観測データを直ちに提供し,今後の漁業被害低減に向けて相互協力していくことになりました。
今後,取得したデータの詳細な解析を進め,寒冷域赤潮の実態を解明し,将来予測に繋げていくことが期待されます。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
道東沖赤潮の横断観測にはじめて成功~漁業被害の原因となる赤潮のメカニズム解明と将来予測の可能性に期待~(PDF)
2021-10-12
本学院環境起学専攻修士課程(当時)(現:斜里町立知床博物館学芸員)の三浦一輝さんと根岸淳二郎准教授ら研究グループは,近年減少傾向にある淡水二枚貝カワシンジュガイが砂を動きにくくすることで川底の安定性を高め,川の地形や流れを変化させることを明らかにしました。川の地形や流れは生物の個体数や様々な生態系機能を決める重要な要因です。本研究は、絶滅危惧種が川の健全な生態系を支える仕組みの一端を明らかにし,絶滅危惧種の保全価値の向上につながります。
本研究成果は,2021年10月5日(火)公開のHydrobiologia誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
川に棲む二枚貝が川の地形や流れを変える?-絶滅危惧種カワシンジュガイが川底の安定性を高めることを実証-(PDF)
2021-10-01
本学院地球圏科学専攻の的場澄人助教(低温科学研究所)は,国立極地研究所の永塚尚子特任研究員を中心とする研究グループと共に,グリーンランド氷床北西部の「SIGMA-D アイスコア」に含まれる鉱物ダスト(岩石由来の微粒子)の分析を行い,過去100 年の間にグリーンランド氷床上に降下したダストの起源について,その連続的な変化を初めて明らかにしました。
アイスコアに含まれる鉱物ダストの濃度や粒径は地球環境変動の歴史を読み解くための指標となっています。さらに,鉱物ダストがどこから飛来したか,つまり,ダストの起源を明らかにすることは,過去の大気循環や供給源となる場所の環境変動を知るための重要な手がかりです。しかし,極域のアイスコアに含まれる鉱物ダストは,量が少ないためにその起源を推定することが難しく,近年の温暖期のダストの起源についてはこれまでほとんど明らかにされていませんでした。
本研究では,電子顕微鏡を用いて鉱物ダストのサイズや組成を一粒ずつ解析することで,濃度が低い時期でもアイスコア中の鉱物ダストの起源推定を可能としました。本成果により,SIGMA-D アイスコアの鉱物ダスト起源はグリーンランドの気温変化の影響を受けて変動しており,温暖な時期には雪や氷の融解によって露出した氷床周辺の堆積物に由来する鉱物ダストが多く飛来していたことが分かりました。この成果は,Climate of the Past 誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
グリーンランド氷床に飛来するダストの起源~アイスコア中の微量なダストから過去 100 年の変化が明らかに~(PDF)
2021-08-27
味覚は,何を食べるかを決定する上で重要な役割を果たします。そのひとつである『旨味(うまみ)』は,舌の上などに存在する味覚センサー分子(旨味受容体 T1R1/T1R3)を介して認識され,栄養となるアミノ酸(タンパク質)が食物中にあることを知る手がかりとなります。私たちヒトの旨味受容体は,アミノ酸の一種であるグルタミン酸に強く応答することを特徴とします。ヒトは霊長類(サル類)の仲間ですが,すべての霊長類がグルタミン酸の味を好ましく感じるわけではないようです。旨味受容体が霊長類の進化の過程でいつ,どのような理由でグルタミン酸に強く応答するようになったのかは不明でした。
今回,本学院生物圏科学専攻の早川卓志助教を含む,明治大学,北海道大学,京都大学,東京大学,日本モンキーセンター等からなる共同研究グループは,アミノ酸センサーだと考えられていた旨味受容体が,霊長類の祖先ではイノシン酸やアデニル酸などのヌクレオチドを感度良く検出するセンサーとして機能していたことを見出しました。ネズミくらいの小ささで昆虫を主食としていた霊長類の祖先が,ヌクレオチドを豊富に含む昆虫をおいしく食べるのに役立っていたと考えられます。
現在地球上には約500種類の霊長類がいます。そのうち,ワオキツネザル,ジェフロイクモザル,ブタオザル,チンパンジーなど,体が大きくなった一部の霊長類の旨味受容体は,葉に豊富に含まれるグルタミン酸に強く応答するよう進化したことが分かりました。これらの体が大きくなった霊長類は,昆虫では補え切れないタンパク質の量を確保するために,葉をたくさん食べるようになったと考えられています。本来,葉は苦くておいしくないはずですが,私たちの祖先が旨味受容体をヌクレオチドセンサーからグルタミン酸センサーへと変化させたことで,新たなタンパク質供給源として,葉をおいしく利用できるようになったと考えられます。
なお,本研究成果は,2021年8月26日(木)公開のCurrent Biology誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
霊長類におけるグルタミン酸の旨味の起源―体の大きな霊長類は旨味感覚で葉の苦さを克服―(PDF)
2021-08-25
本学院生物圏科学専攻の柴田英昭教授(北方生物圏フィールド科学センター)は,農研機構らの研究グループとともに,日本の全ての人間活動と環境を対象に2000年から2015年の窒素収支を解明し,大気や水域への窒素排出の実態を明らかにしました。その結果,国民一人当たりの廃棄窒素は年間41~48 kgで,同時期の世界平均の約2倍であることや,廃棄窒素の発生量に対して環境に排出される反応性窒素は1/3程度に抑えられていることなどが明らかになりました。本成果は,将来世代の持続可能な窒素利用,すなわち,肥料や工業原料としての窒素の恩恵を保ちながら,環境の窒素汚染を防ぐ技術の開発や政策の立案に役立ちます。
なお,本研究成果は2021年6月9日公開のEnvironmental Pollution誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
日本の2000年から2015年の窒素収支を解明-持続可能な窒素利用の実現に向け基礎情報を提供-(PDF)
2021-07-16
本学院環境起学専攻の沖野龍文教授と薬学研究院の松田研一助教,脇本敏幸教授らの研究グループは,多剤耐性菌などに対する抗菌活性を示す環状ペプチドのアルギシクラミド類を,湖沼にアオコを形成する藍藻から発見しました。環状ペプチドに含まれるアミノ酸アルギニンのグアニジン部分の窒素にプレニル基が2個結合していることが構造の特徴です。ペプチド中のアルギニンをプレニル化する酵素は明らかにされていなかったため,研究グループは,この藍藻の遺伝子解析を行い,アルギシクラミド類の生合成酵素の解明に取り組みました。
その結果,AgcFと名付けたプレニル基転移酵素を見いだしました。化学合成したプレニル基をもたないアルギシクラミドCとの酵素反応を試みた結果,プレニル基1個のアルギシクラミドBを経て,プレニル基2個で抗菌性をもつアルギシクラミドAに変換することが確認されました。アルギシクラミドCのアルギニンの代わりに,トリプトファンやリシンなどの異なるアミノ酸に置換した化合物や,アルギシクラミドCと同じアミノ酸配列でありながら環化していない直鎖の化合物を合成して,AgcFとの酵素反応を試みましたが,プレニル化は進みませんでした。一方,プレニル基が2個つながったゲラニル基を取り込むことも,この酵素は可能でした。この酵素の立体構造を予測したところ,活性部位の入り口部分が類似の酵素に比べて広くて,より大きなゲラニル基を取り込めると予想されました。
分子量500~2,000の中分子は新しい医薬品の候補として期待されています。本研究で発見した環状ペプチドもその範疇に入りますが,一般に生体膜を通過しにくく細胞内に入り込めないという問題があります。プレニル化は、脂溶性を高めて生体膜を通りやすくすることができます。実際,プレニル基が2個結合したアルギシクラミドAが最も高い抗菌性を示しました。本研究で発見したプレニル基転移酵素を使って,医薬品候補環状ペプチドのアルギニンをプレニル化することでその効果を高めて実用化を目指すことが期待されます。
なお,本研究成果は,2021年6月28日(月)公開のJournal of the American Chemical Society誌に掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
環状ペプチドの抗菌性を高める新規酵素を発見~中分子ペプチド医薬品創製への貢献に期待~(PDF)
2021-07-16
本学院地球圏科学専攻の大島慶一郎教授らの研究グループは,西部北太平洋の高い生物生産を支えている親潮中層水が,温暖化と18.6年周期潮汐変動の両方に強く影響を受けることを明らかにしました。これらの変動の大きな要因は,親潮中層水を作る2つの水塊,西部亜寒帯水とオホーツク海中層水の混合の割合の変化によります。長期的には低温のオホーツク中層水の占める割合が40年で30%も減少して親潮中層水は高温化しており,これは温暖化による海氷生成の減少によりオホーツク海を起点とするオーバーターンが弱化したことによると考えられます。潮汐が強い年代は,より低温のオホーツク海中層水の流出が増加し,潮汐の強さは温暖化と逆に作用(低温化)することもわかりました。
本研究によって,潮汐が弱くなる2020年代中盤からの10年間は弱化する潮汐の効果と温暖化の効果が相乗して一気に大きな変化(親潮中層水におけるオホーツク海中層水の割合が減り,水温が高くなる)が起こりうることも予想されます。
なお本研究成果は,2021年7月15日(木)公開のScientific Reports誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
海の恵みをもたらす親潮中層水の経年変動機構を解明~2020年代中盤からの10年間に大きな変化があると予測~(PDF)
2021-07-13
本学院地球圏科学専攻(低温科学研究所)の杉山慎教授,青木茂准教授,箕輪昌紘氏(当時)らの研究チームは南極ラングホブデ氷河を掘削し,厚さ234~412mの棚氷の下に広がる海を直接観測しました。その結果,棚氷底面での氷融解とそのメカニズムを明らかにしました。
近年,南極氷床が氷を失っており,海水準の上昇につながる地球環境変動として注目されています。氷床の周縁では氷が海に張り出して棚氷を形成し、その底面が海の熱で融けるプロセスが氷床変動の引き金と考えられています。しかし,厚い棚氷の下へ海水がどのように流入し,どれだけ氷を融かしているのか,その測定は非常に困難で理解が遅れています。本研究では,研究チームが開発した熱水掘削システムを用いて,ラングホブデ氷河の棚氷を4地点で掘削し,棚氷下の海水温,塩分,循環を直接観測しました。その結果,海水は結氷温度よりも最大1℃ほど暖かく,棚氷の全域で氷の融解が示されました。また棚氷の全域における測定によって,これまで予想されていた海洋循環の確認に成功しました。測定された貴重なデータは,棚氷下の海洋循環と底面融解の物理プロセスを検証し,氷床数値モデルの精緻化に貢献するものです。
本研究成果は,2021年7月9日(金)公開のNature Communications誌にオンライン掲載されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
南極の氷河の下で海と氷を直接観測~熱水掘削によって氷床融解のメカニズムを解明~(PDF)
2021-07-11
本学院生物圏科学専攻の仲岡雅裕教授(北方生物圏フィールド科学センター)らの研究グループは,東~東南アジアに分布する熱帯性の海草藻場の多くが2000年代以降減少していること,現状の海洋保護区による保全が不十分であることを明らかにしました。
海草藻場は,多様な魚介類の生息場所となると共に水質を浄化する機能をもつなど,沿岸域で重要な役割を果たしています。しかし,海草藻場は世界各地で減少しています。研究グループは東~東南アジアの13か国・地域を対象に,2000年以降に記録された海草藻場の分布に関する情報を新たに2,720件収集し,海草藻場面積の時間的変化を解析するとともに,海洋保護区による保全状態を国・地域ごとに比較しました。その結果,多くの海草藻場では2000年以降も面積が減少しており,その減少率は平均で年 4.7%であることが判明しました。また,厳密に運用されている海洋保護区に含まれる海草藻場はどの国・地域でも5%以下と非常に少ないことがわかりました。
本研究の成果は,これまで情報が欠損していた東~東南アジアの海草藻場をはじめとする海洋生態系やその海洋生物多様性の保全計画の策定に大きく貢献することが期待されます。
なお,本研究成果は2021年7月8日(木)公開のFrontiers in Marine Science誌にオンライン掲載されました。
アジアの熱帯性海草藻場の詳細な分布と保全状況を解明~年5%の割合で減少する貴重な生態系を早急に保全する必要性を指摘~(PDF)
2021-07-10
本学院地球圏科学専攻のEvgeny A. Podolskiy助教(北極域研究センター),杉山慎教授(低温科学研究所)および理学研究院の村井芳夫准教授,北極域研究センターの漢那直也研究員(現東京大学海洋研究所)らの研究グループは,グリーンランド・ボードイン氷河の直前で,海底地震計を使った観測に世界で初めて成功しました。観測された地震波ノイズの時間変化から,氷河の流動変化が推定できることを初めて明らかにしました。
氷河末端から約640mの海底に海底地震計を,氷河と陸上に GPS(全地球測位システム)受信機と地震計を設置して,地震波ノイズと氷河の流動速度を比較したところ,特に海底の地震波ノイズ振幅と流動速度の間に高い相関があることを発見しました。このことから,地震波ノイズが,氷河がすべる時に生じる微動であることが明らかになりました。
氷河の末端付近はアクセスと機材の設置が困難で,氷の破壊や強風によるノイズの影響を受けるため,流動の測定が困難です。これに対して,海底での観測によって,これらの弱点を克服することが可能になります。
本研究が提案する新しい手法により,グリーンランドにおける氷河から海に流入する氷と融け水のモニタリングが可能となり,その変動要因の解明が期待されます。
本研究成果は,2021年6月24日(木)公開のNature Communications誌にオンライン掲載されました。詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。
世界初!海底地震計を使い,氷河流動の検出に成功~微動を使った新しい氷河観測手法を提案~(PDF)