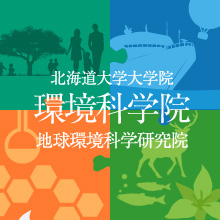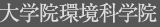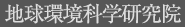屋久島世界遺産地域でヤクシカが減少している!
2021-05-21本学院生物圏科学専攻の揚妻直樹准教授(北方生物圏フィールド科学センター)らの研究グループは,屋久島西部の世界自然遺産地域内に生息するニホンジカの固有亜種・ヤクシカの個体群が,2014年以降,減少傾向にあることを明らかにしました。全国的にシカの急増が伝えられている中で,人間による捕獲や駆除がないにも関わらず,シカが継続的に減少することがわかったのは初めてです。
屋久島には,もともとオオカミなどの中・大型肉食動物が分布しておらず,ヤクシカは天敵が不在のまま進化してきました。また,西部の世界遺産地域は,過去およそ50年間シカの捕獲が行われていないため,自然なシカの生態を知ることができる日本に残された希少な場所となっています。
この地域のシカの数は調査を開始した2001年から2014年まで年率9%で増加していました。ところが,それ以降は,年率マイナス15%で減少し始めました。この地域のシカが地域外へ移出する割合は多めに見積もっても年3.5%であったことから,シカの数が増加から減少に転じた原因は,移出ではなく自然要因による死亡率の増加だと考えられました。これらの結果は自然生態系がシカ個体群を調節している可能性を示すものです。ただし,シカ個体群の変動を理解するには数十年単位の継続データが必要であり,現在の減少傾向もいつまで続くのかはわかりません。今後も捕獲することなく,注意深く見守り調査することで,この希少なシカ個体群の理解へと繋げていくことが重要です。
現在,屋久島の世界自然遺産地域では,生態系保護を目的として,駆除によるシカの個体数調整が行われています。しかし,本研究は,自然生態系の調節機能を活かした,人為によらないシカ管理の可能性とその必要性を示唆するものといえます。
なお,本研究成果は,「保全生態学研究」に掲載予定で,2021年4月20日(火)にオンラインで早期公開されました。
詳細については,以下のプレスリリースをご覧ください。