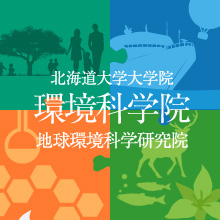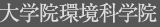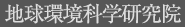2021年度公開講座 環境との調和: 化学を通して見える世界
2021-06-08令和3年度公開講座 環境との調和: 化学を通して見える世界
公開講座開催にあたって
《北海道大学大学院地球環境科学研究院長 大 原 雅》
化学は物質の成り立ちや性質を知る学問分野で,環境破壊,エネルギー問題,有害物質による健康被害など,私たちの前に立ちはだかる様々な問題を解決するための基盤です。物質は周りの環境と調和し,また外部からの刺激に応答するなど,それが置かれた環境の影響を強く受けるため,その理解は物質の成り立ちや性質を理解する上で極めて重要です。また,人をはじめとする生物は,化学物質を通じて他の種や環境と調和しながら生命を営んでいます。本講座では微小な世界で起きている現象を化学の視点から基礎的に理解し,さらに化学が地球規模の問題に対してどのように貢献し,今後,どのような貢献が期待できるのかについて,本大学院に所属する6名の教員が最新の研究成果を含めてわかりやすく解説します。今年は,初めてのオンライン講座ですが,多くの皆さまの受講をお待ちしています。
【公開講座要領】
- 開講時期 令和3年8月23日(月)~9月27日(月)(毎週月曜日※第5回のみ火曜日開催)
- 実施場所 オンラインで実施
- 受講資格 満18歳以上の方であればどなたでも受講できます。(学歴不問)
- 定 員 先着70名
- 受 講 料 無料
- 修了証書 全6回の開講のうち,4回以上受講した方には、最終講義終了時に修了証書を交付します。
- 主 催 北海道大学大学院地球環境科学研究院
- 後 援 札幌市教育委員会
【申込要領】
- 申込期間 令和3年7月9日(金)~7月21日(水)【必着】
- 申込先 北海道大学環境科学事務部教務担当
〒060-0810 札幌市北区北10条西5丁目
電話 (011) 706-2204
E-Mail kyomu (at) ees.hokudai.ac.jp - 申込手続 申し込みは,下記の手順を全て行うことで完了します。
1.申込書【様式】をダウンロードしてご利用下さい.
2.先着順(定員70名)に受講許可の通知を送付
3.手続き完了 - 詳細は,パンフレット内「申込要領」を参照願います。
【その他】
- 本公開講座は、2021年度前期道民カレッジ連携講座(環境生活コース9単位)の指定を受けています。
- 本公開講座は特定の回のみの受講も可能ですので、希望される方は上記申込手続の「1申込み」の際にお申し出ください。
- 次回の講義資料はこちらからダウンロード願います。(9/24更新) 資料のパスワードは、受講者の皆様宛郵送しております、受講許可通知文に記載しています。
北海道大学大学院地球環境科学研究院 公開講座
《環境との調和:化学を通して見える世界》
※講義題目をクリックするとテキストが閲覧できます。(講義終了後に掲載します)
第1回 8月23日(月) 講師:触媒科学研究所 教授 大谷 文章
講義題目:「光触媒による環境浄化とエネルギー変換」
概 要:植物の光合成を考えてもわかるように光は生物が生きていくのに不可欠なものですが,太陽からふりそそぐ膨大な量の光は,環境浄化やエネルギー創出などの化学反応にも利用できます。代表例が光触媒反応です。すでに,日常生活のなかにも光触媒の応用製品がふえてきています。たとえば,ガラスや壁の光触媒コーティングや空気清浄機がそうです。これらは,光触媒反応によって屋外では汚れをふせぎ,室内では汚染空気を浄化や抗菌・抗ウイルス作用をしめします。また,光触媒によって水を分解し,燃料となる水素をとりだす研究も行われています。ここでは,これらの光触媒の基礎とその可能性についてやさしく解説します。
第2回 8月30日(月) 講師:大学院地球環境科学研究院 教授 小西 克明
講義題目:「プラスチック社会と環境」
概 要:プラスチックはポリ袋だけでなく家電製品,自動車など生活の隅々まで浸透していて,現代の社会で欠くことができない身近なものになっています。その一方で,有料レジ袋をはじめプラスチックの削減と再利用を促進する動きが高まるとともに,「マイクロプラスチック」「海洋プラスチック」という言葉がマスコミに頻繁に登場するようになりました。ここでは,科学的視点からプラスチックがどういうものか改めて理解し,国内外の現況ならびにサステナブル社会実現のための取組を解説します。
第3回 9月6日(月) 講師:大学院地球環境科学研究院 教授 小野田 晃
講義題目:「バイオテクノロジーによる環境調和」
概 要:地球の未来を見据えて持続可能(サステイナブル)な発展を続けるために,環境調和型技術としてバイオテクノロジーをより一層利用すべき時代を私たち人類は迎えています。今後は,汚染修復(レメディエーション)ではなく,汚染をひきおこさない製造プロセスと製品(プリベンション)を満たす技術が必要です。私の身の回りの物質の製造,資源,そして,環境浄化で活躍するバイオテクノロジーについて,最近の技術革新も交えて紹介します。
第4回 9月13日(月) 講師:大学院地球環境科学研究院 准教授 山田 幸司
講義題目:「環境にやさしい化学の光:LED,有機EL,蛍光,化学 発光」
概 要:省電力の観点から私たちの身の回りの照明は,白熱電球などからLEDや有機ELに 急速に切り替わりつつあります。これらの発光材料は化学の発展によって安価に大量生産することが可能になりました。また,人工的に生産される蛍光色素や化学発光色素も主にバイオテクノロジーの分野で活用されています。コロナ禍で話題となったPCRの技術などと組み合わせて医療の分野にも進出しつつあります。この講義ではこれらの技術に関わるノーベル賞級の研究との関わりについてお話致します。
第5回 9月21日(火) 講師:大学院地球環境科学研究院 准教授 梅澤 大樹
講義題目:「生物が生活のために利用する有機化合物」
概 要:私たち人類は,医薬品やプラスチックなど有機化合物を製造,利用して便利な生活を営んでいます。陸海,動植物問わず生物も,長い進化を通じて様々な有機化合物を見出し,作り,利用して生活を営んでいます。異性を誘引するフェロモンや外敵から身を守るための毒や防御物質などがよく知られています。これら有機化合物がどのような仕組みでそのような作用を発現させるかを理解することは,人類が持続可能な社会を営んでいくうえでとても参考になります。このような有機化合について紹介・解説するとともに,海洋生物の機能を模倣した私たちの研究についても紹介します。
第6回 9月27日(月) 講師:大学院地球環境科学研究院 准教授 加藤 優
講義題目:「水素エネルギー社会実現へ向けた燃料電池開発」
概 要:現代社会では石油や石炭などの化石燃料を燃焼することでエネルギーを得ることができますが,同時に排出される二酸化炭素の大気中濃度の上昇に伴う気候変動が問題となっています。化石燃料に代わる次世代燃料として,二酸化炭素を排出せずに,水とエネルギーを得ることができる水素(H2)が着目されています。水素をベースとしたクリーンかつ持続可能なエネルギー社会を実現させるためには,水素から発電する燃料電池の高効率化および低コスト化が水素必要不可欠です。本講演では,燃料電池の中でも家庭用燃料電池(エネファーム)や燃料電池車に搭載されている固体高分子形燃料電池の動作原理や最新の研究開発動向等を紹介します。
講義時間は,毎回18:00~19:30です。
※講師の都合により,講義日が変わる場合があります。