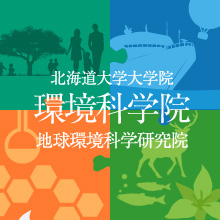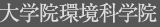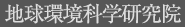令和7年度公開講座
2025-05-13【公開講座概要】
1.開講日程 令和7年8月26日(火)~9月24日(水)
18:00~19:30(質疑応答時間含む)
2.実施場所 地球環境科学研究院内講義室(対面)及びオンライン
3.受講資格 高校生または満18歳以上の方であればどなたでも受講できます。
4.受講方法 対面講義 70名 / オンライン講義 100名
(どちらかを選択してください。併用受講はできません。)
5.受講料 5,000円
※大学生・高専生・高校生は無料です。(生徒手帳コピー等の提出が必要)
※納入後の返金はできません。
6.修了証書
3回以上受講した方のうち希望者には、最終講義終了後に修了証書を交付します。
【申込方法】
1.申込方法
以下の①及び②を完了することで受講申込みが完了となります。
詳細はパンフレットをご覧ください。 → パンフレットをダウンロード
① 仮申込み(受講登録):令和7年6月9日(月)~ 7月7日(月)【必着】
Googleフォームからお申し込み願います。 https://forms.gle/mfUskFpSE1YoTkxK7
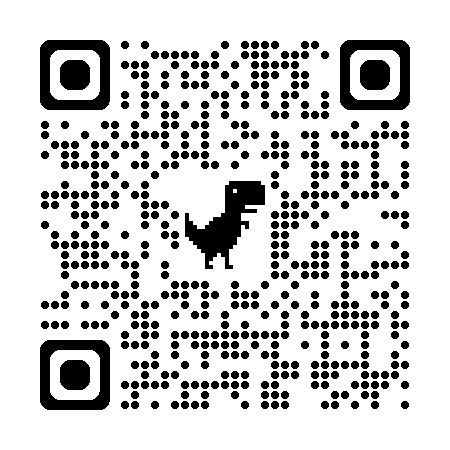
② 本申込み
①の「仮申込み」により受講可となった方へ7月下旬までに「本申込み」に必要な
手続書類(本申込書・受講料振込用紙等)を郵送します。
手続書類が届きましたら、同封されている受講料振込用紙(払込取扱票)により
金融機関にて受講料を納付の上、手続要領に基づき必要書類を送付してください。
※大学生・高専生・高校生は、受講料納付は不要です。生徒手帳・学生証のコピー等を提出してください。
※「本申込み」受理後、受講許可の通知を送付します。
※本申込みの手続き完了をもって受講申込み完了となりますので、ご注意ください。
※定員充足により受講いただけない方へもその旨お知らせします。
【講義日程】
8月26日(火) 触媒科学研究所 中島 清隆 教授
植物資源から工業製品をつくる科学技術
食品廃棄物、農業廃棄物、廃木材、古紙などありふれた植物由来品から基礎化学品を製造する革新的な科学技術を紹介します。この技術開発の進展は石油依存の脱却のみならず、北海道を含む農業地帯を化学工業活動の中心地へと変動させることができます。「次世代の持続可能な科学技術」に関する最新の研究成果や今後の展望をわかりやすく紹介します。
9月2日(火)大学院地球環境科学研究院 梅澤 大樹 准教授
天然有機化合物とは:環境にやさしい船底防汚剤開発に向けた研究
紅麴問題で報道されたプベルル酸を始めとする天然有機化合物について紹介します。天然有機化合物は生物が作る化合物です。2024年3月に発覚した紅麴問題では有害物質(毒)としての側面が注目されましたが、有益なもの(薬の候補など)も多数知られており、歴史や応用なども解説します。
9月9日(火)大学院地球環境科学研究院 大友 亮一 准教授
大気環境の保全に貢献する触媒技術
人為活動によって生成する排ガスには多くの健康被害や環境汚染の原因物質が含まれます。これらの物質を大気中に放出することは法律によって禁止または規制されています。例えば、自動車などの排ガスは、触媒を用いた高度な技術によって“キレイ”な排ガスに変えてから大気に放出されています。今回は排ガス浄化を担う触媒技術について紹介します。
9月16日(火)大学院地球環境科学研究院 廣川 淳 准教授
大気酸化反応の環境科学
空気中に存在する多くの微量成分が、酸化反応を通して別の物質へと変化します。このような大気酸化反応は、酸性雨、光化学スモッグ、気候変動などの大気環境問題と密接に関わっています。本講義では大気酸化反応のメカニズムと環境影響を概説するとともに深い理解を目指した最新の研究をご紹介します。
9月24日(水)大学院地球環境科学研究院 八木 一三 教授
水素・酸素と水で循環する水素社会
2025年に道内でも定置型水素ステーションが設置され、水素社会の到来が近づいています。既に家庭用燃料電池(エネファーム)の普及も進んでいます。しかし今なお水素は化石燃料を元に作られるグレー水素が多く、再生可能エネルギーを元に作られるグリーン水素への移行が必要です。将来の水素社会に向けた取り組みや先端技術開発をお話しします。