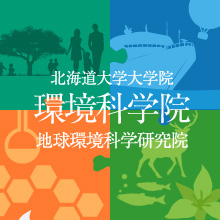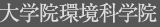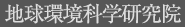環境科学院「見える化」システムを活用する環境負荷低減実現プロジェクトが提案する省エネ対策掲載
2012-06-04環境科学院「見える化」システムを活用する環境負荷低減実現プロジェクトが提案する省エネ対策
快適な学習環境・研究環境を維持しつつ、高度な研究設備を活用していきながら、環境負荷低減を目指します。たとえ研究機器であっても、無駄に電気をつかっていないか考えることが重要です。
照明やエアコンなどが省エネのポイントとなりますが、共用の部屋、講義室、セミナー室、廊下などは、特に誰かが管理しているというわけではなく、利用者である皆さんがその時その時の状況に応じてON/OFFしてください。(講義棟の暖房を除く)
電力消費の多い機器、使用時間の長い機器も大きな省エネのポイントです。少しの運用方法の変更が大きく効きます。何が電力を使うのか知ることから始めましょう。
1.エアコン
環境科学院のエネルギー消費のうちエアコンが占める割合は3分の1です。エアコンの適切な使用は、全体の環境負荷低減に対して大変効果的です。
夏の北海道は外気が涼しいことが多いので、窓を開けたり、普通換気で外気を取り入れたりしましょう。廊下の窓(やA棟の自動扉および渡り廊下の扉)をあけて建物に涼気を取り込むことは効果的です。
複数台のエアコンが設置されている大きな部屋では一旦涼しくなれば、一部のエアコンだけで冷やした方が効果的です。
エアコンフィルタークリーニングは必須です。初夏と年末(大掃除に合わせて)実施してください。その際、ほこりがたくさんたまっているようであれば、さらに頻繁に実施してください。ほこりがそれほどたまっていなければ年2回で十分です。複数の研究室で共用している部屋は、省エネ対策も甘くなりがちです。部屋の管理責任者を中心にエアコンの季節に応じた設定、クリーニングをお願いします。
講義棟(D棟)については、夏と冬で運用が違います。集中管理によって冬期間は使用時間帯に合わせて暖房を入れています。タイムプログラムを組んでいますので、使用後も切らないでください。夏の間の冷房は、使用者がON/OFFしてください。
研究機器・コンピュータを終日稼働する関係で夜間あるいは休日のエアコンが必要な場合があります。その場合でも、その必要性をよく吟味してください。例えば、ある一定温度以下にしなければならない部屋では、冬期間の不在時にはエアコンの必要はないかもしれません。共用の部屋で漫然とエアコンを24時間稼働させることなく、責任者が検討して必要に応じて使ってください。また、共用の部屋のユーザーがエアコンの過剰な使用を感じる場合は、部屋の責任者に相談してください。将来的には、エアコンの終日稼働が必要な機器は、なるべく共用の部屋にまとめていくことが望まれます。新規購入時に設置場所をそのような観点も含めて検討してください。
2.冷蔵庫・冷凍庫
冷蔵庫・冷凍庫・恒温インキュベーターは24時間使用するものなので、積算の消費電力量は非常に大きくなります。残念ながら見える化データでも集計できませんが、1割から2割を占めると予想されます。
冷凍庫の設定温度を5〜10度上げるだけでも大きく消費電力が下がります。例えば−40℃に設定しているフリーザーを−30℃に下げることは可能ではないでしょうか。
一般的に小型あるいは10年以上前の冷凍庫冷蔵庫はエネルギー効率が悪いです。したがって、予算に余裕があれば古い機器を更新あるいは集約してください。ただし、実際にどの程度省エネになるかどうかは機器別に確認する必要があります。省エネ対策を主な理由とする更新の場合は注意深く検討してください。多数の冷凍庫冷蔵庫を使っている研究室では、小型の古い機器の使用をやめて、大型機器にサンプルなどを集約することも検討下さい。(9.居室の項も参照)
3.照明
残念ながら見える化データでも集計できませんが、照明による電力消費もかなり大きいと予想されます。
A棟の廊下をはじめとしてLEDおよび人感センサーが設置されています。また、人感センサーが設置されていないところでも、廊下は消灯することが徹底されている現状は望ましい状況です。しかし、暗すぎて事故が起きないよう必要に応じて照明を点灯してください。大きな部屋では、状況に応じて部分点灯してください。特に昼間は、窓側の照明が不要かもしれません。また、不在時に点灯しているのは一番の無駄です。不在時の消灯を徹底しましょう。
B棟では、蛍光灯が3連でついているところがあります。エコ改修により高効率型に変わっていますので、2本でも従来の3本とほぼ同じ明るさが得られます。ぜひ中央の1本を間引きしてください。また、他の場所で2本のうち1本だけ間引く場合には、ダミー管(例えばコクヨのカットワン3000〜4000円)を入れる必要があります。
4.ドラフトチャンバー
ドラフトチャンバーは1台あたりドライヤーの半分の電気が常時使われていると考えてください。そのくらい消費電力が大きいです。一方、化学物質を使う研究室ではドラフトを適切に使って作業環境を維持することは非常に重要なことです。必要に応じてドラフトをON/OFFしてください。夜間も使用しなければならない研究室もあるようですが、排気吸着式薬品庫の使用なども検討してください。新規購入あるいは更新の際は、局所排気システムあるいは省エネ仕様のドラフトチャンバーを購入してください。
5.給湯器
A棟の給湯器は、畜湯式です。1台あたり20Lのお湯が設定温度にタイマーで設定された開始時間までに到達するよう沸かされます。各部屋で必要な温度に設定してください。また、終了時間をすぎてもすぐに冷めるわけでなく、短い時間で温め直せますので、あまり余裕をもたずにタイマーを設定してください。もちろん、毎日使うわけでない給湯器の電源は切って水抜きしてください。なお、60℃以下に設定すると、大型の貯湯槽などに比べて頻度が少ないですが、レジオネラ属菌の繁殖が報告されています。(9.居室の項も参照)
6.換気
換気も意外に電気を消費します。例えば、A棟で実測したところによると、60平方米に設置されている4か所の換気(強の設定)で300W以上の電力が常時消費されていました。弱の設定で半分です。ただし、実験棟や管理棟などの旧型は10分の1以下です。基本的には室内の二酸化炭素濃度1,000 ppm以下となるように換気することとされています。空気がフレッシュでないと感じたら換気し、特に感じなければ換気しなくてよいと思われます。したがって、夜間帰宅後の換気は不要です。
7.講義室・セミナー室の照明・エアコン・換気
D棟(講義棟)の冬期間のエアコンを除いて、使用者が必要に応じてスイッチを入れ、使用後は切ってください。使用人数と部屋の大きさに応じて部分点灯も可能なはずです。
8.建物の設備
「見える化」データにより、建物の設備に非常に多くの電力が消費されていることがわかっています。そのため、私達は現在エアーハンドリングユニット(外調機)、ロードヒーティング、ガスボイラーの稼働時間 運用方法の改善に取り組んでいます。
9.居室(電気ポット・冷蔵庫)
居室に冷蔵庫が必要以上にありませんか。台数を減らすことができれば確実な節電です。給湯関係も電気を消費します。電気ポットの代わりに電気ケトルで必要な時に必要な量を沸かすことを検討してください。
10.トイレのヒーター
建物の断熱がよいので、一般的には必要ありません。もし、真冬の時期に必要であれば、非常に弱い設定で使ってください。また、必要ないのに電源が入っていると感じた時は、特に断らず切って構いません。
11.冷却機器
実験機器のうち、冷却水循環装置などの冷却機器は電気を大量に消費します。フィルタークリーニングをすることは節電にも装置の故障を防ぐためにも重要です。エアコンよりまめにクリーニングしてください。冷却水循環装置の新規購入の際は、省エネ仕様を選んでください。
12.省エネ仕様の機器
省エネ仕様は一般的に効果ですが、購入の際には是非検討してください。冷却水循環装置の他に、乾燥機、ガスクロマトグラフなど加熱だけの機器でも断熱性能向上による省エネ仕様があるようです。照明付き機器についてもLEDが使われています。
13.パソコン
スリープ機能を設定しておけば、簡単に節電できます。ノートパソコンのACアダプタは、電源が切れていても電力を消費します。スイッチ付きの電源タップを使用すれば、待機電力を簡単に削減することができます。下記の情報も参考になります。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/windows/gg715287
14.サーバー
情報基盤センターのクラウドサービスを利用することで、研究室個別のサーバーを停止することが可能になります。利用料金がかかりますが、教育・研究に支障がなければ使用を検討してください。環境科学院だけでなく、北大トータルの節電に寄与します。スペースも広がります。
15.ワットモニター
研究室の電力消費の状況を知ることは重要です。ワットモニターを事務室会計係で借りることができます。ワットモニターを使えば、瞬間的な消費電力はもちろんのこと、例えば1週間くらいの積算電力量も測定できます。ワットモニターを複数借りて、気になる電気機器(コンセントにつながっている機器)に1週間くらいつけてみると、大体の状況が把握できます。なお、200Vの装置などの消費電力を測定したい場合はご相談下さい。
その他の節電に関する情報がありましたら、お知らせ下さい。あるいは提案もお待ちしています。
沖野龍文 内線4519 e-mail: okino@
@のあとにees.hokudai.ac.jpをつけてください。