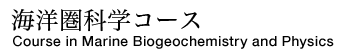研究室紹介

海洋環境と生物生産の関係の研究してます。最近は北海道沿岸域の基礎生産と海洋環境の関係について研究を行っております。北海道沿岸域には環流系・暖流系の様々な海流が流れ込み、陸域からも河川などを通して栄養塩が流入しているため、海域によって基礎生産性は大きく異なります。そこで陸域の土地利用形態(農地、森林、酪農など)を考慮に入れ、海域ごとの生産性の違いについて明らかにすることを目的としております。
先生からのメッセージ

これまで「海洋および陸水域の生物生産と化学成分相互作用の研究」を一貫して行ってきました。その中の代表的な研究として、必須微量金属の植物プランクトンの生長及び生理機能、植物プランクトンブルームに関わる物質循環とエネルギー転送、鉄添加による海洋生物生産の加速と炭素循環(いわゆる鉄散布実験)などがあります。現在は、亜寒帯域の沿岸域における生物生産に関わる研究を行っています。それには、河川や地下水が与える沿岸域の生物生産への影響評価があり、具体的には陸域の土地利用形態が沿岸域に流入する栄養塩濃度や組成にどのような影響があるのかを現地調査、堆積物コアの分析、モデル計算などにより明らかにしています。また、北海道・東北の主要な水産資源であるホタテ漁業と生物生産の関係についても、オホーツク海、噴火湾、陸奥湾などで研究を行っています。いろいろな自然界の営みの仕組みをまだ人類は完全に理解していません。特に海洋については、未知なるテーマがたくさん眠っています。その一つを自分の手で解明する「どきどき、わくわく」を経験してみませんか?
現在の研究テーマ
- Isotopic shifts between the diet and tissue of Japanese Scallop in Mutsu Bay
- 陸奥湾における窒素態栄養塩の循環過程
- 生物起源ケイ素堆積量から推定する陸奥湾における基礎生産量の歴史的変遷
- 日本海沿岸域における対馬暖流水の変質過程
- オホーツク海北海道沿岸域における生物起源粒子の生成と鉛直輸送
- 噴火湾ホタテ養殖における付着生物の影響
近年の博士論文の題名
- 平成20年度
- Influence of riverine nutrient fluxes on primary production dynamics in Ishikari Bay, subarctic oligotrophic coastal environment of Japan(亜寒帯貧栄養性石狩湾における基礎生産動態に及ぼす河川起源栄養塩の影響評価)
- 平成21年度
- Stable isotopic ecology of the Japanese Scallop Patinopeten Yessoensis (Jay, 1857) (日本産ホタテガイPatinopeten Yessoensis (Jay, 1857)の安定同位体についての生態学的考察
近年の修士論文の題名
- 平成18年度
- Food sources and requirement of the Japanese scallop, Patinopecten (Mizuhopecten) yessoensis (Jay) in two habitats examined using stable isotope analysis(安定同位体を用いた日本産ホタテガイ(Patinopecten (Mizuhopecten) yessoensis (Jay))の餌起源と要求量に関する研究)
- 十勝川水系からの栄養塩類供給が沿岸域の基礎生産構造へ与える影響
- 河川プルームが石狩湾の基礎生産環境に及ぼす影響とその季節変化
- 平成19年度
- 北海道亜寒帯域貧栄養内湾における微生物食物網のダイナミクス
- 北海道沿岸域にもたらされる河川起源栄養塩フラックスの見積もりと歴史的変遷
- 平成20年度
- 土地利用形態を考慮した流出解析モデルによる十勝川水系の栄養塩供 給機構の解析
- 噴火湾の従属栄養細菌に対するウイルス溶菌の影響
- 海洋堆積物中の生物起源シリカを指標とした北海道沿岸域の基礎生産 力の歴史的変遷
- 平成21年度
- 噴火湾の底層水中における窒素態栄養塩の硝化過程の定量的考察
- 平成22年度
- 噴火湾における親生物元素の初期続成作用における分解過程と堆積フラックスの歴史的変遷
卒業生の進路
- 就職先
- JA全農, 北斗市行政職員, 北海道大学事務職員, (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構, (株)大丸松坂屋百貨店, DOWAホールディングス(株), JFEエンジニアリング(株), (株)エコニクス, (株)マクロミル, (株)テクノ菱和、(株)片山化学工業研究所, 北海道公立高校教職員
- 進学先
- 東京大学大気海洋研究所, 京都大学農学研究科