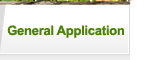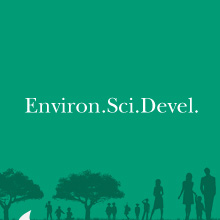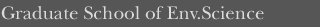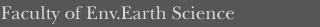2024年度沼口賞受賞者および選定理由
2025-03-252024年度沼口賞
氏名: 猪又 雅史(Masafumi Inomata)
題目: 都市近郊山地における登山道地形の特徴と利用の分析-札幌市藻岩山を例に-
氏名: 齋藤 淳也(Junya Saito)
題目: Does removal of pleopods provide an easy sterilization method for invasive
crayfish? (腹肢の除去は、侵略的外来種のザリガニを簡単に不妊化する手法となるか?)
=========================================================================
氏名: 猪又 雅史(Masafumi Inomata)
題目: 都市近郊山地における登山道地形の特徴と利用の分析-札幌市藻岩山を例に-
【選定理由】
本研究は、登山やトレイルランニング等のアウトドアレクリエーションの場としての都市近郊山地に着目し、その登山道の自然環境や利用状況を定量化することで、地形条件と利用頻度との関係など、自然と人との相互作用を系統的に明らかにした。そのために携帯端末のモバイルレーザ測量などによる現地調査に基づく最新の高精細3次元地形情報を活用し、また登山道の通行実績を示す集計された人流データを、これも現地調査による検証とあわせて、意義のある空間統計解析を行った。地形情報と人流データを組み合わせた、自然と人間の相互的な作用を明らかにする、革新的な分析結果を得ることができた。
都市近郊山地における登山道研究は未だ途上であり、本研究論文はその先駆けとしての位置付けを得られるものである。登山道の地形的特徴から、人流データに基づく利用状況の定量的・統計的評価、またそれらの相互作用を、地理空間情報科学の手法も駆使しながらわかりやすく図示するとともに、個別の議論から、総合的な議論を通して、登山道の最適な維持管理への提言に至るまで系統的に示す論文構成となっている。
論文としての研究成果に付け加えると、特筆すべきは、これらの調査・分析は指導教員からの指示によるものだけではなく、多くの部分を自ら立案し、また現地に赴いて相応の時間をかけて実施したものという点である。研究成果を系統的に取りまとめ、高品質な形で論文としてまとめ上げた。まさに自主的な研究の遂行がなされ、さらにはいくつもの学会・研究会等にも積極的に参加・発表し、学術コミュニティのなかで多様な研究者と対等の議論を行い、またそれを自らの研究にフィードバックさせた。自ら進めた修士論文の一部は、既に学術誌に投稿中でもあり、その論文投稿を行う際に学んだ論文・図表の書き方も、修士論文のなかに充分に活かされている。総じて、模範的な修士論文研究を体現していた。
以上の理由から,本論文は修士論文として極めて優れた水準に達していると評価できるとともに、環境起学専攻の理念と目的に合致し、受賞に相応しいと認められる。
———————————————————————————————–
氏名: 齋藤 淳也(Junya Saito)
題目: Does removal of pleopods provide an easy sterilization method for invasive
crayfish? (腹肢の除去は、侵略的外来種のザリガニを簡単に不妊化する手法となるか?)
【選定理由】
外来種の侵入定着は生物多様性や生態系機能の低下の大きな脅威となっており、その防除方法が世界中で求められている。本研究は、北米原産のウチダザリガニの不妊化による個体数低減を目指して、メスの腹肢(ふくし)除去の効果、その持続性や更なる改善手法、そして脱落卵の生存の可能性を検証した。2年間にわたる室内実験装置での個体飼育と対照実験により、腹肢の除去は抱卵能力を顕著に低下させ、その効果は少なくとも2年間継続することが明らかになった。また、処理による生残率の低下は見られず、脱落卵の野外環境下での生存確率は低いことも示唆された。
これらの成果は、ザリガニの腹肢が抱卵に極めて重要な役割を果たすことを示すとともに、その除去は本種の不妊化技術として有効であることを示唆した。ザリガニの生物学的な理解を深めるとともに、実践的な手法開発の観点から高い新規性が認められる。今後、野外環境下で本手法の効果実証を行うことに期待が持てる。生態系管理手法としての実用性と必要条件を十分に検討し、実験水槽での操作実験を緻密に複合的に用いた重層的な研究計画・成果は高く評価できる。
以上の理由から、本論文は環境起学専攻の理念と目的に合致し、受賞に相応しいと認められた。