
億僗僩僪僋僞乕
| 戝搰丂榓桾 | 乽戝婥棨堟惗懺宯寢崌儌僨儖偺奐敪偲彨棃梊應乿 |
壏抔壔
| 埨惉丂揘暯 | 乽愥昘寳偵偍偗傞僄傾儘僝儖偺桝憲丒捑拝夁掱丄媦傃愥昘僐傾傪梡偄偨崅暘夝擻曻幩嫮惂椡偺曄摦暅尦乿 |
| 揷懞丂妜巎 | 乽撿嬌奀偵偍偗傞奀昘惗嶻検偺擭曄摦乿 |
摑崌宆僾儘僕僃僋僩俀丗戝婥丒奀梞丒棨柺丒暔帒丒惗懺摑崌儌僨儖
| 栰懞丂戝庽 | 乽奀昘惗惉偲梈夝偵敽偆戝婥傊偺擇巁壔扽慺曻弌z廂偵娭偡傞尋媶乿 |
| 廳岝丂夒恗 | 乽屆奀梞弞娐暅尦偺偨傔偺僾儘僉僔乕奐敪偍傛傃奀掙懲愊暔傊偺摉奩僾儘僉僔乕偺墳梡乿 |
| 憗愳丂恀婭 | 乽怉暔僾儔儞僋僩儞偺嵶朎巰偲抧媴娐嫬曄壔乿 |
僆僝儞憌攋夡
| 曅壀丂崉暥 | 乽奀梞惈僶僋僥儕傾偵偍偗傞巼奜慄偺塭嬁昡壙乿 |
惗懺婡擻掅壓
| 彲嶳丂婭媣巕 | 乽惗暔懡條惈偵拲栚偟偨怷椦偺暅尦婡峔偲嵞惗帠嬈庤朄偺専摙乿 |
| 堜揷丂釳 | 乽婥岓曄摦偑拵攠壴怉暔偺憲暡嫟惗宯偵媦傏偡塭嬁梊應乿 |
| 悪杮丂懢榊 | 乽暢傪梡偄偨傾儉乕儖僸儑僂偲僔儀儕傾僩儔偺堚揱揑夝愅乿 |
| 崱堜丂崃婭 | 乽娐嫬曄壔偵墳偠偨儈僕儞僐偺宍懺曄壔偺暘巕婡峔乿 |
墭愼暔幙丒娐嫬廋暅
| 慮崻峅徍 | 乽僇乕儃儞僫僲僠儏乕僽傪梡偄偨娐嫬廋暅媄弍偺奐敪乿 |
| Lim, Chungwan | `Construction of alkalic tephrochronogogical framework in the Japan/East Sea for testing the synchronization of abrupt changes during the Late Quaternary` |
尋媶寁夋偺儁乕僕傊
乽戝婥棨堟惗懺宯寢崌儌僨儖偺奐敪偲彨棃梊應乿
娐嫬壢妛尋媶堾丂丂俠俷俤尋媶堾丂丂戝搰丂榓桾
丂怷椦偼棨堟偺戝偒側柺愊傪愯傔丆戝婥偲棨柺娫偱偺憡屳嶌梡偵偍偄偰廳梫側栶妱傪扴偭偰偄傞丅怷椦傪娷傓怉惗偼丆戝婥亅棨柺娫偱悈丆擬丆擇巁壔扽慺摍偺僄僱儖僊乕丆暔幙桝憲捠偟偰戝婥偐傜偺塭嬁傪庴偗丆戝婥傕傑偨怉惗偐傜塭嬁傪庴偗偰偄傞丅偙偺戝婥亅棨柺憡屳嶌梡偼怉惗偺懚嵼偵傛傝暋嶨偵側傞偑丆怉惗偺桳柍偵傛偭偰戝婥偲棨柺偺傗傝庢傝偼戝偒偔堎側傞偲偄偆揰偐傜丆戝婥棨柺夁掱偵偍偄偰昁梫晄壜寚偱偁傞丅
丂抧媴壏抔壔偵敽偭偨崀悈検傗婥壏偺曄壔偼怉惗傊塭嬁傪梌偊丆怉惗偑曄壔偡傞偙偲偼戝婥偺彅夁掱偵塭嬁傪梌偊傞偲峫偊傜傟傞丅偟偐偟丆尰嵼偺戝婥戝弞娐儌僨儖偱峴傢傟偰偄傞壏抔壔幚尡偱偼丆奺抧堟偱偺怉惗偑屌掕偝傟丆壏抔壔帪偱傕摨偠怉惗偺傑傑偱偁傞丅偙傟傪夵慞偡傞偨傔偵偼丆怉惗偺惉挿丆屚巰偲偄偭偨怉惗摦懺傪峫椂偟偨儌僨儖偺奐敪偑昁梫偱偁傞丅偙偺傛偆側怉惗摦懺儌僨儖傪戝婥戝弞娐儌僨儖偵寢崌偡傞偙偲偵傛傝尰幚偵嬤偄棨堟偑嵞尰偝傟傞偙偲偑尒崬傑傟傞丅
丂杮尋媶偱偼丆戝婥棨堟惗懺宯寢崌儌僨儖傪奐敪偟丆婥岓偲怉惗偺娭學傪柧傜偐偵偡傞偙偲傪栚揑偵偡傞丅埲壓偵尋媶撪梕傪帵偡丅
戝婥棨堟惗懺宯寢崌儌僨儖偺奐敪
丂搶嫗戝妛婥岓僔僗僥儉僙儞僞乕偲崙棫娐嫬尋媶強偱奐敪偝傟偨戝婥戝弞娐儌僨儖乮CCSR/NIES
AGCM乯偵怉惗摦懺傪壛枴偟偨戝婥亅棨柺儌僨儖偱偁傞MINoSGI傪慻傒崬傒丆戝婥棨堟惗懺宯寢崌儌僨儖偺奐敪傪峴偆丅
怉惗偲婥岓偺娭傢傝
丂寢崌儌僨儖傪梡偄偰怉惗摦懺傪慻傒崬傫偩岠壥傪昡壙偡傞偙偲偱丆戝婥亅棨柺憡屳嶌梡偵偍偗傞怉惗偲婥岓偺娭傢傝傪夝柧偡傞丅
挿婜曄摦
丂挿婜揑側婥岓曄摦偲怉惗偺娭學傗壏抔壔傊偺塭嬁傪昡壙偡傞丅崱傑偱偺傛偆側怉惗屌掕偺壏抔壔幚尡偲怉惗摦懺傪壛枴偟偨寢崌儌僨儖偺幚尡傪斾妑偡傞丅
怉惗偺墦妘揑側戝婥傊偺塭嬁
丂怉惗偼嬊抧揑側婥岓偵塭嬁傪梌偊傞偩偗偱偼側偔丆墦妘揑側婥岓宍惉傊偺塭嬁偑峫偊傜傟傞丅偦偙偱杒曽怷椦傪偼偠傔偲偟偨奺抧堟偺怉惗忬懺偑嬊抧揑丆墦妘揑側婥岓偵偳偺傛偆側塭嬁傪梌偊偰偄傞偐傪挷傋傞丅
丂埲忋偺尋媶傪捠偟偰丆怉惗亅婥岓娫偺憡屳嶌梡偺棟夝偍傛傃壏抔壔傊偺塭嬁傪昡壙偡傞偙偲偱丆彨棃偺婥岓宍惉丆曄摦偵偍偗傞棨堟惗懺宯偺栶妱傪柧傜偐偵偟偨偄丅
乽愥昘寳偵偍偗傞僄傾儘僝儖偺桝憲丒捑拝夁掱丄媦傃愥昘僐傾傪梡偄偨崅暘夝擻曻幩嫮惂椡偺曄摦暅尦乿
抧媴寳壢妛愱峌丂攷巑屻婜壽掱1擭 埨惉丂揘暯(巜摫嫵姱丗杮摪晲晇乯
亙尋媶攚宨亜
丂丂廋巑尋媶偵偰丄傾儔僗僇偺昘壨偱孈嶍偝傟偨愥昘僐傾50倣偺僟僗僩傪挻崅暘夝擻偱暘愅傪峴偭偨丅僐傾偼偙偺10擭傪暅尦偡傞偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丅傑偨丄尰抧娤應偵偍偄偰婥徾丒愥昘娤應傪峴偭偨丅偦偺椉幰偺寢壥偐傜丄嬤擭偺杒懢暯梞堟偺僟僗僩偺桝憲丒捑拝夁掱偑棟夝偝傟偨丅偟偐偟丄愥昘僐傾偼婥徾僨乕僞偺側偄婜娫傪暅尦偱偒傞偙偲偑廳梫偱偁傞偨傔丆2杮栚偵孈嶍偝傟偨栺216倣偺愥昘僐傾偐傜夁嫀100乣300擭偺婥岓曄摦婰榐偺拪弌偑婜懸偝傟傞丏
亙尋媶栚揑亜
丂丂2杮栚偺愥昘僐傾偐傜丄夁嫀偺僄傾儘僝儖乮杮尋媶偱偼庡偵僟僗僩乯偺挿婜曄摦忣曬傪崅暘夝擻偱拪弌偡傞丅僄傾儘僝儖偼懢梲岝傪嶶棎丒媧廂偡傞偙偲偵傛傝丄抧媴偺曻幩廂巟偵塭嬁傪梌偊傞丅21悽婭COE偺栚巜偡抧媴壏抔壔梊應偵偍偄偰偼丄偙偺岠壥偺峫椂偼昁梫晄壜寚偱偁傞丅杮尋媶偱偼丄嶶棎丒曻幩揱払棟榑傪梡偄偰丄杒敿媴偺僟僗僩偵傛傞曻幩嫮惂椡偺挿婜曄摦傪崅暘夝擻偱暅尦偡傞丅嵟廔揑偵丄廋巑偺尋媶偱摼偨丄僄傾儘僝儖偺桝憲宱楬傗捑拝夁掱偵偍偗傞抦幆傪摫擖偟丄夁嫀100乣300擭偺杒敿媴偺僟僗僩偵傛傞曻幩嫮惂椡偺曄摦偑婥岓偵梌偊偰偒偨塭嬁偵偮偄偰昡壙偡傞偙偲傪杮尋媶偺栚揑偲偡傞丅
亙尋媶曽朄亜
1. 愥昘僐傾乮嶥杫偱嵦庢偟偨愥僒儞僾儖娷傓乯僒儞僾儖拞偺僟僗僩偺棻巕悢乮0.52亅16兪m乯傪儗乕僓乕岝嶶棎憰抲(Laser
Particle Counter)傪梡偄偰丄崅暘夝帪娫擻乮栺10cm娫妘乯偱暘愅偟丄夁嫀100乣300擭偺婫愡曄摦傑偱曔傜偊偨僟僗僩曄摦傪拪弌偡傞丅偙偺憰抲偼尰嵼丄強懏尋媶婡娭偱偁傞杒奀摴戝妛戝妛堾丒娐嫬壢妛堾乮掅壏壢妛尋媶強丗埲屻丆掅壏尋偲屇傇乯偵側偄偨傔丄嬌抧尋媶強偵偍偄偰暘愅傪峴偆丅
丂丂嶥杫偱嵦庢偟偨愥僒儞僾儖偼掅壏尋偺僀僆儞僋儘儅僩僌儔僼傕暘愅偵梡偄傞丅傑偨丄2004亅2005擭搤婫偵娤應傪偍偙側偭偨丄岝妛揑偵應掕偟偨僄傾儘僝儖傗崀愥棻巕僨乕僞傪巊梡偡傞丅
2. 嶶棎丒曻幩揱払棟榑傗丄愥昘僐傾偐傜拪弌偝傟偨僟僗僩偺棻宎暘晍忣曬傪梡偄偰曻幩嫮惂椡傪寁嶼偟丄夁嫀100乣300擭偺曻幩嫮惂椡偺挿婜曄摦傪崅暘夝帪娫擻偱暅尦偡傞丅
3. 寁嶼寢壥傪尦偵僟僗僩偵傛傞曻幩嫮惂椡偺挿婜曄摦偑婥岓傊梌偊傞塭嬁偵偮偄偰媍榑傪偍偙側偄丆彨棃偺梊應偵偮偄偰傕媍榑傪峴偄丄傑偲傔傞丅
亙尋媶寁夋亜
乮侾乣俀擭栚乯
丂丂2004亅2005擭搤婫丄嶥杫偺掅壏尋棤偱枅擔嵦庢偟偨丄愥僒儞僾儖拞偺僟僗僩丒僀僆儞摍傪暘愅偡傞乮壞崰傑偱偵廔椆梊掕乯丅偦偺僨乕僞偲僄傾儘僝儖偺岝妛應掕僨乕僞媦傃崀愥棻巕偺娭學偐傜丄崀愥帪偺僄傾儘僝儖捑拝僾儘僙僗偵偮偄偰媍榑偡傞乮僐傾偺僟僗僩僨乕僞傪夝庍偡傞嵺偺幚嵺偺僼儔僢僋僗傊姺嶼偡傞偨傔偺尋媶乯丅傑偨丄壞偔傜偄傪傔偳偵廋巑壽掱偵偍偗傞尋媶惉壥偺堦晹傪傑偢1杮榑暥偵搳峞偡傞丅
丂丂壞埲崀偐傜丄傾儔僗僇偺儔儞僎儖嶳偱2004擭偵孈嶍偟偨丆2杮栚偺愥昘僐傾栺216m乮1杮栚偲廳暋偟偰偄側偄50m埲崀150m傪拞怱偵暘愅乯偺僟僗僩暘愅傪忋婰偵婰嵹偟偨曽朄偱峴偆丅愥昘僐傾偺暘愅偼婎杮揑偵楢懕偟偰10cm娫妘掱搙偱庢摼偡傞丅僐傾暘愅偵偼旕忢偵帪娫偑偐偐傞偺偱丄暘愅偵偼1擭埲忋偐偐傞梊掕偱偁傞丅攷巑1擭屻婜偐傜暘愅傪巒傔丄2擭栚傕堷偒懕偒僐傾偺僟僗僩暘愅傪峴偆丅
丂丂摨帪偵丄僐傾偺僨乕僞傪巊偭偰丄崅暘夝擻偺曻幩嫮惂椡傪尒愊傕傞偨傔偺儌僨儖傪峔抸偡傞丅儌僨儖傪峔抸偡傞偨傔丄嶶棎丒曻幩揱払棟榑偺曌嫮傪恑傔傞丅嬶懱揑偵偼丄偙傟傑偱偺悢懡偔偁傞嶶棎棟榑傪峫椂偟偨曻幩揱払儌僨儖傪嶲峫偵偟偮偮丄愥昘僐傾偺僨乕僞傪揔墳偟傗偡偄儌僨儖傪峔抸偡傞乮崱屻丆懠偺応強偱孈嶍偝傟偨愥昘僐傾偺僨乕僞偱傕巊偊傞傛偆偵偡傞偨傔偵乯丅
乮俁擭栚乯
丂丂2擭娫偱庢摼偟偨丄崅暘夝擻僟僗僩僨乕僞傪尦偵曻幩嫮惂椡傪丄峔抸偟偨儌僨儖偱寁嶼傪峴偄夁嫀100乣300擭偺曻幩嫮惂椡偺曄摦偑婥岓偵梌偊偰偒偨塭嬁傪昡壙偟丄暔幙弞娐傗婥岓曄摦傊偺塭嬁傪愥昘寳偺帇揰偐傜媍榑傪峴偄丄傑偲傔傞丅
儁乕僕偺愭摢傊
乽撿嬌奀偵偍偗傞奀昘惗嶻検偺擭曄摦乿
戝婥奀梞寳娐嫬壢妛愱峌丂嬌堟戝婥奀梞妛島嵗
攷巑屻婜壽掱3擭丂揷懞丂妜巎乮巜摫嫵姱丗戝搰丂宑堦榊丂彆嫵庼乯
尋媶栚揑丗
丂撿嬌奀偼偦偺傎偲傫偳偑婫愡奀昘堟偱偁傝丄奀昘偑帩偮惓偺僼傿乕僪僶僢僋岠壥側偳偑尨場偲側偭偰丄抧媴壏抔壔側偳偺婥岓曄摦偐傜偺姶搙偑崅偔丄奀昘柺愊偑戝偒偔擭乆曄摦偡傞丅偙偙偼撿嬌掙憌悈偑嶌傜傟傞奀堟偱偁傞偲嫟偵丄戝婥奀梞娫偺擬岎姺偑惙傫偵峴傢傟偰偄傞奀堟偱傕偁傝丄愒摴堟偲暲傫偱抧媴婯柾偱偺婥岓曄摦傪寛傔傞椞堟偱偁傞偺偱偼側偄偐偲峫偊傜傟偰偄傞丅偙偺撿嬌奀偵偍偄偰丄戝婥偵懳偟偰傕奀梞偵懳偟偰傕戝偒側塭嬁傪梌偊傞椞堟偼増娸億儕僯儎偱偁傞丅偙偙偱偼搤婫偵偍偄偰丄捠忢偺奀昘堟偲斾傋偰擬僼儔僢僋僗偍傛傃奀昘惗嶻検偑堦寘戝偒偄丅偙偙偱偺戝偒側奀昘惗嶻偵敽偆墫暘攔弌偵傛傞崅枾搙悈宍惉偼丄掙憌悈宍惉偺尮偲側傞丅偟偐偟側偑傜偙偺奀堟偼尰応娤應偑嬌傔偰擄偟偄丅偙傟傜偺彅尰徾傪掕検揑偵柧傜偐偵偡傞偨傔偵偼丄塹惎儕儌乕僩僙儞僔儞僌偲擬廂巟寁嶼偑堦偮偺桳岠側曽朄偱偁傞丅
尋媶寁夋丗
丂塹惎儕儌乕僩僙儞僔儞僌偵傛偭偰撿嬌奀偺奀昘偺惗惉丒暘晍丒徚柵側偳偺幚懺傪掕検揑偵柧傜偐偵偡傞偨傔偵丄奀昘敾暿傾儖僑儕僘儉傪嶌惉偡傞丅尰嵼丄儅僀僋儘攇曻幩寁乮SSM/I乯婸搙壏搙僨乕僞傪梡偄偰奀昘偺庬椶偲昘岤傪専弌偡傞傾儖僑儕僘儉偺採弌傪弨旛拞偱偁傞丅NOAA AVHRR僨乕僞偺懠偵丄2003擭偵崑嵱昘慏偵傛偭偰峴傢傟偨崙嵺撿嬌奀昘娤應乮ARISE, 2003乯偵嶲壛偟偨嵺偵庢摼偟偨撿嬌尰応娤應僨乕僞偲偺斾妑傪峴偆丅偙偺傾儖僑儕僘儉偵傛偭偰丄奀昘偺庬椶偲昘岤偺嬻娫暘晍丄惗惉丒徚柵偺條巕丄偦偟偰偦偺婫愡丒擭曄摦傪丄婛懚偺奀昘傾儖僑儕僘儉傛傝傕崅偄惛搙偱柧傜偐偵偡傞偙偲偑偱偒傞丅
丂傑偨丄擬廂巟寁嶼偵傛偭偰戝婥-奀梞-奀昘娫擬岎姺傪柧傜偐偵偟丄嵟傕擬岎姺偑戝偒偄増娸億儕僯儎堟偱偺奀昘惗嶻棪丒擬墫僼儔僢僋僗偺僷儔儊乕僞壔傪帋傒傞丅偙傟偼婥岓儌僨儖偵斀塮偝傟摼傞悈弨傪傔偞偡丅偦偟偰10擭埲忋拁愊偝傟偨僨乕僞傪梡偄傞偙偲偵傛傝丄奀昘惗嶻検傗崅枾搙悈宍惉偺抧堟嵎傗婫愡丒擭曄摦傪柧傜偐偵偡傞丅偙傟偵傛傝丄抧媴壏抔壔偺塭嬁偺壜擻惈偑峫偊傜傟傞奀昘丒崅枾搙悈偺惗嶻検尭彮偵偮偄偰丄庡梫惗嶻堟偺忬嫷傪柧傜偐偵偡傞偙偲偑偱偒傞丅1990擭戙偵偍偗傞奀昘丒崅枾搙悈惗嶻検偺擭乆曄摦偲抧媴壏抔壔偲偺娭學傪柧傜偐偵偡傞偨傔偵丄偝傜側傞夝愅傪峴偆丅
儁乕僕偺愭摢傊
乽奀昘惗惉偲梈夝偵敽偆戝婥傊偺擇巁壔扽慺曻弌z廂偵娭偡傞尋媶乿
抧媴寳壢妛愱峌丂暔幙弞娐丒娐嫬曄慗妛僐乕僗
攷巑屻婜壽掱侾擭丂栰懞 戝庽乮巜摫嫵姱丗媑愳媣岾乯
丂杮尋媶偺嵟廔栚揑偼丄奀昘惗惉偲梈夝偵敽偆戝婥丒奀梞娫偺擇巁壔扽慺乮CO2乯岎姺傪巟攝偡傞梫場傪柧傜偐偵偟丄婫愡奀昘堟偑扽慺弞娐偵壥偨偡栶妱傪昡壙偡傞偙偲偱偁傞丅抧媴婯柾偺婥岓傪僐儞僩儘乕儖偡傞梫場偲偟偰丄崅堒搙奀堟偵暘晍偡傞奀昘偑壥偨偟偰偄傞栶妱偼戝偒偄丅椺偊偽丄奀昘偺懚嵼偼傾儖儀僪乮懢梲岝偺斀幩擻乯傪憹戝偝偣丄擔幩媧廂偺戝暆側掅壓傪彽偔丅傑偨丄戝婥偲奀梞偺娫偱抐擬嵽偲偟偰摥偒丄壏抔壔傪寉尭偝偣傞岠壥傕偁傞偲擣幆偝傟偰偄傞丅堦曽丄暔幙弞娐偺娤揰偐傜偼丄奀昘偼扨側傞戝婥-奀梞娫偺暔幙岎姺偺乬忈暻乭偲偟偰擣幆偝傟偰偒偨丅椺偊偽丄奀昘偑懚嵼偡傞偲壏幒岠壥婥懱偱偁傞CO2偺奀梞傊偺曻弌丒媧廂偑惗偠側偄偲偝傟偰偒偨丅偟偐偟丄幚嵺丄奀昘偼丄晛抜変乆偑栚偵偡傞扺悈昘偲偼堎側傝丄懡岴惈偺峔憿傪帩偪惼偄偨傔丄僈僗摟夁惈偑戝偒偄偙偲偑丄悢彮側偄娤應偵傛傝柧傜偐偵側傝偮偮偁傞乮Gosink
et al.,1976; Semiletov et al., 2004乯丅偦偙偱丄挊幰偼丄幒撪幚尡偱奀昘偺惗惉丒惉挿傪嵞尰偟丄奀昘傪捠偟偰偺CO2岎姺偺婎杮揑側儊僇僯僘儉傪柧傜偐偵偟偰偒偨乮Nomura
et al.,2005乯丅幚嵺偺奀梞偵偼暔棟丄惗暔丒壔妛揑梫場偑暋嶨偵擖傝崿偠偭偰偄傞丅奀昘傪捠偟偰偺CO2岎姺偼丄戝婥偲奀昘拞偵懚嵼偡傞僽儔僀儞乮崅墫暘悈乯偺擇巁壔扽慺暘埑乮pCO2乯嵎丄傕偟偔偼戝婥偲奀昘壓奀悈偺pCO2嵎偵傛偭偰惗偠傞丅奀昘惉挿婜偵奀昘拞僽儔僀儞偺pCO2偺寛掕梫場偼丄庡偵僽儔僀儞偺掅壏壔偵傛傞擹弅岠壥乮崅墫暘壔乯丄偮傑傝暔棟揑梫場偱偁傞乮Nomura
et al.,2005乯丅堦曽丄奀昘梈夝婜偼丄庡偵奀昘捈壓媦傃奀昘拞僽儔僀儞偱偺傾僀僗傾儖僕乕乮怉暔僾儔儞僋僩儞乯偺懚嵼丄偮傑傝惗暔丒壔妛揑梫場偑桪愭偟丄惗暔偺岝崌惉丒屇媧偑僽儔僀儞偺pCO2傪巟攝偡傞偲峫偊傜傟傞乮Semiletov
et al., 2004乯丅婫愡奀昘堟偱偺尰応娤應偵偍偄偰偼丄奀昘拞媦傃奀昘壓偵偍偗傞暔棟丄壔妛丒惗暔夁掱偑扴偭偰偄傞偦傟偧傟偺CO俀媧廂丒曻弌擻椡傪棟夝偟丄幒撪幚尡偱摼偨婎杮揑側儊僇僯僘儉傪峫椂偟偰婥懱岎姺傪掕検昡壙偡傞昁梫偑偁傞丅杮尋媶偱偼埲壓偺崁栚傪幚巤偡傞丅
嘥丏昘忋尰応娤應偵梡偄傞CO2岎姺検應掕婡婍乮僠儍儞僶乕乯偺嶌惉媦傃梊旛幚尡傪峴偆丅
嘦丏嵱昘慏粋猓偱偺婫愡奀昘堟慏敃娤應乮2寧忋弡乯媦傃僒儘儅屛偱偺昘忋娤應乮1寧壓弡乗俁寧壓弡乯偵偰嘆僠儍儞僶乕朄傪梡偄CO俀岎姺検偺應掕傪峴偆丄嘇奀昘昞柺壏搙丄婥壏丄幖搙丄晽丄挿抁攇曻幩僼儔僢僋僗偺楢懕娤應傪峴偄丄奀昘偺惉挿娐嫬傪抦傞丄嘊僒儞僾儖乮奀昘拞僽儔僀儞丄奀悈丄僠儍儞僶乕撪僄傾乕乯偺嵦庢傪峴偆丅
嘨丏扽巁宯惉暘乮倫俫丄慡扽巁擹搙乯丄梟懚婥懱惉暘擹搙丄僋儘儘僼傿儖検偺應掕傪峴偆丅
嘩丏嘊偱摼傜傟偨寢壥夝愅傛傝暔棟丄壔妛丒惗暔夁掱偑扴偭偰偄傞偦傟偧傟偺CO俀媧廂丒曻弌擻椡傪昡壙偡傞丅
嘪丏嘦-嘆丄嘦-嘇丄嘩偺寢壥傪慻傒崌傢偣僷儔儊乕僞壔偟丄塹惎僨乕僞偵傛傝奺婫愡奀昘堟偺摿挜乮奀昘暘晍丄昘岤側偳乯傪峫椂偟偨忋偱丄杒嬌奀傗撿嬌奀偺婫愡奀昘堟偱偺CO俀岎姺検傪抦傞丅偦偟偰丄慡媴偵偍偗傞婫愡奀昘堟偑慡媴扽慺廂巟偵梌偊傞塭嬁傪昡壙偡傞丅
嘫丏堷偒懕偒幒撪幚尡乮弶婜墫暘曄壔側偳乯傪峴偆丅
儁乕僕偺愭摢傊
乽屆奀梞弞娐暅尦偺偨傔偺僾儘僉僔乕奐敪偍傛傃奀掙懲愊暔傊偺摉奩僾儘僉僔乕偺墳梡乿
抧媴寳壢妛愱峌丂抧媴寳壢妛僐乕僗
攷巑屻婜壽掱侾擭丂丂廳岝丂夒恗乮巜摫嫵姱丗搉曈朙彆嫵庼乯
亂尋媶栚揑亃
丂丂惣晹杒懢暯梞偵偍偗傞嵟廔昘婜偐傜尰嵼乮Holocene乯偵偐偗偰偺奀梞弞娐條幃乮偮傑傝丄奀梞昞憌偺塰梴墫弞娐條幃乯偺曄摦傪暅尦偡傞偙偲傪栚揑偲偡傞丅
亂尋媶曽朄亃
丂丂宂憯乮堚奫乯妅拞偺嬥懏乮Ge丄Zn摍乯[eg.,Froelich et al.,1992]媦傃拏慺埨掕摨埵懱斾乮兟15N 乯[eg.,Sigman et al.,1999]偼丄杮尋媶奀堟偲摨條丄奀梞怺憌偐傜偺桸徃偵傛傝丄奀梞昞憌偺塰梴墫偑堐帩偝傟偰偄傞撿戝梞偵偍偄偰丄夁嫀丄屆奀梞偺塰梴墫娐嫬暅尦偺僾儘僉僔乕偲偟偰巊梡偝傟偰偒偨丅偟偨偑偭偰撿戝梞偲摨條丄奀梞怺憌偐傜偺桸徃偵傛傝丄奀梞昞憌偺塰梴墫偑堐帩偝傟偰偄傞杮尋媶奀堟偵偍偄偰傕丄偙傟傜偺僾儘僉僔乕偼奀梞昞憌偵偍偗傞塰梴墫偺忬嫷傪斀塮偡傞偲峫偊傜傟傞丅偟偐偟夁嫀丄偙傟傜偺僾儘僉僔乕偑懲愊暔偵帄傞傑偱偺夁掱偵懚嵼偡傞捑崀棻巕偵偍偄偰丄偳偺傛偆側嫇摦傪帵偡偺偐傪専徹偟偨椺偼側偄丅
丂丂偦偙偱丄傑偢尰嵼偺惣晹杒懢暯梞偵偍偄偰丄偙傟傜偺僾儘僉僔乕偑奀梞昞憌偵偍偗傞塰梴墫偺忬嫷傪偳偺掱搙偺姶搙傪傕偭偰丄斀塮偟偆傞偺偐傪専徹偡傞丅専徹偺曽朄偲偟偰偼丄奀梞昞憌偵偍偗傞塰梴墫偺帪宯楍僨乕僞僙僢僩偑懚嵼偡傞抧揰乮St.Knot乯偵偍偄偰丄愝抲偝傟偰偄傞僙僕儊儞僩僩儔僢僾偵曔廤偝傟偨捑崀棻巕拞偺偙傟傜僾儘僉僔乕傪應掕偟丄奀悈偺僨乕僞偲斾妑丒専摙偡傞偙偲偵傛傞丅捑崀棻巕拞偺偙傟傜僾儘僉僔乕偺應掕偼丄奀梞昞憌偵偍偗傞塰梴墫偺帪宯楍僨乕僞僙僢僩偑懚嵼偡傞暯惉12擭乣暯惉17擭偵偐偗偰峴偄丄婫愡揑側姶搙丄宱擭揑側姶搙偺掱搙傪専徹偡傞丅側偍捑崀棻巕僒儞僾儖偼婛偵擖庤嵪傒丅
亂尋媶寁夋亃
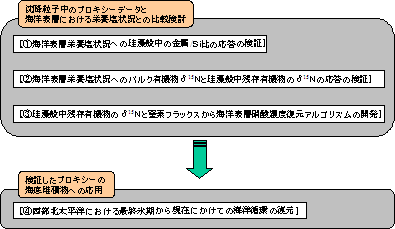 丂丂尋媶寁夋偼丄僼儘乕偵帵偡偲偍傝偱偁傝丄奺崁栚偺徻嵶偼埲壓偵帵偡偲偍傝偱偁傞丅
丂丂尋媶寁夋偼丄僼儘乕偵帵偡偲偍傝偱偁傝丄奺崁栚偺徻嵶偼埲壓偵帵偡偲偍傝偱偁傞丅
嘆丗丂宂憯妅拞偺Ge/Si斾丄Zn/Si斾偼奀悈拞偺塰梴墫忣曬傪婰榐偟偰偄傞偲偄偆曬崘偑偁傞[eg.,Floerich
et al.,1992]丅偦偙偱丄奀梞昞憌偺塰梴墫帪宯楍僨乕僞僙僢僩偑偁傞抧揰偵偍偗傞捑崀棻巕拞偺偙傟傜僾儘僉僔乕傪應掕偟丄奀悈僨乕僞偲偺斾妑丒専徹傪峴偄丄偦偺僾儘僉僔乕偲偟偰偺桳梡惈傪挷傋傞丅摿偵Ge/Si斾偼偗偄巁墫擹搙偺巜昗偵側傞壜擻惈偑偁傞偨傔廳梫偱偁傞丅
嘇丗丂捑崀棻巕拞偺僶儖僋桳婡暔偺拏慺埨掕摨埵懱斾乮兟15N乯偼丄戝嬊揑偵偼奀梞昞憌偺徤巁墫擹搙偲惗暔惗嶻偺戝偒偝偵傛傝寛傑偭偰偄傞傕偺偺丄擭戙偺屆偄棻巕摍偺墶偐傜偺桝憲傗丄捑崀夁掱偵偍偗傞暘夝條幃偺堘偄摍偵傛傝塭嬁偝傟傞偨傔丄僶儖僋桳婡暔偺摨埵懱斾偺忣曬偐傜丄奀梞昞憌偺塰梴墫忬嫷傪悇嶡偡傞偙偲偼擄偟偄丅偦偙偱丄暘夝傪庴偗偯傜偄宂憯妅拞巆懚桳婡暔偺兟15N偑奀梞昞憌偺塰梴墫忬嫷偺僾儘僉僔乕偺岓曗偲峫偊丄偙傟偺奀梞昞憌塰梴墫忬嫷傊偺墳摎偍傛傃僶儖僋桳婡暔兟15N偲偺斾妑専摙傪峴偄丄偦偺僾儘僉僔乕偲偟偰偺桳梡惈傪専徹偡傞丅
嘊丗丂杮尋媶奀堟嬤朤偱偺僙僕儊儞僩僩儔僢僾娤應寢壥傛傝丄捑崀棻巕拞偺僶儖僋桳婡暔兟15N偲PON僼儔僢僋僗偐傜奀梞昞憌偺徤巁墫擹搙傪尒愊傕傞傾儖僑儕僘儉傪採埬偟偨愭峴尋媶偑偁傞乮Nakatsuka
et al.,1997乯丅偙偺尋媶偱偼丄僶儖僋桳婡暔偺摨埵懱斾傪巊梡偟偨偨傔丄屆偄棻巕偺崿擖偑偁傝怺憌僩儔僢僾偺僨乕僞偼巊梡偱偒側偐偭偨丅宂憯妅拞巆懚桳婡暔兟15N偼丄暘夝偺塭嬁偑偒傢傔偰彮側偄偨傔丄偙偺摨埵懱斾傪巊梡偡傟偽丄怺憌僩儔僢僾偺僨乕僞丄偟偄偰偼懲愊暔偺僨乕僞偐傜傕奀梞昞憌偺徤巁擹搙傪尒愊傕傟傞壜擻惈偑偁傞丅摉僨乕僞傪梡偄偰丄徤巁墫擹搙暅尦偺怴偨側傾儖僑儕僘儉偺採埬傪帋傒傞丅
嘋丗丂嘆乣嘊偵偍偄偰丄専徹偟偨僾儘僉僔乕傪奀掙懲愊暔偵墳梡偡傞偙偲偵傛傝丄崱傑偱枹夝柧偱偁傞嵟廔昘婜偐傜尰嵼偵偐偗偰偺奀梞弞娐條幃偺悇堏偵偮偄偰柧傜偐偵偡傞丅
儁乕僕偺愭摢傊
乽怉暔僾儔儞僋僩儞偺嵶朎巰偲抧媴娐嫬曄壔乿
娐嫬婲妛愱峌丂愭嬱僐乕僗丂
攷巑屻婜壽掱侾擭丂憗愳恀婭乮巜摫嫵姱丗楅栘岝師彆嫵庼乯
[尋媶攚宨]
奀梞怉暔僾儔儞僋僩儞偵傛傞慡奀梞偱偺擭娫偺扽慺屌掕検乮弮婎慴惗嶻乯偼栺 45 ~ 57 x 1015 g C偲尒愊傕傜傟偰偍傝丄偙偺抣偼棨忋怉暔偺婎慴惗嶻偲傎傏摨摍偱偁傞(Falkowski et al., 2003)丅偡側傢偪丄怉暔僾儔儞僋僩儞偼丄奀梞偺庡梫側婎慴惗嶻幰偱偁傝丄奀梞偺惗懺宯傗暔幙弞娐夁掱偵偍偄偰丄嬌傔偰廳梫側栶妱傪壥偨偟偰偄傞丅嬤擭丄奀梞昞憌偺怉暔僾儔儞僋僩儞偺彍嫀夁掱偺1偮偲偟偰丄奀梞昞憌偱偺怉暔僾儔儞僋僩儞偺嵶朎巰偺廳梫惈偑巜揈偝傟傞傛偆偵側偭偰偒偨乮Bidle and Falkowski, 2004乯丅偟偐偟丄惗暔惗嶻偺崅偄杒惣懢暯梞垷姦懷堟偵偍偗傞怉暔僾儔儞僋僩儞偺嵶朎巰偵娭偡傞抦尒偼夁嫀偵慡偔曬崘偝傟偰偄側偐偭偨丅偝傜偵丄嬤擭丄杒惣懢暯梞垷姦懷堟偺怉暔僾儔儞僋僩儞偺尰懚検傗弮孮廤惗嶻偑擭乆掅壓偟偰偄傞偙偲偑帵嵈偝傟偰偄傞(Ono et al., 2002; Chiba et al., 2004; Miller et al., 2004) 丅偙偺偨傔丄壓婰偺幚尡傪峴偆丅
[尋媶栚揑丒撪梕]
侾丏弔婫僽儖乕儉帪偵偍偗傞恊挭堟偍傛傃崟挭丒恊挭崿崌堟偵偍偗傞怉暔僾儔儞僋僩儞偺嵶朎巰乮D1乯
恊挭堟偱偼丄弔婫偵怉暔僾儔儞僋僩儞僽儖乕儉偑婲偒傞偙偲偑抦傜傟偰偄傞乮Saito et al., 2002乯偑丄僽儖乕儉偺惙悐傪巟攝偡傞場巕偵偮偄偰偼枹偩姰慡偵棟夝偝傟偰偄側偄丅傑偨丄僽儖乕儉傪宍惉偡傞庬偺曄壔偑擭乆婲偒偰偄傞偙偲偑巜揈偝傟偰偄傞乮Chiba et al., 2004乯丅堦曽丄杒奀偵偍偄偰偼丄怉暔僾儔儞僋僩儞僽儖乕儉偺尭悐偵懳偟偰丄嵶朎巰偑75 亾傪婑梌偟偰偄偨偲偄偆曬崘傕偁傞(Brussaard et al., 1995)偨傔丄恊挭偍傛傃崟挭丒恊挭崿崌堟偵偍偄偰丄弔婫僽儖乕儉帪偺怉暔僾儔儞僋僩儞偺嵶朎惗懚棪傪應掕偟丄奀梞惗懺宯傗奀梞暔幙弞娐偵偍偗傞怉暔僾儔儞僋僩儞偺嵶朎巰偺廳梫惈傪掕検揑偵昡壙偡傞丅
俀丏幒撪攟梴幚尡(D1偲D2)
杒惣懢暯梞垷姦懷堟乮恊挭堟乯偱弔婫僽儖乕儉傪宍惉偡傞宂憯Thalassiosira nordenskioeldii丄慡僎僲儉夝撉偑廔椆偟偨宂憯Thalassiosira pseudonana丄媦傃奀梞偺扽慺丒棸墿弞娐偵戝偒側塭嬁傪媦傏偡偲峫偊傜傟偰偄傞墌愇憯Emiliania huxleyi傪嵽椏偵丄抧媴娐嫬曄壔偵傛偭偰婲偙傞偲梊應偝傟傞奀悈壏忋徃丄奀悈偺pH掅壓丄塰梴墫擹搙尭彮偵懳偡傞怉暔僾儔儞僋僩儞傊偺塭嬁傪丄摿偵嵶朎巰偵拝栚偟偰丄昡壙偡傞丅側偍丄T. nordenskioeldii偼塰梴墫娐嫬偑埆壔偡傞偲媥柊朎巕傪宍惉偟丄惗偒墑傃傞愴棯傪帩偭偰偄傞偙偲傪廋巑壽掱偱偺尋媶偱妋擣偟偨偨傔丄媥柊朎巕傪宍惉偟側偄宂憯T. pseudonana傪梡偄偰幚尡傪峴偄丄惗懚愴棯偵傛傞嵶朎惗懚棪摍偺堘偄偵偮偄偰夝柧偡傞丅杮尋媶偱偼丄嵶朎惗暔妛傗暘巕惗暔妛偺暘栰偱奐敪偝傟偨嵶朎巰偺専弌曽朄乮僇僗僷乕僛妶惈應掕朄傗DNA抐曅壔應掕朄摍乯傕摫擖偟丄尰応幚尡偱偼庢摼偡傞偙偲偑弌棃側偄丄傛傝徻嵶側怉暔僾儔儞僋僩儞偺嵶朎巰偺婡峔傪柧傜偐偵偡傞丅
3丏尋媶敪昞(D1乣D3)
丂廋巑夁掱偱峴偭偨尋媶偲忋婰偺尋媶偵娭偟丄崙撪奜偺妛夛偱尋媶敪昞傪峴偆丅傑偨丄榑暥傪嶌惉偟丄崙嵺帍偵搳峞偡傞丅攷巑屻婜壽掱3擭師偵攷巑榑暥傪嶌惉偡傞丅
儁乕僕偺愭摢傊
乽奀梞惈僶僋僥儕傾偵偍偗傞巼奜慄偺塭嬁昡壙乿
娐嫬婲妛愱峌/峀堟娐嫬楎壔僐乕僗
攷巑壽掱1擭丂曅壀崉暥(巜摫嫵姱丗搶惓崉)
<攚宨媦傃栚揑>
丂奜梞堟偺桳婡暔偺戝敿傪愯傔傞梟懚懺桳婡暔偼嵶嬠偵傛偭偰庢傝崬傑傟丄慇栄拵傗曏栄拵側偳偺旝惗暔傪宱偰崅師徚旓幰傊偲桝憲偝傟偰偄傞丅偙偺嵶嬠偵巒傑傞僄僱儖僊乕偺棳傟傪旝惗暔儖乕僾偲屇傃丄奜梞堟偱偺暔幙弞娐傪峫偊傞嵺偵柍帇偱偒側偄僶僀僆儅僗偲峫偊傜傟偰偄傞丅傑偨丄僆僝儞憌偺攋夡偵傛傝惗暔偵桳奞側巼奜慄(UVB)偑憹壛偟丄嵶嬠孮廤偺憹怋懍搙傗嵶朎惉挿懍搙偑慾奞偝傟傞偲偄偆曬崘偑悢懡偔偝傟偰偄傞丅偟偐偟丄挿攇挿椞堟偺巼奜慄(UVA)傗幷岝壓偵偍偄偰偙傟傜偺DNA懝彎偼廋暅偝傟傞偙偲傕抦傜傟偰偄傞丅偮傑傝丄嵶嬠偵偼UVB嫮搙偺嫮偄拫娫偵DNA懝彎偑拁愊偝傟丄UVA嫮搙偑UVB偵彑傞梉曽偲岝偺側偄栭娫偵廋暅偝傟偰偄傞丅堦擔偺娫偵拁愊偝傟傞DNA懝彎偺検偼懢梲岝拞偺UVB偺嫮搙傗擔徠帪娫偵傛偭偰堎側傞偙偲偵側傞偺偱丄堦擔偺廃婜偱姰慡偵廋暅偝傟側偗傟偽梻擔偵DNA懝彎偑巆傞丅
丂娐嫬拞偺嵶嬠偼暘棧偡傞偙偲偑崲擄側偺偱丄DNA懝彎傗嵶朎惉挿懍搙偼嵶嬠孮廤慡懱偺検偲偟偰偟偐掕検偝傟側偐偭偨丅傑偨丄偙傟傑偱偼DNA懝彎偺拁愊検偵偮偄偰偺尋媶偑懡偔廋暅夁掱偵偮偄偰偺尋媶偼彮側偄丅偦偙偱丄杮尋媶偱偼DNA廋暅偺夁掱偵拝栚偟偰DNA懝彎偲廋暅偵梫偡傞帪娫偺娭學傪庬儗儀儖偱昡壙偡傞偙偲傪栰奜挷嵏偲幒撪幚尡偵偰帋傒傞丅
<尋媶寁夋>
1)栰奜挷嵏
丂栰奜挷嵏偱偼岝娐嫬偺堎側傞挷嵏奀堟偵偍偄偰24帪娫埲忋丄悢帪娫偍偒偵昞憌偺奀悈傪嵦廤偡傞丅偙偺撪偺壗夞偐偼桳岝憌拞偱偺墧捈僒儞僾儕儞僌傕峴偆丅岝偺寁應偼嬻拞偺UVA,UVB,PAR傪楢懕揑偵丄悈拞偺巼奜慄偲PAR傪桳岝憌偺僒儞僾儕儞僌偲摨帪偵峴偆丅偙傟傜偺僒儞僾儖偺岝忦審偵敽偭偨DNA懝彎偺掕検揑曄壔傪寁應偡傞丅傑偨丄摨偠僒儞僾儖傪梡偄偰PCR-DGGE朄傪峴偄嵶嬠偺庬慻惉偺曄壔傪掕惈揑偵捛愓偡傞丅峏偵丄妀巁媈帡暔幙傪庢傝崬傑偣偨DNA傪峈尨偲偟偰丄嵶朎柶塽妛揑庤朄傪梡偄偰怴偨偵崌惉偟偨僎僲儉DNA傪慖弌偡傞偙偲偑偱偒傞偺偱丄PCR-DGGE朄偲崌傢偣偰峴偆偙偲偱妶惈傪帩偭偨庬偺帪宯楍曄壔傪柧傜偐偵偡傞丅
丂挷嵏偼増娸堟偐傜奜梞堟傪娷傫偩娤應掕慄偱峴偄丄娤應揰偛偲偵昞柺奀悈偺庬峔惉丄妶惈検丄DNA懝彎検傪寁應偡傞偙偲偱丄摨帪婜偵偍偗傞悈暯揑暘晍傪柧傜偐偵偡傞丅峏偵丄婫愡偛偲偵摨條偺僒儞僾儕儞僌傪峴偄丄偦傟傜傪斾妑偡傞偙偲偱婫愡揑側曄摦傪柧傜偐偵偟偨偄丅
2)幒撪幚尡
丂幒撪幚尡偱偼娐嫬拞偐傜偺扨棧姅傪梡偄偰峴偆丅媅帡揑側尰応娐嫬傪嶌惉偟岝嫮搙偲攇挿傪惂屼偟偨幚尡宯偱拁愊偟偨DNA懝彎検偲廋暅偺帪娫宱夁傪柧傜偐偵偡傞丅懢梲岝傪柾偟偨恖岺岝尮偲摿掕偺攇挿傪僇僢僩偡傞僼傿儖僞乕傪梡偄傞偙偲偱岝娐嫬(巼奜慄偺攇挿傗徠幩嫮搙)傪惂屼偟丄拁愊偟偨DNA懝彎検傪嵶朎柶塽妛揑庤朄偱掕検偡傞丅偙傟傜傪埫忦審壓偱攟梴偟偰DNA懝彎検偲BrdU庢傝崬傒検傪悢廫暘偍偒掕検偡傞丅埲忋偺偙偲偐傜尰応偵懚嵼偡傞嵶嬠偺巼奜慄偵懳偡傞姶庴惈偲丄廋暅偵梫偡傞帪娫傗廋暅晄壜擻偵側傞DNA懝彎検偲偄偭偨巼奜慄偵懳偡傞愽嵼擻椡偲廋暅夁掱傪柧傜偐偵偡傞丅
丂2005擭搙偼丄
1) 5寧偺栰奜挷嵏帪偺奀悈偐傜嵶嬠傪扨棧攟梴偟丄庬傪摨掕偡傞偙偲丅
2) 俋寧埲崀偺栰奜挷嵏
傪梊掕偟偰偄傞丅
儁乕僕偺愭摢傊
乽惗暔懡條惈偵拲栚偟偨怷椦偺暅尦婡峔偲嵞惗帠嬈庤朄偺専摙乿
惗暔寳壢妛愱峌/怉暔惗懺妛僐乕僗
攷巑屻婜壽掱侾擭丂彲嶳婭媣巕乮巜摫嫵堳丗峛嶳棽巌乯
1.尋媶偺攚宨偲栚揑
丂丂怷椦偺傕偮惗暔懡條惈曐帩傗娐嫬曐慡側偳偺惗懺揑婡擻偵懳偟偰偼崅偔昡壙偝傟偰偄傞偑丄奐敪偵傛傞揤慠椦偺敯嵦偍傛傃恖岺椦柺愊偺憹壛偵傛傞椦憡偺扨堦壔傗峳攑偵傛傝偦偺婡擻掅壓偑婋湝偝傟偰偄傞丅偙偺偙偲偐傜丄恖堊揑僀儞僷僋僩傪庴偗偰杮棃偺尨惗怷椦怉惗偑攋夡偝傟偨抧堟偵偍偄偰丄惗懺揑婡擻偺崅偄懡條惈偁傞怷椦偺嵞惗偲曐慡偺偨傔偺懳嶔偼媫柋偲側偭偰偄傞丅
丂丂偟偐偟丄暋嶨側怷椦惗懺宯偺暅尦偵偼庬偺惗懺摿惈偲嫟偵丄偦偺懠庬乆偺摦揑側娐嫬梫場偑娭傢傞丅偟偨偑偭偰丄偦偺庤朄偼忢偵幚尡揑僾儘僙僗傪娷傓傕偺偲側傞偑丄偄傑偩偵柧妋側巜恓傗昡壙婎弨偑妋棫偝傟偰偍傜偢丄媄弍揑偵懡偔偺壽戣傪書偊偰偄傞丅
丂丂偙偆偟偨攚宨偐傜丄杮尋媶偱偼奐戱屻曻婞偝傟偨愓抧偱偁傞憪抧偍傛傃恖岺憿椦抧側偳丄怷椦偲偟偰偺惗懺揑婡擻偺掅壓偟偨娐嫬傪懳徾偵丄懡條惈偁傞怷椦偺暅尦婡峔傪夝柧偟丄暅尦偵偍偗傞栤戣揰偲夵慞嶔傪帵偡偙偲傪栚揑偲偡傞丅
2. 尋媶偺曽朄
丂丂杮尋媶偱偼丄杒奀摴抦彴敿搰幬棦挰娾旜暿偺奐戱愓抧偵偍偗傞怷椦暅尦偺庢傝慻傒傪庡側尋媶懳徾偲偡傞丅奐戱偲偄偆恖堊揑僀儞僷僋僩偵傛傝杮棃暘晍偟偰偄偨尨惗揑側怷椦怉惗偑幐傢傟偨搚抧偼丄棧擾偵傛傝曻婞偝傟杚憪抧傗擇師揑憪尨丄恖岺椦側偳偺怉惗偵曄壔偟偨丅偙偺傛偆側奐戱愓抧偵偍偗傞尨惗怷椦偺暅尦偵偼丄(1) 憗婜偵堦師揑側怷椦傪憿惉偡傞偙偲偵傛傝庡偵暔棟揑側娐嫬偺夵慞傪恾傞偙偲丄偁傞偄偼 (2) 廃曈偵巆懚偡傞曣庽椦傗搚忞僔乕僪僶儞僋偐傜偺揤慠峏怴傪懀恑偝偣傞庤朄偑偁傞丅偟偐偟丄懡條壔巤嬈偵偍偄偰偼峏怴偵懳偡傞慾奞梫場偺塭嬁傕偁傝丄堎側偭偨娐嫬壓偱偼偦偺掱搙傕堎側傞丅
丂丂杮尋媶偱偼丄奐戱愓抧偺怉惗棜楌傪攃埇偟丄怉惗偺曄壔僷僞乕儞傪柧傜偐偵偟偨偆偊偱丄峏怴偵塭嬁偡傞梫場傪拪弌偟丄懡條壔偺慾奞梫場偵偮偄偰専徹偡傞丅傑偨丄庽庬摫擖偵傛傞堦師椦憿惉偺惗堢忬嫷偲懡條壔巤嬈偵傛傞怷椦偺庬峔惉偍傛傃峔憿偺曄壔偵偮偄偰丄懳徠嬫偲偺斾妑偵傛傝挷嵏夝愅偟丄暅尦庤朄偺専徹傪峴偆丅
2005擭搙丂尋媶栚昗
1) 奐戱抧偵偍偗傞搚抧棙梡偲怉惗偺曄慗
尋媶懳徾抧偼丄1910擭戙偵奐戱偑巒傑傝1966擭埲崀偼棧擾偵傛傝曻婞偝傟丄偦偺屻堦晹偼怉椦偝傟嬤擭偼怷椦嵞惗帠嬈偑峴傢傟偰偄傞丅擖怉埲崀偺怉惗偺曄慗恾傪嶌惉偟丄搚抧棙梡偲偺娭學偵偮偄偰峫嶡偡傞偲偲傕偵丄怉惗曄壔偺掕検揑昡壙傪峴偆丅
2) 怷椦嵞惗帠嬈偺専徹
尰嵼偺奐戱愓抧偺怉惗忬嫷傪孮廤惗懺妛揑庤朄偵傛傝挷嵏偟丄夁嫀偺挷嵏帒椏偲偺斾妑偐傜庬慻惉偺曄壔傪柧傜偐偵偡傞丅
儁乕僕偺愭摢傊
乽婥岓曄摦偑拵攠壴怉暔偺憲暡嫟惗宯偵媦傏偡塭嬁梊應乿
惗暔寳壢妛愱峌丂惗暔懡條惈僐乕僗
攷巑屻婜壽掱侾擭丂堜揷釳乮巜摫嫵堳丗岺摗妜乯
尋媶寁夋
丂丂嬤擭偺恖娫妶摦偵傛傞抧媴壏抔壔偁傞偄偼婥岓曄摦偼丄惗暔娐嫬偵塭嬁傪梌偊丆惗暔懡條惈偺尭彮傪堷偒婲偙偟偰偄傞丅惗暔懡條惈偺尭彮偼丄惗懺宯傪宍惉偡傞惗暔娫偺條乆側嫟惗宯偺曵夡偵傛傝壛懍偝傟傞偲峫偊傜傟丄偦偺塭嬁梊應偵偼懡條側嫟惗宯傪惗傒弌偡僾儘僙僗偺夝柧偑晄壜寚偱偁傞丅杮尋媶偱偼丄棨堟惗懺宯偵偍偄偰懡條側恑壔傪悑偘偰偄傞堐娗懇怉暔偺斏怋僔僗僥儉偲憲暡嫟惗宯偺娭學偵拝栚偟丄壴暡攠夘崺拵偺峴摦偵娭楢偟偨怉暔偺斏怋愴棯宍惉僾儘僙僗偺夝柧偲憲暡嫟惗宯偺娐嫬曄摦偵懳偡傞姶庴惈偺夝柧傪栚揑偲偡傞丅摿偵丄抧媴壏抔壔偵傛傞婥岓曄摦偑丄怉暔偺斏怋惉岟偵梌偊傞塭嬁偵偮偄偰丄怉暔偲壴暡攠夘崺拵偺憡屳嶌梡偺娤揰偐傜梊應傪帋傒傞丅
丂丂憲暡嫟惗宯偺懡條惈堐帩婡峔傪夝柧偡傞偵偼丄孮廤峔惉怉暔偲壴暡攠夘崺拵偺憡屳娭學栐傪棟夝偡傞昁梫偑偁傞丅孮廤撪偵嫟懚偡傞怉暔偼丄奺乆偑摿挜揑側斏怋愴棯傪帩偭偰偍傝丄偦傟偵寢傃偮偄偨憲暡嫟惗娭學傪帩偭偰偄傞偲梊憐偝傟傞丅椻壏懷偺戙昞揑側怉惗偱偁傞棊梩峀梩庽椦偵偍偗傞憲暡崺拵憡偼丄摿掕怉暔庬傪愱峌朘壴偡傞僴僫僶僠椶乮僗儁僔儍儕僗僩乯偲丄僴僄丒僴僫傾僽椶偵戙昞偝傟傞懡條側怉暔偵朘壴偡傞崺拵椶乮僕僃僱儔儕僗僩乯偵戝暿偝傟傞丅偙偺揟宆揑側俀偮偺僞僀僾偺堘偄偵拝栚偟丄嬶懱揑偵埲壓偺揰偵偮偄偰尋媶偡傞丅傑偨丄摨帪偵懡條側庬偑嫟懚偡傞奀昹抧堟側偳偵偍偗傞挷嵏傪幚巤偡傞偙偲偵傛傝丄僶僀僆乕儉偺堎側傞怉暔孮廤娫偵偍偗傞婥岓曄摦偺塭嬁偺嵎堎傪柧傜偐偵偡傞偙偲傪栚揑偲偡傞丅
丒億儕僱乕僔儑儞僞僀僾偵墳偠偨怉暔偺岎攝條幃偺夝柧
丂丂怉暔偺岎攝條幃偺攃埇丄媦傃壴暡攠夘崺拵偺僞僀僾側傜傃偵峴摦僷僞乕儞偵傛傞憲暡幰偲偟偰偺昡壙傪峴偆丅傑偨丄怉暔偺斏怋惉岟偺掱搙乮検揑丗寢幚惉岟偵傛傞昡壙丄幙揑丗帺怋棪偵傛傞昡壙乯偲億儕僱乕僔儑儞僞僀僾偵娭楢偟偨斏怋愴棯偺攃埇偵傛傝丄壴暡攠夘幰偺僞僀僾偵墳偠偨岎攝條幃丄媦傃帺怋偵傛傞斏怋偺曗彏偺掱搙傪専弌偡傞丅
丒壴暡攠夘崺拵偺曄摦偑怉暔偺斏怋惉岟偵媦傏偡塭嬁偺昡壙
丂丂壴暡攠夘崺拵偺弌尰昿搙偺棳摦惈偑怉暔偺斏怋惉岟偵塭嬁偡傞掱搙傪丄惗堢応強娫曄摦偲擭曄摦偵墳偠偨壴暡惂尷偺掱搙偲帺怋棪偺曄壔偵傛傝夝柧偡傞丅怉暔偲壴暡攠夘崺拵偺弌尰帪婜偺晄堦抳偼丄僗儁僔儍儕僗僩僞僀僾偺怉暔偵廳戝側懝幐傪傕偨傜偡偑丄懡條側壴暡攠夘崺拵偲娚傗偐側娭學傪帩偮僕僃僱儔儕僗僩僞僀僾偵偼塭嬁偑彮側偄偐傕偟傟側偄丅帺怋棪偺曄壔偺攃埇偵傛傝丄僕僃僱儔儕僗僩僞僀僾偺庬巕惗嶻偺埨掕惈偑懡條側壴暡攠夘崺拵偺懚嵼偵傛傝堐帩偝傟偰偄傞偺偐丄帺怋偵傛傞曗彏嶌梡偵傛傝堐帩偝傟偰偄傞偺偐傪嬫暿偡傞丅
丒憲暡嫟惗宯偺娐嫬曄摦偵懳偡傞姶庴惈偺昡壙
丂丂僗儁僔儍儕僗僩偲偺憲暡嫟惗宯傛傝僕僃僱儔儕僗僩偲偺憲暡嫟惗宯偺曽偑曄摦娐嫬壓偱偼埨掕偟偰偄傞丄偲偄偆嶌嬈壖愢偺専徹傪峴偆丅孮廤撪偵偍偗傞億儕僱乕僔儑儞僔儞僪儘乕儉偲岎攝條幃偺娭學偐傜丄曄摦娐嫬壓偵偍偗傞奺憲暡嫟惗宯偺埨掕惈傪梊應偡傞棟榑儌僨儖傪峔抸偟丄応強娫曄摦傗擭曄摦傪壛枴偟偨僔儈儏儗乕僔儑儞偵傛傝丄婥岓曄摦偑憲暡嫟惗宯偵媦傏偡塭嬁偺梊應傪帋傒傞偲偲傕偵丄僶僀僆乕儉偺堎側傞孮廤傪斾妑偡傞偙偲偵傛傝丄惗暔偵梌偊傞堦斒揑側塭嬁偲丄僶僀僆乕儉偛偲偺摿堎揑側塭嬁偺専弌傪帋傒傞丅
儁乕僕偺愭摢傊
乽暢傪梡偄偨傾儉乕儖僸儑僂偲僔儀儕傾僩儔偺堚揱揑夝愅乿
娐嫬婲妛愱峌丂婲妛尋媶僐乕僗
攷巑屻婜夁掱堦擭丂悪杮 懢榊乮巜摫嫵姱丗搶惓崉乯
尋媶攚宨媦傃栚揑
丂丂丂儘僔傾嬌搶偺増奀廈撿晹偵偺傒惗懅偡傞愨柵婋湝庬偱偁傞傾儉乕儖僸儑僂Panthera pardus orientalis偼丄懌愓媦傃帺摦嶣塭挷嵏偵傛傝丄30摢慜屻惗懅偟偰偄傞偲偄傢傟偰偄傞丅偙偺抧堟偵偼丄摨偠偔愨柵婋湝庬偱偁傞僔儀儕傾僩儔Panthera tigris altaica傕惗懅偟偰偄傞丅惗懅堟偼丄傾儉乕儖僸儑僂偵斾傋偰梱偐偵戝偒偔丄増奀廈媦傃僴僶儘僼僗僋廈撿晹偵峀偑傝丄偦偺屄懱悢偼400摢慜屻偲偄傢傟偰偄傞丅
尰嵼丄偙偺擇庬偑惗懅偡傞儘僔傾嬌搶偵偍偄偰丄怺崗側惗懅抧攋夡偑恑峴偟偰偄傞丅戝婯柾側怷椦敯嵦偑惙傫偵峴傢傟偰偍傝丄傑偨搙乆敪惗偡傞嶳壩帠偵傛傞塭嬁偼嬌傔偰戝偒偄丅増奀廈偵偼偄偔偮偐帺慠曐岇嬫偑懚嵼偟偰偄傞偑丄偄偢傟傕揰嵼偟偰偍傝丄揝摴傗姴慄摴楬偵傛傞惗懅抧偺暘抐壔傕栤戣偲側偭偰偄傞丅偙偺傛偆側惗懅抧傪庢傝姫偔娐嫬偺埆壔偼丄愨柵婋湝庬偱偁傞偙偺擇庬偺屄懱悢偺尭彮傪彽偄偰偄傞丅尰嵼丄WCS (Wildlife Conservation Society)傪拞怱偲偟偰丄摦暔墍屄懱傪傕偲偵偟偨傾儉乕儖僸儑僂偺戞擇偺屄懱孮傪峔抸偡傞寁夋偑媍榑偝傟偰偄傞偑丄偙偺寁夋偺幚巤偺偨傔偵傕丄尰懚偡傞屄懱孮偺堚揱揑峔憿傪柧傜偐偵偡傞偙偲偼廳梫偱偁傞丅傑偨丄偙傟傜婓彮庬偺堚揱揑峔憿傪柧傜偐偵偡傞偙偲偼丄惗暔懡條惈偺娤揰偐傜傕嬌傔偰廳梫偱偁傞丅
丂偙偺傛偆側婓彮庬偵懳偡傞堚揱妛揑夝愅偵偼丄懳徾摦暔偵捈愙怗傟傞偙偲側偔DNA傪摼傞偙偲偑偱偒傞暢偑桳岠偱偁傞丅杮尋媶偱偼丄傾儉乕儖僸儑僂偲僔儀儕傾僩儔偺屄懱孮曐慡傪栚巜偟丄暢偐傜拪弌偟偨DNA傪梡偄偰丄偦偺曪妵揑側堚揱揑夝愅傪栚揑偲偡傞丅
尋媶寁夋
丂丂廋巑壽掱偺尋媶偵偍偄偰丄暢偺庬敾掕媦傃惈敾掕曽朄傪妋棫偟偨丅2002乣03偺搤婫偵傾儉乕儖僸儑僂偺惗懅抧偵偍偄偰嵦庢偝傟偨暢傪梡偄偰丄埲壓偺偙偲傪峴偆丅
乮侾乯 屄懱幆暿朄偺妋棫
丂丂偄偔偮偐偺DNA拪弌曽朄傪帋偟丄傛傝拪弌岠棪偺傛偄曽朄傪慖戰偡傞丅偡偱偵僗儅僩儔僩儔傗僀僄僱僐偱奐敪偝傟偰偄傞儅僀僋儘僒僥儔僀僩僾儔僀儅乕偺拞偐傜巊梡偡傞堚揱巕嵗傪慖戰偟偨屻丄偦偺堚揱巕嵗傪憹暆偡傞僾儔僀儅乕傪梡偄偰暢偺堚揱巕宆傪寛掕
乮俀乯 堚揱揑懡條搙偺應掕
丂丂Control region偺堦晹傪憹暆偡傞摿堎揑僾儔僀儅乕傪奐敪偟丄墫婎攝楍傪寛掕丅儅僀僋儘僒僥儔僀僩暘愅媦傃Control
region側偳偺墫婎攝楍偐傜丄堚揱揑懡條搙傪應掕
乮俁乯 屄懱孮僒僀僘偺悇掕
丂丂偡傋偰偺暢偺堚揱巕宆傪寛掕偟丄摨堦堚揱巕宆偺暢偺弌尰昿搙偐傜Mark-Recapture
method傪梡偄偰屄懱孮僒僀僘偺悇掕傪峴偆
儁乕僕偺愭摢傊
乽娐嫬曄壔偵墳偠偨儈僕儞僐偺宍懺曄壔偺暘巕婡峔乿
惗暔寳壢妛愱峌丂惗懺堚揱妛僐乕僗
攷巑壽掱1擭丂崱堜丂崃栘乮巜摫嫵姱丗嶰塝揙乯
尋媶栚揑
丂丂儈僕儞僐偵偍偄偰曔怘幰偵桿摫偝傟傞昞尰宆懡宆偺敪惗惂屼婡峔傪柧傜偐偵偡傞偙偲傪栚揑偲偟偰娐嫬僔僌僫儖傪庴偗偨屄懱偺惗棟揑曄壔偐傜丄宍懺宍惉偵帄傞敪惗妛揑夁掱傪徻嵶偵夝愅偡傞丅摿偵丄宍懺桿摫偺暘巕敪惗婡峔偺夝柧偵庡娽傪抲偔丅
尋媶撪梕
丂丂尋媶偵偼丄悽奅奺抧偵峀偔暘晍偟帞堢偟傗偡偔丄偄傑僎僲儉夝愅傗宍懺曄壔偵娭偡傞惗懺妛揑側尋媶偑恑傫偱偄傞儈僕儞僐乮Daphnia
pulex乯傪庡偲偟偰梡偄傞丅
侾丏宍懺曄壔偵偍偗傞慻怐宍懺妛揑尋媶
丂丂宍懺偍傛傃慻怐曄壔夁掱偺徻嵶側娤嶡傪峴偆丅儈僕儞僐偺屻摢晹撍婲傗愲摢偼丄忋旂嵶朎偲奺嵶朎僒僀僘偺憹戝偺寢壥偲峫偊傜傟偰偄傞傕偺偺丄慻怐宍懺妛丄敪惗妛揑側曬崘偼旕忢偵彮側偄丅宍懺曄壔帪婜傗宍惉夁掱傪慻怐丒嵶朎儗儀儖偱柧傜偐偵偡傞偨傔偵丄僇僀儘儌儞敇業屄懱偺棏偐傜泱敪惗丄偦偟偰杊屼宍懺傪傕偮傑偱偺夁掱偵偍偄偰丄奜晹宍懺偍傛傃撪晹宍懺傑偨偼慻怐曄壔夁掱傪宍懺寁應丒憱嵏揹巕尠旝嬀偵傛傞娤嶡傗慻怐愗曅傪嶌惉偡傞偙偲偵傛傝丄徻嵶偵娤嶡偡傞丅昞柺峔憿偍傛傃丄愲摢傗撍婲偺撪晹峔憿傪柧傜偐偵偡傞丅
俀丏杊屼宍懺宍惉偵娭傢傞岓曗堚揱巕偺扵嶕
丂丂侾乯偵偍偗傞宍懺曄壔夁掱丄帪婜偺徻嵶側娤嶡偐傜丄捠忢屄懱偲杊屼宍懺宍惉屄懱偲偱敪惗妛揑嵎堎偑惗偠傞僗僥乕僕傪摿掕偡傞丅偦傟傜偺帪婜偵偍偗傞摿堎揑偵敪尰偡傞堚揱巕敪尰傪丄Differential
display朄傪梡偄偰斾妑偟丄敪惗抜奒傑偨偼宍懺摿堎揑堚揱巕偺摨掕傪峴偆丅傑偨丄偙傟偲暯峴偟偰丄僔儑僂僕儑僂僶僄傗傾儖僥儈傾側偳偱抦傜傟偰偄傞宍懺宍惉偵廳梫側栶妱傪偡傞堚揱巕乮wg,dpp,hh,Dll側偳乯傪儈僕儞僐偱僋儘乕僯儞僌偡傞丅
俁丏敪尰摦懺偺夝愅
丂丂俀乯偵傛偭偰丄宍懺宍惉帪偵摿堎揑偵敪尰偟偰偄傞岓曗堚揱巕偺扵嶕傪峴偄丄偙傟傜偺堚揱巕偺敪尰検偍傛傃敪尰偺嬊嵼傪夝愅偡傞丅嬶懱揑偵偼丄Real-time掕検PCR傪梡偄偰丄惉挿夁掱偵偍偗傞敪尰検偺曄壔傪挷傋傞丅傑偨丄in situ僴僀僽儕僟僀僛乕僔儑儞偵傛偭偰丄敪尰晹埵傪摿掕偡傞丅
係丏 梒庒儂儖儌儞偱宍懺桿摫傪帋傒傞
丂丂儈僕儞僐椶偼扨堊惗怋傪峴偭偰偄傞偑娐嫬偺埆壔乮崅枾搙丄抁擔丄塧帒尮晄懌側偳乯偵傛傝梇傪惗偠椉惈惗怋傪峴偆偙偲偑抦傜傟偰偄傞丅嵟嬤偱偼丄崺拵傗峛妅椶傑偨僆僆儈僕儞僐偱梒庒儂儖儌儞傗梒庒儂儖儌儞條暔幙偑惈寛掕偵娭楢偟偰偄傞偲偄偆曬崘偑偁傞丅梒庒儂儖儌儞偼丄崺拵偱偼僔儘傾儕偱暫戉僇乕僗僩傪桿摫偡傞偙偲傗丄僐僆儘僊偺扨憷丒挿憷宆偺寛掕婡峔偵梡偄傜傟偰偄傞偙偲偑抦傜傟偰偄傞丅偙偺偙偲偐傜峛妅椶傗儈僕儞僐偺宍懺曄壔偺桿摫傊偺娭梌偑悇應偝傟傞偨傔梒庒儂儖儌儞傗梒庒儂儖儌儞條暔幙傪梡偄偰宍懺曄壔桿摫傪帋傒傞丅桿摫偝傟傟偽宍懺宍惉傊偺撪暘斿宯偺娭梌偑帵嵈偝傟傞丅嬶懱揑偵偼僓儕僈僯側偳偺峛妅椶偱儂儖儌儞偲偟偰妋棫偝傟偰偄傞僼傽儖僱僙儞巁儊僠儖側偳傪梡偄傞丅偙傟傜偺儂儖儌儞偱忋婰偺堚揱巕偺敪尰偑桿摫傑偨偼梷惂偝傟傞偐傪夝愅偡傞丅偳偺傛偆側惗棟忦審偑宍懺宍惉偵塭嬁傪梌偊傞偐惗棟妛揑側帇揰偐傜傕宍懺宍惉儊僇僯僘儉偺夝柧傕帋傒傞丅
俆丏宯摑娫偱偺杊屼宍懺宍惉條幃偺斾妑
丂丂僼僒僇暔幙偵傛偔斀墳偡傞宯摑偼僼僒僇偺懡偄屛徖偵惗懅偟偰偄傞孹岦偑偁傞丅傑偨摨宯摑偱偁偭偰傕宍懺曄壔搙崌偄偺堎側傞傕偺偑懚嵼偡傞丅傑偨栰奜偐傜偙傟傜偺宯摑傪嵦廤偟敪尰摦懺偺夝愅寢壥偲曔怘幰枾搙偲斾妑偡傞偙偲偱丄杊屼宍懺宍惉婡峔偺恑壔偵偮偄偰峫嶡偡傞丅
丂丂埲忋偺寢壥傛傝丄曔怘幰僇僀儘儌儞偵傛偭偰桿摫偝傟傞宍懺曄壔儊僇僯僘儉傪慻怐妛揑丄堚揱妛揑娤揰偐傜峫嶡傪峴偆丅儈僕儞僐偺惗妶巎愴棯偲枾愙偵娭楢偟偨宍懺曄壔偺暘巕婡峔傪扵傞偙偲偱丄娐嫬梫場偲昞尰宆敪尰偲偺憡屳嶌梡偑丄悈奅惗懺宯偺懡條惈傪巟偊傞忋偱壥偨偟偨栶妱偵偮偄偰傕棟夝傪怺傔傞偙偲傪栚昗偲偟偰尋媶傪恑傔偰偄偒偨偄丅
擭師寁夋
乮侾丄俀擭栚乯
丂丂儈僕儞僐偍傛傃丄僼僒僇偺帞堢宯傪妋棫偡傞丅傑偨丄僼僒僇僇僀儘儌儞傪梡偄偰妋幚偵儈僕儞僐偺宍懺曄壔屄懱傪桿摫偱偒傞傛偆偵桿摫宯傪妋棫偡傞丅
丂丂師偵曔怘幰偵傛傞宍懺曄壔偵偍偗傞慻怐宍懺夵曄偺夁掱傪丄憱嵏揹巕尠旝嬀偍傛傃僷儔僼傿儞愗曅傪嶌惉偟娤嶡丒婰榐偡傞偲偲傕偵丄尠挊側宍懺曄壔偑惗偠傞帪婜傪摿掕偡傞丅傑偨Differential
Display朄偵傛偭偰宍懺曄壔偵摿堎揑側堚揱巕偺専嶕傗摿堎揑堚揱巕偺岓曗偵偮偄偰嵞尰惈傪妋擣偟丄敪尰検丒敪尰晹埵丒敪尰帪婜偺夝愅傪峴偆丅暯峴偟偰婛抦偺宍懺宍惉場巕偺僋儘乕僯儞僌傪峴偄丄敪尰偵嵎偺偁傞岓曗傪摿掕偡傞丅梒庒儂儖儌儞側偳偵傛傞丄宍懺曄壔偺恖堊揑桿摫偺幚尡宯偺奐敪傪帋傒丄偝傜偵偦偺宯傪梡偄丄忋婰偱摼傜傟偨堚揱巕孮偺敪尰摦懺傪夝愅偡傞丅
乮俁擭栚乯
丂丂侾擭栚偵堷偒懕偒丄宍懺曄壔帪偵摿堎揑偵敪尰偡傞堚揱巕偺敪尰夝愅傪惛椡揑偵峴偆丅
丂丂摼傜傟偨寢壥傪憤崌偟丄僇僀儘儌儞庴梕偐傜撍婲峔憿宍惉偵帄傞敪惗僾儘僙僗丄敪尰僷僞乕儞偺僾儘僼傽僀儖偵敽偆堚揱巕傪惍棟偡傞丅摼傜傟偨堚揱巕偺偆偪丄廳梫側婡擻傪壥偨偡偲峫偊傜傟傞傕偺偺婡擻夝愅傪丄RNAi側偳偺曽朄傪梡偄偰帋傒傞丅埲忋摼傜傟偨寢壥偵偮偄偰暘巕敪惗妛揑丒惗懺敪惗妛揑娤揰偐傜峫嶡傪峴偄丄崙嵺帍偵搳峞偟攷巑榑暥偵傑偲傔傞丅彨棃揑偵偼庬娫傗宯摑娫偱宍懺宍惉場巕傗敪尰摦懺傪斾妑偟丄廳梫側堚揱巕偺暘巕恑壔偵娭偡傞峫嶡傪峴偆偙偲偱丄宍懺偺懡條惈傗娐嫬墳摎偺恑壔夁掱傪峫嶡偡傞丅
儁乕僕偺愭摢傊
乽僇乕儃儞僫僲僠儏乕僽傪梡偄偨娐嫬廋暅媄弍偺奐敪乿
娐嫬暔幙壢妛愱峌丂惗懱暔幙壢妛僐乕僗
攷巑壽掱1擭丂慮崻峅徍乮巜摫嫵姱丂屆寧暥巙丂彆嫵庼乯
丂丂廬棃偺擔杮偼岺嬈媄弍偺敪払偲嫟偵丄悈幙丄戝婥偍傛傃搚忞傪墭愼偟偰偄偨丅惌晎偼墭愼傪怘偄巭傔傞偨傔偵丄娐嫬婎杮朄丄悈幙墭戺杊巭朄丄戝婥墭愼杊巭朄偍傛傃搚忞墭愼懳嶔朄傪惂掕偟丄娐嫬傊偺晧壸偑嵟掅尷偵梷偊傜傟偮偮偁傞丅峏偵嬤擭偵偍偄偰偼丄夁嫀偵墭愼偝傟偨娐嫬傪廋暅偡傞庤朄偑拲栚偝傟偰偄傞丅
丂偦偙偱丄悈幙偍傛傃搚忞偺墭愼暔幙彍嫀曽朄傪奐敪偡傞偨傔偺尋媶傪峴偆丅嬶懱揑側庤朄偲偟偰偼丄僇乕儃儞僫僲僠儏乕僽傪巊梡偡傞丅僇乕儃儞僫僲僠儏乕僽偵偼妶惈扽摨條偵丄慳悈惈偺桳婡暔傪嫮屌偵媧拝偝偣傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅偟偐偟側偑傜丄僇乕儃儞僫僲僠儏乕僽偺昞柺愊偺戝偒偝埲奜偺妶惈扽偵懳偡傞桪埵惈偼丄扨憌媦傃懡憌峔憿傪偲傞揰偵偁傝丄杮尋媶偱偼丄懡憌僇乕儃儞僫僲僠儏乕僽傪梡偄傞丅側偤側傜偽丄懡憌僇乕儃儞僫僲僠儏乕僽偼榋堳娐偱慻傒崌傢偝傟偨僔乕僩傪懡憌偵墌摏忬偵姫偄偨峔憿傪庢傞偙偲偵傛偭偰丄嫮搙偑嫮偔丄壔妛揑偵埨掕偱偁傞偲嫟偵丄桳婡暔偵懳偟偰崅偄曔廤岠壥傪帩偮帠偑抦傜傟偰偄傞偐傜偱偁傞丅峏偵丄偁傜偐偠傔僉儗乕僩擻傪帩偮桳婡壔崌暔傪媧拝偝偣偰偍偗偽丄悈拞偺桳奞側桳婡暔幙傪曔廤偡傞偲嫟偵丄廳嬥懏椶傪傕曔廤偡傞偙偲偑婜懸偱偒傞丅偦傟屘丄帠嬈強偱栤戣偵側傝偑偪側丄俠俷俢丄俛俷俢偍傛傃僲儖儅儖僿僉僒儞拪弌暔幙偺抣傪傕摨帪偵尭彮偝偣傞偙偲傕婜懸偱偒傞丅偙傟傪丄崅暘巕枌偵曪傓偙偲偵傛傝丄僒僀僘攔彍擻偲媧拝慖戰惈傪帩偨偣偮偮丄幚梡壔傪栚巜偡丅偙偺庤朄傪儀乕僗偲偟偰丄悈宯偺娐嫬廋暅偲娐嫬墭愼暔幙攔弌検嶍尭曽朄傪峫埬偡傞丅
丂杮尋媶偼丄俠倓丄俹倐丄俥倕丄倁俷俠倱丄俠俷俢丄俛俷俢偍傛傃僲儖儅儖僿僉僒儞拪弌暔幙傪尭彮偝偣傞庤朄傪峫埬偡傞丅壗屘側傜偽丄俠倓偍傛傃俹倐偵偼娐嫬婎弨偍傛傃攔悈婎弨傪挻偊傞悈偼柵懡偵側偄偑丄揝峾嬈側偳偺岺応宯攔悈偺傒側傜偢丄搚忞桼棃偱抧壓悈偵怹弌偟偰墭愼偟偨応崌丄怺崗側栤戣偵側傞丅堸椏悈偱栤戣偵側傞俥倕偼丄屆偄攝娗傪梡偄偨悈摴悈偐傜専弌偝傟傞丅傑偨丄倁俷俠倱偼堸椏悈嶦嬠梡偺師垷墫慺巁桼棃丄帠嬈強偱偺愻忩傕偟偔偼扙帀傪婲場偲偟偰攔弌偝傟傞墫慺壔崌暔偲愇桘惛惢傗偙傟傪巊梡偡傞壔妛岺応攔悈偵娷傑傟傞朏崄懓偑婎弨抣傪挻偊偰栤戣偵側傞帠偑偁傞丅傑偨丄俠俷俢丄俛俷俢偍傛傃僲儖儅儖僿僉僒儞拪弌暔幙偼堸怘偍傛傃媼桘嬈傪昅摢偵丄婎弨抣傪挻偊傞帠偑偟偽偟偽偁傞丅偙傟傜偺栤戣傪夝寛偡傞偨傔偵丄埲壓偺寁夋傪棫偰偨丅
傑偢丄媧拝慺嵽偺宍忬丄枌傪宍惉偡傞崅暘巕偍傛傃廳嬥懏傪曔廤偡傞僉儗乕僩帋栻傪慖掕偟丄廳嬥懏傪慖戰揑偵彍嫀偡傞慺嵽偺嶌惉傪帋傒傞丅偙偺枌傪嶌惉偡傞偙偲偵傛偭偰丄摿偵娐嫬拞偱栤戣偵側傝偑偪側俠倓偍傛傃俹倐傪拞怱偲偟偨廳嬥懏椶偺彍嫀傪峴偆丅摨帪偵丄枌撪偵僇乕儃儞僫僲僠儏乕僽傪暘嶶偝偣丄倁俷俠倱傪娷傓桳奞桳婡壔崌暔彍嫀傪壜擻偲偡傞慺嵽偺奐敪傪峴偆丅偙偺擇偮偺庤朄傪慻傒崌傢偣傞帠偵傛傝丄廳嬥懏椶偺慖戰揑彍嫀偲桳奞桳婡壔崌暔彍嫀偲偄偆丄俀庬椶偺桳奞暔幙椶傪彍嫀偡傞偙偲偑壜擻側怴婯娐嫬廋暅僇乕儃儞僫僲僠儏乕僽慺嵽偺奐敪傪峴偆丅
儁乕僕偺愭摢傊
`Title: Construction of alkalic tephrochronogogical framework in the Japan/East
Sea for testing the synchronization of abrupt changes during the Late Quaternary`
Division: Division of Environmental Science Creation
Lim, Chungwan (Mentor Professor: Kazuhiro Toyoda)
丂丂The importance of establishing the precise rate and mode of climate
response in different parts of the world cannot be over-emphasized in global
paleoclimate. Tephrochronology provides time-parallel marker horizons that
allow precise correlation between environmental and climatic records of
the past. But the detection of cryptotephra horizons (tephra horizons that
are invisible to the naked eye) for addressing abrupt climatic change has
never been examined until quite recently. Recently, it is demonstrated
that instrumental neutron activation analysis (INAA) is useful for the
supersensitive and effective detection of alkalic tephras, as well as the
identification of the source volcanoes. The tephra framework should be
tougher based on the detection and the identification of some unknown alkalic
explosive volcanism that provides many distal tephra layers to the Japan/East
Sea and the Japan island arc.
丂丂Therefore, I plan to investigate many piston core samples in conjunction
with the Ocean Research Institute at the University of Tokyo of Japan and
National Institute of advanced Industrial Science and Technology (AIST)
in Japan and Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources in Korea.
The objective of this study is the construction of alkalic tephrochronogogical
framework by INAA performance throughout many cores from Japan/East Sea.
This research on the alkaline cryptotephras, which would be found to occur
in and around Japan and Korea, will make it possible to find further correlation
and to identify palaeo-environmental record (palaeoceanographic, terrestrial,
sea-level and geomorphic) of tephra events. The information should be utilized
to estimate the development of new methodology and to capable of coaxing
small amounts from the most obdurate samples, so that time frames and site-linkage
techniques that were used in past environmental studies are improved in
terms of future environmental studies in Earth.
儁乕僕偺愭摢傊
尋媶寁夋偺儁乕僕傊