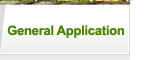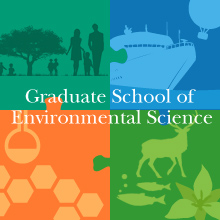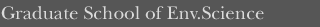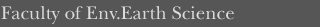研究院アワー2012年1月17日(火) 太陽光発電量予測に向けた気象庁現業モデルの日射量予測の検証
2011-12-16日時:2012年1月17日(火) 17:00〜18:30
場所:大学院地球環境科学研究院講義棟D101室
演題:太陽光発電量予測に向けた気象庁現業モデルの日射量予測の検証
講演者:大竹 秀明 博士
(産業技術総合研究所 太陽光発電工学研究センター 特別研究員)
座長:藤井 賢彦 准教授(統合環境科学部門 実践・地球環境科学分野)
講演内容:再生可能エネルギーを利用した発電の一つに太陽光発電(Photovoltaics, PV)がある。PVシステムでは日射(短波放射)量により発電量が変化する。太陽光発電電力の主な変動要因である気象要素の予測は太陽光発電電力の推定や他の発電システムと連帯した電力系統の安定化を図るためにも必要である。最近の発電量予測に関連した研究については大関(2010)によるレビュー報告がある。また, 気象庁GPVデータを用いた工学的モデルによる発電量予測の研究も行われている(Fonseca Jr. et al. 2011)。(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のロードマップによると、2030年までに約10GW/年のPVが国内で生産・導入することが検討されている。今後、日本においてPVを大量導入することを考えた場合、発電量予測に気象庁の気象モデルを利用する上で日射量予測の精度検証が重要である。
気象庁メソ気象数値予報モデル(MSM)の出力結果を用いて, 翌日の発電量予測を行うためには, 予測される日射量が地上の観測値に比べてどのくらいの予測誤差が含まれているのかを把握する必要がある。気象庁ではルーチン的な日射量予測の検証は行っているものの、PVシステムではより詳細な時間・空間的な予測誤差の検証が求められている。一方, MSMの積分時間は最長でも33時間であり, MSMを利用した発電量予測は前日にしか行えない。そこで全球予報モデル(GSM)の84時間予報を用いて,2,3日前に日射量がどの程度予測可能かを検討する必要もある。本研究ではMSMとGSMで予測された日射量について各気象官署地上観測データを用いて予測精度の検証を進めている。
全体的にはMSMの予測値は快晴時は観測値に近い結果を示し, モデルの放射過程は良好に働いていることを示唆していた。しかし, 夏季の雲域が広がり易い時期(梅雨期など)で予測値が観測値からばらつく傾向が見られた。また, 観測値からのずれが大きい事例を対象に雲のタイプを調べた結果, 降水の伴わないような層状性の雲が出現する場合に予測誤差が大きくなる傾向が見られた。地域的、季節的な違いを見ると、夏季の北日本ではモデルは観測値に近いが冬季はややモデルの過大傾向がみられた。また、関東付近から西日本付近では夏季のモデルの過小傾向が顕著である。南西諸島では冬季の過大傾向と夏季の過小傾向が顕著である。一方, GSMの予測値も快晴時は観測値に近い値を示していた。しかし, 雲が広がる事例ではGSMの日射量が過大に見積もられる傾向(数MJ/m2程度)がある。これは季節に依らず顕著である。このことからGSMのモデルの光学的な雲の厚さが実際よりも薄い, または雲域が広がっていないことが推測される。