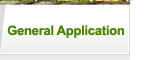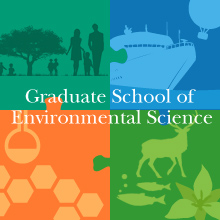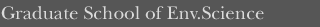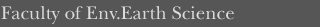研究院アワー2011年11月28日:エアロゾルの沈着が与える様々な影響について
2011-11-212011年11月28日(月) (Nov. 28, 2011) 17:00〜18:30
場所: 大学院地球環境科学研究院講義棟D101室
演題:これまでの経緯と海外での研究生活について
講演者:安成 哲平 博士
(Universities Space Research Association(USRA)客員研究員)
座長:白岩 孝行 准教授(低温科学研究所/大学院環境科学院環境起学専攻)
※対象を学院内関係者に限定させて頂きます。
講演内容: 2008年3月に北大環境科学院で学位をいただいたあと、京都の総合地球環境学研究所で1年ポスドクをした後渡米をして、2年半近くになる。久しぶりの北大訪問であるが、若手研究者が海外へ出ることでプラスになること、マイナスになること両者について今後世界へ羽ばたく若手研究者たちに有益な情報を提供できるような話を簡単にしようかと考えている。また、北大での大学院生活の中でどのような研究生活をしていたかも簡単にご紹介し、それが今の研究生活にどう影響しているかについて述べようと思う。また、本業の研究の話は時間に限りもあるが、NASA/GSFCでのメインタスクの積雪に関するモデリングのお話をしようと思う。
(NASA/GSFC全球予報モデルGEOS-5の研究)
近年ヒマラヤの氷河の後退が話題となっているが、氷河の後退に関わる要因は様々で複雑である。現在、ヒマラヤ・チベット域では、温暖化はもちろんのこと、Indo-Gangetic Plainにおけるプレモンスーン季節における大気汚染が問題となっている。この大気汚染の中に含まれるダスト(砂漠起源)やブラックカーボン(森林火災、家庭のコンロ、車などの不完全燃焼起源)は太陽光吸収性があるため、積雪表面に積もることで積雪のアルベドを下げ氷河での融解に寄与することが考えられるため、1つの氷河後退に貢献する要因として注目されている。現在NASA Goddard Space Flight CenterではGoddard Earth Observing System version 5 (GEOS-5)という全球数値予報モデルが開発されている。しかしながら、GEOS-5の従来の陸面モデル内の積雪モデルでは、単純な積雪アルベドモデルを使っており、積雪汚染の効果を考慮することはできなかった。そこで、日本で開発された積雪密度から比表面積を求めて計算する積雪アルベドスキームを元にして、そこに上記エアロゾルの太陽光吸収効果を取り入れたスキームを新たに導入した。また、GEOS-5内の化学輸送モデルからの上記エアロゾルの沈着量から直接積雪内の不純物質量濃度を計算し、その質量濃度を新しいアルベドスキームで使えるように不純物質量計算スキームも導入した。計算スキームは主に北大の大学院時代に、低温研裏で冬季に気象研の青木輝夫博士と行った観測データで検証を行ってきた。新しいGEOS-5にて、2007-2009年までの全球計算を行い、ヒマラヤ・チベット域に注目してみると、旧積雪アルベドスキームはアルベドが低すぎるために春の時期の雪の縮小が早すぎる結果を得た。一方、新しいスキームでは、旧スキームより現実的な積雪域がMODISとの比較から見られた。また、積雪汚染の効果の「ある」「なし」を新しいスキームで検討すると、明らかに有意に太陽光吸収性エアロゾルによって、積雪アルベド、積雪被覆率、積雪水量の減少が見られた。実際の氷河では、デブリ、内部凍結、流動などもあるため、この結果が直ちに氷河後退を意味するわけではないが、少なくともプレモンスーンの大気汚染がデブリカバー域でない氷河の積雪の表面融解には寄与する可能性がありうると考えられる。ヒマラヤの氷河研究の発展としては、不足している積雪汚染関連の観測データの充実と他の氷河後退要因との比較検討なども行う必要がある。
連絡先:統合環境科学部門 実践・地球環境科学分野 藤井 賢彦
(E-mail: mfujii at ees.hokudai.ac.jp, 内線: 2359)